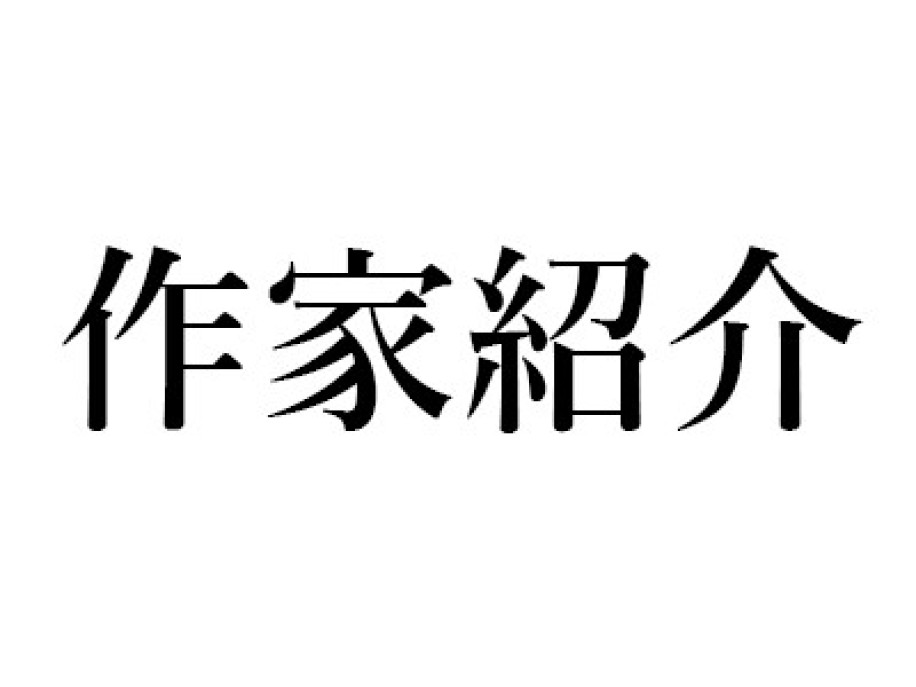書評
『ユートピアとしての本屋:暗闇のなかの確かな場所』(大月書店)
毎日のように本屋へ行く。昨日あそこにあった本が、今日はここに移動している。全ては本屋の意志だ。もちろん、本そのものが意志を持っているが、限られたスペースにそれらを配置するための選択の集積が、本屋の思考であり、客との相性を生む。
千葉市・幕張にある「本屋lighthouse」をひとりで立ち上げた著者による一冊、『ユートピアとしての本屋 暗闇のなかの確かな場所』(関口竜平著、大月書店・1870円)で「本屋には社会を変える力がある」と言い切る。そして、「『いないことにされている』存在を、あるいはそのまなざしを、本を通して現出させること」ができるとする。ネット書店が隆盛(りゅうせい)してから、従来の本屋が「リアル書店」と言われるようになったが、あの呼称に慣れたくない。口パク歌手のせいで「生声歌手」と呼ばれはしない。そもそも書店とはリアル。その場に考えを現出させることができる。
著者の本屋には、扱わないと決めている本がある。いわゆるヘイト本、そして、歴史修正主義的な本だ。とりわけこの10年近く、隣国の人々を名指しし、「〇〇人に生まれなくてよかった」と題するような本まで並ぶようになった。自分たちを肯定するために他者を引きずり落とす。これらの本を置かない理由を「社会を壊すから」「人を殺すから」とする。なにを大げさな、と思う人もいるのだろうか。そう思える優位性はどこから来るのかを考えたほうがいい。
送られてきた本を素直に並べるのが本屋の仕事であり、個々の本を判別するのは越権行為との考えも根強い。売れているからたくさん置く、売れていないから置かない、そんな従順な本屋もある。
本という産物には書き手の考えが詰まっている。読者は「私はこう思った」と感じる。ならば、その双方を結びつける場所にも、考えや思いがある。「本屋は作り手のひとり」との宣言を受け止める。今日行った本屋のあの棚は、明日にはわずかに変わる。その変化を感知できるかはわからない。簡単にわからないから、また行くのだ。
千葉市・幕張にある「本屋lighthouse」をひとりで立ち上げた著者による一冊、『ユートピアとしての本屋 暗闇のなかの確かな場所』(関口竜平著、大月書店・1870円)で「本屋には社会を変える力がある」と言い切る。そして、「『いないことにされている』存在を、あるいはそのまなざしを、本を通して現出させること」ができるとする。ネット書店が隆盛(りゅうせい)してから、従来の本屋が「リアル書店」と言われるようになったが、あの呼称に慣れたくない。口パク歌手のせいで「生声歌手」と呼ばれはしない。そもそも書店とはリアル。その場に考えを現出させることができる。
著者の本屋には、扱わないと決めている本がある。いわゆるヘイト本、そして、歴史修正主義的な本だ。とりわけこの10年近く、隣国の人々を名指しし、「〇〇人に生まれなくてよかった」と題するような本まで並ぶようになった。自分たちを肯定するために他者を引きずり落とす。これらの本を置かない理由を「社会を壊すから」「人を殺すから」とする。なにを大げさな、と思う人もいるのだろうか。そう思える優位性はどこから来るのかを考えたほうがいい。
送られてきた本を素直に並べるのが本屋の仕事であり、個々の本を判別するのは越権行為との考えも根強い。売れているからたくさん置く、売れていないから置かない、そんな従順な本屋もある。
本という産物には書き手の考えが詰まっている。読者は「私はこう思った」と感じる。ならば、その双方を結びつける場所にも、考えや思いがある。「本屋は作り手のひとり」との宣言を受け止める。今日行った本屋のあの棚は、明日にはわずかに変わる。その変化を感知できるかはわからない。簡単にわからないから、また行くのだ。
ALL REVIEWSをフォローする