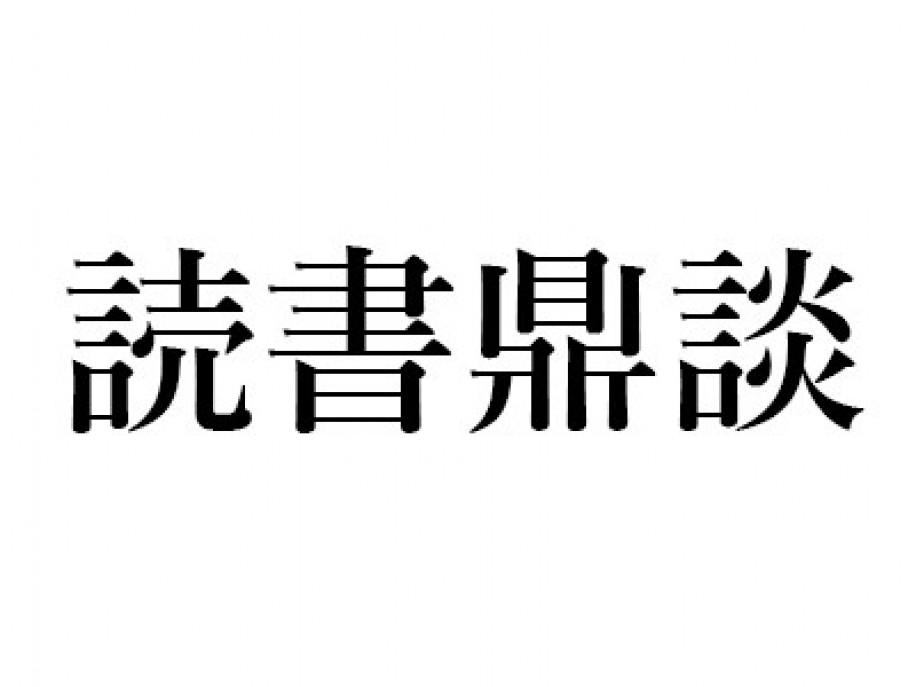書評
『ちょー日本語ドリル』(シネマサプライ)
ちょー雪ってカンジ!
これはもしかしたら、書いたことがあるかもしれないが、家人がこういうテレビ番組を見たそうだ。いまどきの女子高生ばかりを集め親孝行をやらせようというのである。集められた女子高生の中からもっともいまどきっぽい(言葉づかいもファッションも、そして親孝行なんか絶対するようなタイプではなさそうなことも)子が選ばれ、そして、親孝行の一環としてスタジオに父親を呼び、その父親に料理を作って食べてもらう――というようなことではなかったかと思う。その女子高生君はしきりに「ほんとに来るの?」と質問していたようだが、やがてスタジオにほんとに父親が現れた。その瞬間、女子高生君はこう叫んだ。「ちょー来た!」
司会者氏はその女子高生君に、「そんな日本語あるかいな」と注意をうながしたそうだが、その話を聞いたわたしは逆に、あまりに絶妙な言葉づかいに唸ってしまったのだった。
「ちょー来た!」
確かに、これは正しい日本語ではない。「副詞+来た」という用法には、「早く来た」「遅く来た」「もう来た」「よく来た」「やっと来た」があるが、「ちょー来た!」はない。
意味からいうと「ついに、やっと、ほんとに来た、でもそんなの信じられない」であろうか。しかし、「ちょー」なら一語ですむのである。
「ちょー」が現代日本語の特殊な接頭語として登場して何年になるであろう。「ちょー」は不断の進化を続け、ついに「ちょー来た!」のような複雑なニュアンスを獲得するところまで来たのである。もしかしたら、女子高生諸君たちが育んできた「ちょー」言語による新たな言文一致(明治期・昭和末期に続く第三番目という意味では新々言文一致と呼ぶべきなのかもしれない)が可能となりつつあるのであろうか。しかし、仮に新々言文一致が可能であるとして、それが文学として成立するためにはまだ解決されねばならない問題が残されている。
たとえば、あのアクセントの多様さをどう文章に移し替えられよう。
問い。次のことばのイントネーションは、①語尾上がり②平坦③語尾下がりのいずれか?
1、ちょータリ
2、とりあえずー
3、サロン
4、やばくなーい?
5、クラブ
あるいはまた、ポケベルによって開拓されつつある未知の数字言語はどのようにして文学の中に取り入れればいいのか。
問い。次の数字を通常の日本語に翻訳せよ。
50960303864-9101U
以上、解答は『ちょー日本語ドリル』(たまやJAPAN編、シネマサプライズ株式会社)を参考にするように。なお、このドリルには「ちょー日本語」による『枕草子』冒頭部分が掲載されているが、思えば橋本治の現代語訳『枕草子』も当時の(といってもそんなに昔じゃないはずだが)女子高生の口語をもとにした言文一致体が強烈なショックを読む者に与えたのだった。
それにしても口語の変化の激しさはすさまじい。
「春はやっぱ夜明け? 頃がまじキレイだよ、かなりおすすめ。うちの地元とかいってさりげにイナカなの」
なるほど。そうそう、このドリルには川端康成の『雪国』も「ちょー日本語」に翻訳されているのだった。
「ちょー雪ってカンジ!ってゆうかーちょー長いトンネルを出たら、ちょー雪ってカンジ」みたいな。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする