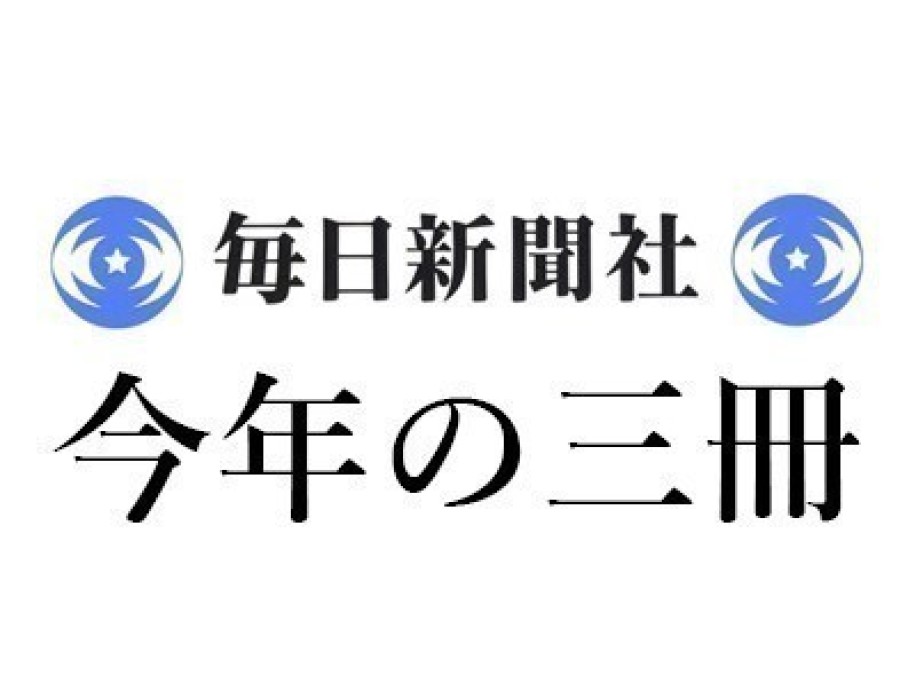書評
『精神の風通しのために 日高普著作集』(青土社)
開かれた個性、「知の巨人」の全貌
本紙の書評執筆者を長くつとめられ、二〇〇六年に八三歳で亡くなった日高普さんの著作集。私は「本を見る会」という書評執筆者の会合でこの『資本論』研究の泰斗の謦咳(けいがい)に接する機会を得たが、そのたびに老いて盛んな好奇心には驚嘆せざるをえなかった。たとえば、私がフランスの娼館(しょうかん)研究の成果を披露して日本の高級クラブのような業態は欧米では珍しいと言うと、日高さんは非常に興味を示され「よし、今度、ロンドンに行くから確かめてこよう」と語られたことがある。見極めるべき真実があれば、どんなものでもこれを究明せざるを得ない純粋な知識欲は最晩年に至るまで衰えを知らなかった。戦後文学史に残る『世代』以来の盟友である中村稔氏によって編纂(へんさん)された本書はそうした日高さんの「開かれた個性」がよく表れた本に仕上がっている。
とりわけお勧めなのが、第二部「マルクス主義」である。中越戦争やポル・ポトの大虐殺という現実を前にしたオールド・マルクス・ボーイが、人類解放の美しい夢が見るも無残な結果に終わったのはなぜかと自問した文章が集められているからだ。
マルクスは労働者は窮乏化すれば必然的に革命的になると考えた。一方、レーニンは労働者階級は自然発生的には革命的たりえないから前衛党によって革命意識を外部注入する必要があると見なした。事実、このレーニン型の前衛党組織は効率よく機能して十月革命を成功に導いたが、クロンシュタットの叛乱(はんらん)が起こったとき、レーニンはここで権力を労働者に譲ったら革命の挫折は必至だと恐れた。
「民衆が権力を監視するかわりに、権力が民衆を監視する。権力の大きな強みは情報を握っていることだ。情報は権力維持のために利用され、権力に都合の悪い情報は民衆の耳に達しにくくなる。こうして少数の、計画し、操作し、管理するものと、多数の、計画され、操作され、管理されるものとの二元的な社会が成立する。(中略)ロシアのような社会で革命のために必要欠くべからざるものとして考え出されたレーニン主義が、革命を成功させることができたとしてもそのいきつく果てはどす黒い抑圧図だということ、白が黒に転化したのはまさに必然的ななりゆきだということが、レーニンには予測できなかったのであろうか」
本書には歴史、文学、映画、演劇、科学などのエッセイや書評も多く集められているが、中で出色なのが「横光利一『旅愁』を再読して」である。「横光が日本の特殊性を強調しながら、どんな内容の特殊性を考えているのか、ぼくにはどうしてもつかめなかった。(中略)こんど読んで、おやおやと思った」。というのも、横光は日本文化の特殊性を主張するのに、本居宣長はおろか万葉も源氏物語も読んではいないのではないかと感じたからだ。それは横光に限らない。高度成長以前の日本のインテリはみな、左右の別を問わず、維新以前の日本は未開社会で、未来には明るい欧米型の社会があるという単線型史観に囚(とら)われており、「一般的な欧米文化と特殊的な日本文化と『どちらが良いと思われるのですか』という観点からしか、歴史をみることができなかった」のである。
表題にあるように、なによりも「精神の風通し」のよさを重んじ、マルクスは評価してもマルクス主義のドグマからは自由で、あらゆる分野の事象の謎を自分の頭で考えるために読書をこよなく愛した二〇世紀日本最後の「知の巨人」の全貌を知るための好著。
ALL REVIEWSをフォローする