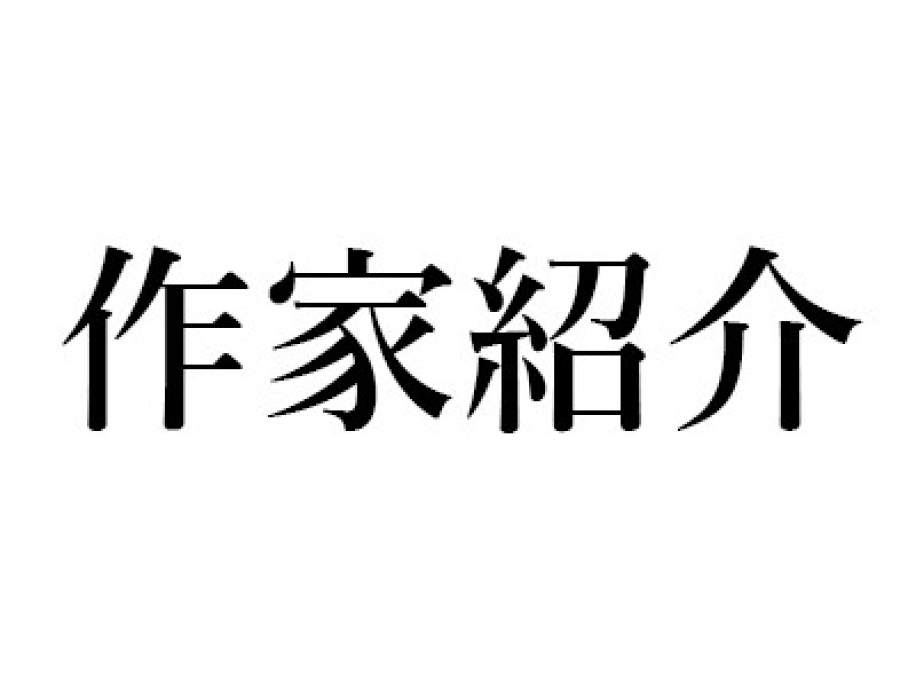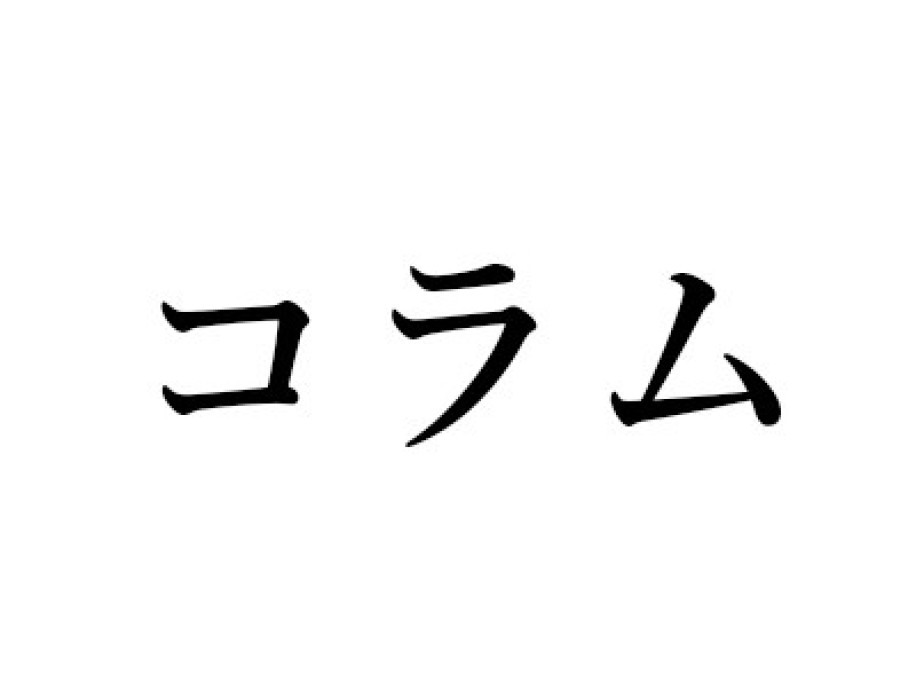書評
『漱石を読む―日本文学の未来』(福武書店)
今年のNo.1『漱石を読む』にぼくが傍線を引いた所
今年いちばん面白かった本は小島信夫の『漱石を読む―日本文学の未来』(福武書店)で、これ、連載中は副題の方の『日本文学の未来』がタイトルだったんだ(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1993年ごろ)。なんでも、そのタイトルでは売れにくいっていうんで『漱石を読む』になったらしいのだが、どっちだって同じじゃないかねえ。それにしても、やってくれるよ。いまどき『日本文学の未来』なんてタイトルつけねえよ、ふつう。タイトルもすごいし、二段組で五七六頁もあるし、四八〇〇円もするし、それでもって中身が最高なんだから。その証拠に、この本はぼくが引いた傍線でびっしり。他人はどうだか知らないが、ぼくは気にいっちゃうと、本にすぐ傍線を引く。どんどん、引く。だから、本が傍線だらけだと、きわめて気にいったということになるんだけど、後になってからどうしてそんなところに傍線引っ張ったんだかぜんぜんわからないぜってことだってある。ちなみに、いままでもっとも傍線を引いた本は何だったか考えてみたんだが、たぶんトーマス・マンの『ゲーテ論集』(未來杜)かジョルジュ・プーレの『人間的時間の研究』(筑摩叢書)のどちらかだったんじゃないだろうか。さっき本棚の奥から探しだして頁を開いてみたが、やっぱり傍線が引きまくってありました。
真の人間、本質的な人間は、過去のなかにでも、現在のなかにでもなく、過去と現在とをつなぐ関係のなかに、すなわち両者のあいだにその存在が認められる。(『人間的時間の研究』)
こんなところに傍線を引いた上に「!」までいくつも並んでる。これを読んでいた頃、ぼくは二十歳だったっけ。若いねえ。
しかし、そのぼくも四十二歳になったので小島信夫の評論に傍線を引くようになったのでありました。
さてこの『漱石を読む』。漱石の『明暗』を冒頭から丹念に読むことからはじまり、それから先は小島信夫らしく例によって脱線また脱線なのだが、いちおう評論なので、読むことと考えることに作者は徹している。しかし、読むことと考えることだけでこんなに面白くていいのか!マイケル・クライトンの二千倍も面白いそ!とぼくは思うけど、みなさんはどうでしょう。
こういう気楽な文章の流れとつきあっていると、私達が求めているのは、いったい何であったのか、という気持になる。私達は実は何もきかされるのを求めたりしているわけではない。何も読みたいわけではない。ただ目うつりするものだけを追いかけているにすぎなくて、それはこの読者である私が真剣であることを要求されたくない、と思っている。ただ、眼が動くからこちらの人間さまも関心をもっているように見えるだけで、それ以外何ものでもない、という姿勢のままである。
この世界はスイも甘いもすべてを常識としているところである。多くの小説は、甘い考えを抱いているが、それを許さぬ世間とぶつかって挫折し、世間が悪い、もっと自由をあたえろ、筋の通ったことを認め、その筋を通せ、と訴えるようなふうであることが多い。
というようなところを読んでいると思わず傍線を引いてしまい、そうだそうだ読者はだまされやすいものなあとひとりごとを眩くのである。そう、小島信夫はこんなことさえいっている。
なぜ彼は清子に対して、あのような注意の眼を向けるのだろう。なぜ彼は風呂場にいて彼女が戸をあけて入ってくることを期待するばかりか、いっしょに風呂へ入ることさえ当然と思っているふしがあるのだろう。いったいこの二人は何をしてきたのだ。夢とは何なのだ。読者はだまされてはいけない!
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする