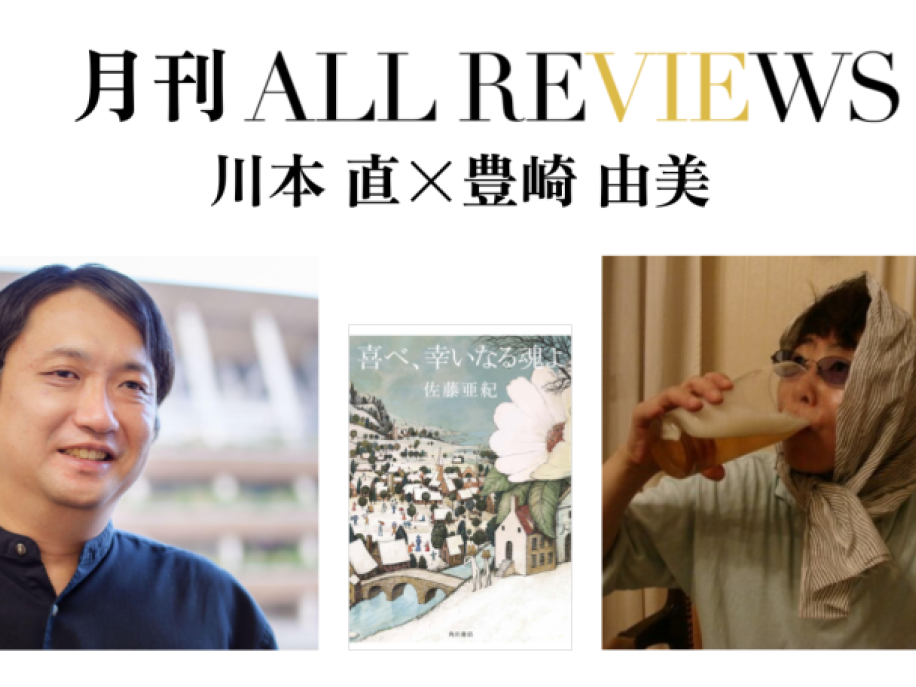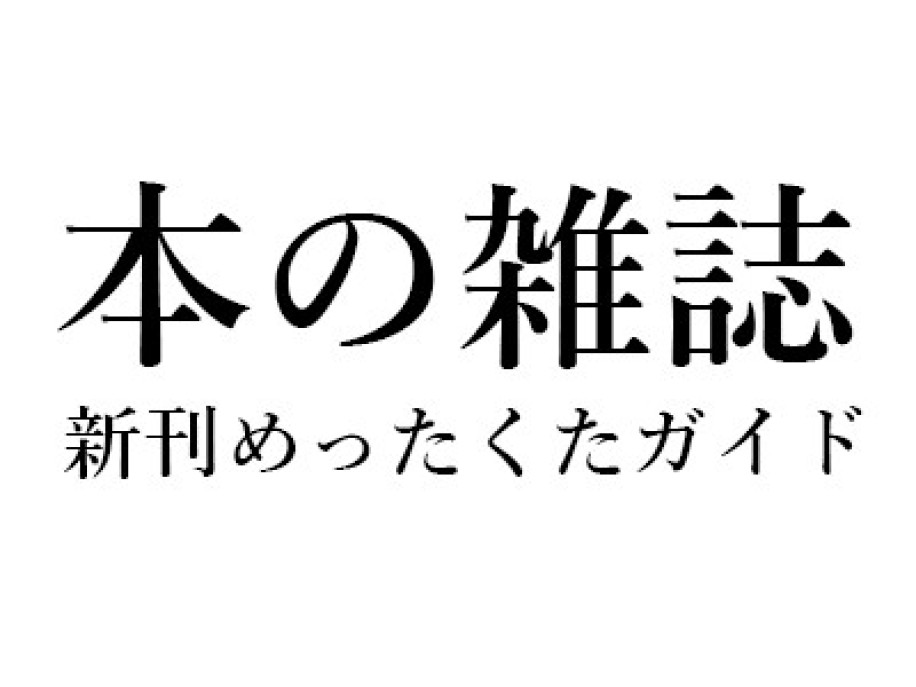書評
『ミノタウロス』(講談社)
トヨザキ的評価軸:
「金の斧(親を質に入れても買って読め)」
「銀の斧(図書館で借りられたら読めば―)」
「鉄の斧(ブックオフで100円で売っていても読むべからず)」
物語の舞台は、第一次世界大戦と革命に揺れるロシア帝国のウクライナ地方。地主に成り上がった男の次男として生を受けた青年・ヴァシリを語り手に、ソビエト連邦誕生前夜の混沌を駆け抜け、頓死した無法者たちの、生き残りをかけた暴力と強奪の日々を描いているんです。
ゾラやバルザックといったフランスの小説を読み耽り、ニヒリストとして成長していくヴァシリ。が、父が死に、二月革命が起こると、何不自由ない特権階級の生活も終わりを告げます。徒党を組んだ革命派の若者たちに焼き払われる屋敷。賭博に手を出した兄のせいで人手に渡る土地。父親の共同経営者であるシチェルパートフのところに身を寄せるものの、ヴァシリは言い争いの末に彼を射殺、逃亡してしまいます。途中、部隊に置き去りにされたドイツ兵のウルリヒ、馬扱いがうまく朴訥なフェディコと出会い、三人は生き延びるために略奪の限りを尽くすのですが――。
ウクライナの平原を舞台に、ロシア軍内の赤軍と白軍、強盗集団入り乱れてのアナーキーなドンパチが繰り広げられる中盤以降の展開は、冒険小説ファンならしびれること必定。タチャンカと呼ばれる機関銃つきの馬車を駆り、赤軍のパイロットを殺して奪った複葉機を操ってのスピード感と臨場感溢れるアクション・シーンは、乾いた詩情に包まれた的確かつスタイリッシュな文章によって、映像化の必要がないほど、読む者の眼前に立体的に現れるのです。
そこらの冒険小説作家のおっさんに書かせたら、間違いなく上下巻の分厚い作品になってしまうほど複雑かつ膨大なエピソードを内包する時代を背景におきながら、二百八十ページ弱の物語にした点も、佐藤亜紀の並々ならぬ力量を示すというべきでありましょう。情報の枝葉を刈り、言葉を選び、その配置を吟味し、必要最小限の文章によって最大限の効果を引き出し密度の高い小説を創りあげる。佐藤亜紀の文体家としてのアビリティの高さが堪能できるという意味においても、大量死という現代の”軽い”死と暴力ではなく、血腥くてリアルな死と暴力を描ききったという点においても、大変な傑作なんであります。直木賞がこの作品を無視したら笑止。文学的常識を疑いましてよ。
[後記=直木賞からは無視されましたが、第二十九回吉川英治文学新人賞を受賞いたしました!]
【この書評が収録されている書籍】
「金の斧(親を質に入れても買って読め)」
「銀の斧(図書館で借りられたら読めば―)」
「鉄の斧(ブックオフで100円で売っていても読むべからず)」
血湧き肉躍るピカレスクロマンの傑作です
雨がそぼ降る六月は佐藤亜紀礼賛強化月間に決定! いや、だって、すごいんだもの、『ミノタウロス』は。世界文学なんだもの。サム・ペキンパーの映画くらいカッコいいんだもの。マカロニ・ウェスタンかっつーくらい、血湧き肉躍るピカレスクロマンの傑作なんだもの。物語の舞台は、第一次世界大戦と革命に揺れるロシア帝国のウクライナ地方。地主に成り上がった男の次男として生を受けた青年・ヴァシリを語り手に、ソビエト連邦誕生前夜の混沌を駆け抜け、頓死した無法者たちの、生き残りをかけた暴力と強奪の日々を描いているんです。
ゾラやバルザックといったフランスの小説を読み耽り、ニヒリストとして成長していくヴァシリ。が、父が死に、二月革命が起こると、何不自由ない特権階級の生活も終わりを告げます。徒党を組んだ革命派の若者たちに焼き払われる屋敷。賭博に手を出した兄のせいで人手に渡る土地。父親の共同経営者であるシチェルパートフのところに身を寄せるものの、ヴァシリは言い争いの末に彼を射殺、逃亡してしまいます。途中、部隊に置き去りにされたドイツ兵のウルリヒ、馬扱いがうまく朴訥なフェディコと出会い、三人は生き延びるために略奪の限りを尽くすのですが――。
ウクライナの平原を舞台に、ロシア軍内の赤軍と白軍、強盗集団入り乱れてのアナーキーなドンパチが繰り広げられる中盤以降の展開は、冒険小説ファンならしびれること必定。タチャンカと呼ばれる機関銃つきの馬車を駆り、赤軍のパイロットを殺して奪った複葉機を操ってのスピード感と臨場感溢れるアクション・シーンは、乾いた詩情に包まれた的確かつスタイリッシュな文章によって、映像化の必要がないほど、読む者の眼前に立体的に現れるのです。
そこらの冒険小説作家のおっさんに書かせたら、間違いなく上下巻の分厚い作品になってしまうほど複雑かつ膨大なエピソードを内包する時代を背景におきながら、二百八十ページ弱の物語にした点も、佐藤亜紀の並々ならぬ力量を示すというべきでありましょう。情報の枝葉を刈り、言葉を選び、その配置を吟味し、必要最小限の文章によって最大限の効果を引き出し密度の高い小説を創りあげる。佐藤亜紀の文体家としてのアビリティの高さが堪能できるという意味においても、大量死という現代の”軽い”死と暴力ではなく、血腥くてリアルな死と暴力を描ききったという点においても、大変な傑作なんであります。直木賞がこの作品を無視したら笑止。文学的常識を疑いましてよ。
[後記=直木賞からは無視されましたが、第二十九回吉川英治文学新人賞を受賞いたしました!]
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする