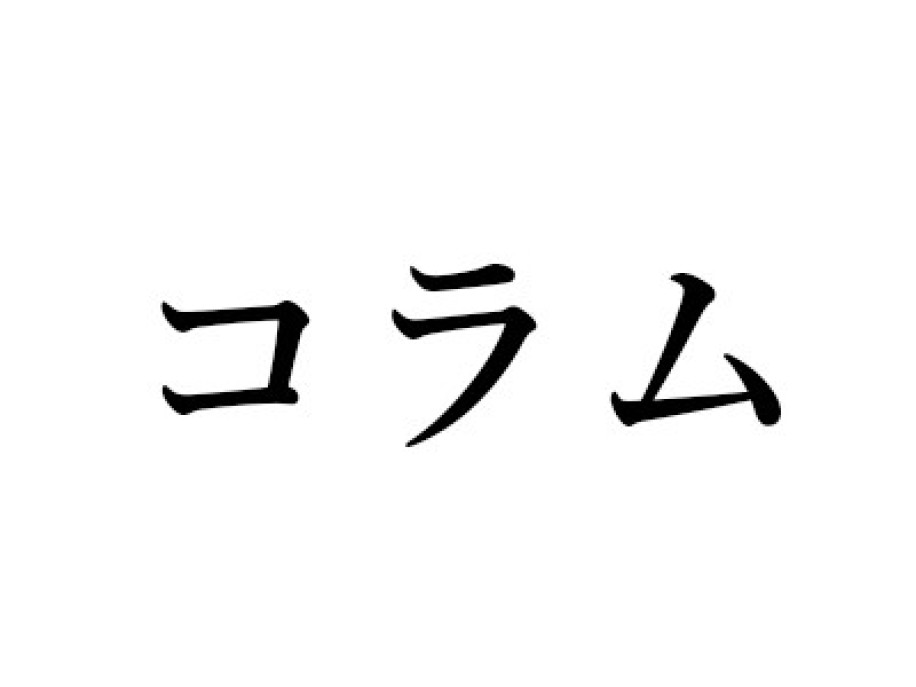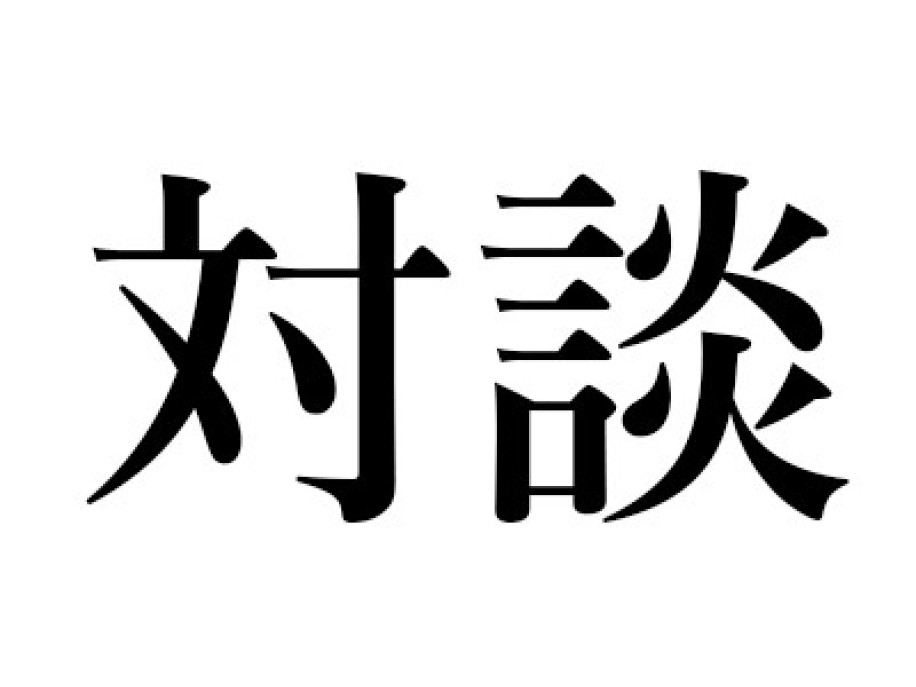前書き
『国民国家のリアリズム』(KADOKAWA)
「ハクソー・リッジ」でも「炎のランナー」でも、強い意志を貫くことができたのは神との契約があったからだ。いっぽうで国民国家の一員として愛国心を発露してもいるのである。
ヨーロッパ的近代国家を目指した日本では、一八八九年(明治22年)に大日本帝国憲法を発布して翌年に総選挙が実施され、帝国議会が開催された。福沢諭吉は「政府ありてネーション(国民)なし」と藩閥政府の専制を批判したが、議会が開かれることで意思決定に「国民」が参加し、文字通り国民国家が誕生した。
だが明治維新後の日本に足りないものがあった。キリスト教にあたる内面の規範の軸、公共的価値体系であった。初代首相の伊藤博文はそれに気づいていた。
帝国議会開催の直前に「教育に関する勅語」(以下、教育勅語)が発布された。
「炎のランナー」では、英国国王とキリスト教の神は区別されているが、日本では天皇は憲法に規定された立憲君主でありながら、教育勅語は憲法と無関係に天皇により発せられた道徳律であった。天皇にはいわば一人二役のような役割が負わされた。
天皇は憲法に規定された存在(いわゆる「天皇機関説」)でありながら、教育勅語の発布者として宗教的な色彩を帯びたことになる。
「朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ」から始まって、「我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ」とか「夫婦相和シ朋友相信シ」とか「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」と、教育勅語は、国民国家における国民の規範と義務、利他的な心得を説いたものだ。
キリスト教のように聖書を根拠にするわけにはいかないので、天皇が国を肇めた永遠の昔から存在した道徳律とされた。法律には大臣の副署と呼ばれる署名が付くのだが、教育勅語に副署をしたらただの立憲君主の命令になってしまう。だから教育勅語は大臣の副書がない。あくまでも天皇のつぶやきのようなかたちをとりながら先祖伝来の伝統的な道徳として扱い、憲法とは別にした。
「ハクソー・リッジ」や「炎のランナー」の主人公が個人として挫けずにいるのは、国民国家への強い忠誠心を持ついっぽうで、別に、自ら信ずるところの規範に従うことができたからである。
教育勅語が発布された翌年、第一高等中学校の教員であったキリスト者の内村鑑三が不敬事件を起こしたと非難された。教育勅語奉読式で自らの信念に従い、ていねいに敬礼をしなかった点を咎められた。内村鑑三は、憲法に規定された天皇に従う愛国者としての自負、忠誠心を強く持ちながら、道徳律の発布者としての天皇については、キリスト者として区別したからである。
日本にも内村鑑三のような「ハクソー・リッジ」や「炎のランナー」に負けない「個人」がいたことは、日本の近代国家のスタートがまずまずであった証しともいえる。
近代国家を国民国家と言い換えてもよい。独立した個人(内心の自由)、主権者としての国民によって構成されたこの仕組みは、歴史的な産物だからである。
十七世紀から十九世紀にかけてヨーロッパで整えられた国民国家体制は、もっとも安定した統治システムと思われてきた。日本では明治維新という革命により素早く国民国家に切り換えることができた。国民国家は、専制王権に対して国民が主権者であるようなシステム、国境に区切られた一つのエリアのなかで共通の国語教育を義務づけ、言語だけでなく国旗や国歌などシンボル体系を持ち一体感を醸成してきた。
立憲君主制を採用した明治政府は、「富国強兵」により国家が産業振興に積極的に関わり、主権国家を維持するために納税だけでなく徴兵の義務も課しているが、ヨーロッパモデルを踏まえたものであった。
国民国家は歴史的産物であると書いたが、進化の過程で誕生した究極のシステムともいえた。だが歴史的産物であるかぎり、それを超えようとする動きが二十世紀に起きる。国民国家が集まる国際社会であっても国家間の戦争を抑止しにくい面がある。ヨーロッパにおける第一次大戦は総力戦となり史上最大の殲滅戦となった。その結果、国際連盟が誕生したりパリ不戦条約が締結される。それでもヒトラーの戦争を防ぐことはできず、第二次大戦後、ヨーロッパ諸国は、欧州経済共同体(EEC)をつくり国境の壁を低くしながら、ついにEU(欧州連合)にたどり着いた。経済のグローバル化とも軌を一にした動きでもあった。
ところが近年、イギリスのEU離脱、トランプ政権の誕生など、国民国家への回帰現象が顕著になっているかのようでもある。
以上を踏まえたうえで気鋭の国際政治学者で『シビリアンの戦争──デモクラシーが攻撃的になるとき』の著者、三浦瑠麗さんと話し合いながら、国際社会と日本の針路を考えてみたい。
明治憲法発布の直前、日本の進むべき道を中江兆民は『三酔人経綸問答』として著している。三人の登場人物が酒の酔いにまかせて論争を繰り広げる構成の本である。ヨーロッパ列強を鏡としながらその欠点を指摘して非戦論を唱える洋学紳士(紳士君)、アジアへの強引な進出を主張する豪傑君、それぞれの言い分を聞きながら現実主義的な調整役を演じる南海先生、思想と性格が異なるそれぞれの意見により読者は多角的な視点を得ることができる。
本書の討論は三酔人ではなく、二人の男子と女子である。父親と娘ほどに年齢は離れている。体験も知識もおよそ懸け離れている。だからこそ異なる視座で意見を述べ合い、耳を傾けるべきところは互いに素直に耳を傾ける。瑠麗さんの柔らかく、かつ鋭い表現によって僕はずいぶん蒙を啓かれた想いがしている。読者の皆さんの胸のうちもここに加えて、新しい三酔人としつつお読みいただければうれしい。
ヨーロッパ的近代国家を目指した日本では、一八八九年(明治22年)に大日本帝国憲法を発布して翌年に総選挙が実施され、帝国議会が開催された。福沢諭吉は「政府ありてネーション(国民)なし」と藩閥政府の専制を批判したが、議会が開かれることで意思決定に「国民」が参加し、文字通り国民国家が誕生した。
だが明治維新後の日本に足りないものがあった。キリスト教にあたる内面の規範の軸、公共的価値体系であった。初代首相の伊藤博文はそれに気づいていた。
帝国議会開催の直前に「教育に関する勅語」(以下、教育勅語)が発布された。
「炎のランナー」では、英国国王とキリスト教の神は区別されているが、日本では天皇は憲法に規定された立憲君主でありながら、教育勅語は憲法と無関係に天皇により発せられた道徳律であった。天皇にはいわば一人二役のような役割が負わされた。
天皇は憲法に規定された存在(いわゆる「天皇機関説」)でありながら、教育勅語の発布者として宗教的な色彩を帯びたことになる。
「朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ」から始まって、「我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ」とか「夫婦相和シ朋友相信シ」とか「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」と、教育勅語は、国民国家における国民の規範と義務、利他的な心得を説いたものだ。
キリスト教のように聖書を根拠にするわけにはいかないので、天皇が国を肇めた永遠の昔から存在した道徳律とされた。法律には大臣の副署と呼ばれる署名が付くのだが、教育勅語に副署をしたらただの立憲君主の命令になってしまう。だから教育勅語は大臣の副書がない。あくまでも天皇のつぶやきのようなかたちをとりながら先祖伝来の伝統的な道徳として扱い、憲法とは別にした。
「ハクソー・リッジ」や「炎のランナー」の主人公が個人として挫けずにいるのは、国民国家への強い忠誠心を持ついっぽうで、別に、自ら信ずるところの規範に従うことができたからである。
教育勅語が発布された翌年、第一高等中学校の教員であったキリスト者の内村鑑三が不敬事件を起こしたと非難された。教育勅語奉読式で自らの信念に従い、ていねいに敬礼をしなかった点を咎められた。内村鑑三は、憲法に規定された天皇に従う愛国者としての自負、忠誠心を強く持ちながら、道徳律の発布者としての天皇については、キリスト者として区別したからである。
日本にも内村鑑三のような「ハクソー・リッジ」や「炎のランナー」に負けない「個人」がいたことは、日本の近代国家のスタートがまずまずであった証しともいえる。
近代国家を国民国家と言い換えてもよい。独立した個人(内心の自由)、主権者としての国民によって構成されたこの仕組みは、歴史的な産物だからである。
十七世紀から十九世紀にかけてヨーロッパで整えられた国民国家体制は、もっとも安定した統治システムと思われてきた。日本では明治維新という革命により素早く国民国家に切り換えることができた。国民国家は、専制王権に対して国民が主権者であるようなシステム、国境に区切られた一つのエリアのなかで共通の国語教育を義務づけ、言語だけでなく国旗や国歌などシンボル体系を持ち一体感を醸成してきた。
立憲君主制を採用した明治政府は、「富国強兵」により国家が産業振興に積極的に関わり、主権国家を維持するために納税だけでなく徴兵の義務も課しているが、ヨーロッパモデルを踏まえたものであった。
国民国家は歴史的産物であると書いたが、進化の過程で誕生した究極のシステムともいえた。だが歴史的産物であるかぎり、それを超えようとする動きが二十世紀に起きる。国民国家が集まる国際社会であっても国家間の戦争を抑止しにくい面がある。ヨーロッパにおける第一次大戦は総力戦となり史上最大の殲滅戦となった。その結果、国際連盟が誕生したりパリ不戦条約が締結される。それでもヒトラーの戦争を防ぐことはできず、第二次大戦後、ヨーロッパ諸国は、欧州経済共同体(EEC)をつくり国境の壁を低くしながら、ついにEU(欧州連合)にたどり着いた。経済のグローバル化とも軌を一にした動きでもあった。
ところが近年、イギリスのEU離脱、トランプ政権の誕生など、国民国家への回帰現象が顕著になっているかのようでもある。
以上を踏まえたうえで気鋭の国際政治学者で『シビリアンの戦争──デモクラシーが攻撃的になるとき』の著者、三浦瑠麗さんと話し合いながら、国際社会と日本の針路を考えてみたい。
明治憲法発布の直前、日本の進むべき道を中江兆民は『三酔人経綸問答』として著している。三人の登場人物が酒の酔いにまかせて論争を繰り広げる構成の本である。ヨーロッパ列強を鏡としながらその欠点を指摘して非戦論を唱える洋学紳士(紳士君)、アジアへの強引な進出を主張する豪傑君、それぞれの言い分を聞きながら現実主義的な調整役を演じる南海先生、思想と性格が異なるそれぞれの意見により読者は多角的な視点を得ることができる。
本書の討論は三酔人ではなく、二人の男子と女子である。父親と娘ほどに年齢は離れている。体験も知識もおよそ懸け離れている。だからこそ異なる視座で意見を述べ合い、耳を傾けるべきところは互いに素直に耳を傾ける。瑠麗さんの柔らかく、かつ鋭い表現によって僕はずいぶん蒙を啓かれた想いがしている。読者の皆さんの胸のうちもここに加えて、新しい三酔人としつつお読みいただければうれしい。
ALL REVIEWSをフォローする