書評
『江戸前―日本近代文芸のなかの江戸主義』(ビレッジセンター出版局)
江戸学が最近、揉めている。一方に徳川300年をユートピア的に理想化し、遊女こそは最先端の知的女性であったと肯定するロマンティックな立場がある。そしてもう一方に、こうした理想化は今日の立場から逆投影されたノスタルジアであって、遊女の平均寿命が24歳であったという社会の悲惨にこそ目を向けなければならないと批判する、よりリアリスティックな立場がある。
若い研究家はこのどちらの陣営に属するかで、決断を迫られているようだ。だがこうした対立を越えたところで、山口昌男の『敗者学のすすめ』(平凡社)のように、江戸時代の文化的遺産が明治以後の近代に何を遺しえたのかをめぐって、より達観した視点からなされた書物も、最近出現している。
平岡正明の『江戸前』も、その系譜に属するエッセイ集だといえるだろう。この人、明治の東京には薬局は仁星堂か芳生堂かと喧伝された、その芳生堂の三代目に当たるらしい。湯島の坂を語るにも、斎藤緑雨の短編を語るにも、身体の記憶が感じられる。イタリアの理論家グラムシだったら「文化の腐植土」というところだ。江戸前とは「苦味走って勇み肌で粋」であることに、財力、権力、社会的地位より高い価値をもつことだと、端的に定義している。
本書の内容は露伴、荷風から長谷川伸まで多岐にわたっている。ひとつだけ述べるならば、綺堂の『半七捕物帖』と胡堂の『銭形平次捕物控』の間には、大震災による江戸の第2の崩壊が横たわっているという指摘がある。前者は遠慮を知る町人の文化的成熟がまだまだ残っていた1910年代に執筆されたが、後者はすべてが灰燼に帰した後に、大正モダニズム文化のなかで書かれた。同じ捕物帖といっても、江戸をめぐる眼差しがまったく異なっているという。
平岡正明は最初、戦闘的なジャズ評論家として出発した。その後彼は、第3世界革命論から座頭市論、犯罪論、日本帝国主義論と、さまざまに多様な分野で天才的な扇動家として活動しながら、歌謡曲、河内音頭、落語、浪曲といったぐあいに、一貫して日本における大衆娯楽としての語りもの、歌もの系譜について語ってきた。その彼が本書において江戸の運河を流れる真水から生まれた新内について論じるのは当然のことだろう。日本近代では若いころは西洋にかぶれ、長じて日本に回帰するというのが評論家の定石とされる傾向があるが、平岡の場合にはもとより大アジア主義と格闘してきただけあって、単純に回帰すべき日本など存在していない。彼が信頼しているのは文化としての江戸であって、国家としての日本ではない。
一見先祖の文化的足跡を辿るノスタルジックなもののように見えて、実はきわめてアクチュアルな問題提起をもった好著である。
【この書評が収録されている書籍】
若い研究家はこのどちらの陣営に属するかで、決断を迫られているようだ。だがこうした対立を越えたところで、山口昌男の『敗者学のすすめ』(平凡社)のように、江戸時代の文化的遺産が明治以後の近代に何を遺しえたのかをめぐって、より達観した視点からなされた書物も、最近出現している。
平岡正明の『江戸前』も、その系譜に属するエッセイ集だといえるだろう。この人、明治の東京には薬局は仁星堂か芳生堂かと喧伝された、その芳生堂の三代目に当たるらしい。湯島の坂を語るにも、斎藤緑雨の短編を語るにも、身体の記憶が感じられる。イタリアの理論家グラムシだったら「文化の腐植土」というところだ。江戸前とは「苦味走って勇み肌で粋」であることに、財力、権力、社会的地位より高い価値をもつことだと、端的に定義している。
本書の内容は露伴、荷風から長谷川伸まで多岐にわたっている。ひとつだけ述べるならば、綺堂の『半七捕物帖』と胡堂の『銭形平次捕物控』の間には、大震災による江戸の第2の崩壊が横たわっているという指摘がある。前者は遠慮を知る町人の文化的成熟がまだまだ残っていた1910年代に執筆されたが、後者はすべてが灰燼に帰した後に、大正モダニズム文化のなかで書かれた。同じ捕物帖といっても、江戸をめぐる眼差しがまったく異なっているという。
平岡正明は最初、戦闘的なジャズ評論家として出発した。その後彼は、第3世界革命論から座頭市論、犯罪論、日本帝国主義論と、さまざまに多様な分野で天才的な扇動家として活動しながら、歌謡曲、河内音頭、落語、浪曲といったぐあいに、一貫して日本における大衆娯楽としての語りもの、歌もの系譜について語ってきた。その彼が本書において江戸の運河を流れる真水から生まれた新内について論じるのは当然のことだろう。日本近代では若いころは西洋にかぶれ、長じて日本に回帰するというのが評論家の定石とされる傾向があるが、平岡の場合にはもとより大アジア主義と格闘してきただけあって、単純に回帰すべき日本など存在していない。彼が信頼しているのは文化としての江戸であって、国家としての日本ではない。
一見先祖の文化的足跡を辿るノスタルジックなもののように見えて、実はきわめてアクチュアルな問題提起をもった好著である。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
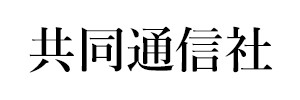
共同通信社 2000年5月
ALL REVIEWSをフォローする









































