書評
『ユージニア』(角川グループパブリッシング)
恩田陸といえば、九一年に『六番目の小夜子』でデビュー以来、ミステリー、ホラー、ファンタジー、学園小説と多彩なジャンルの小説を手がけるエンターテイナーの鑑のごとき作家。しかも、多作。なのに、高水準。買って読んで悔いなしの、ハズレなきことで知られる信頼印のアベレージ・ヒッターなんであります。『ユージニア』もまた、読み始めたら途中でやめるのが困難。それほど面白いのだけれど、単に面白いだけじゃすまないのが、恩田ワールドの特長です。不穏な気配ムンムン。読み終えてスッキリというエンターテインメントお約束の大団円は、この物語には用意されていません。むしろ、疑問は増す一方。得体の知れない小説になっているのです。
惨劇の舞台は町の名家として知られる医者の家。ある夏の日、その屋敷で催された祝宴で、届けられた酒やジュースに混入されていた毒物によって一七名が死亡するという事件が発生。後に犯人は見つかるものの、すでに自殺しており、動機がわからないまま事件は一応の決着をみます。一〇年後、事件を取材した本が出版されベストセラーに。著者は少女の頃に惨劇の屋敷の近所に住んでおり、危うく難を逃れた女性でした。
それからさらに時を経た今、すでに遠い過去となった事件の関係者やベストセラーの著者、生き残ったお手伝いさんの娘、刑事、自殺した犯人をよく知る人などに聞き取りをする人物が現れます。実行犯は自殺した男かもしれないけれど、それを示唆した者がいるのではないか……。謎を残す事件について語る幾人もの証人。しかし、そのどれもが主観によっているために、多少のうさん臭さが伴ってしまうのです。いわゆる“信用ならざる語り手”というやつですね。そうした一人称で語られる聞き取りのパートの合間に、かつて事件について書かれたベストセラーからの抜粋やその著者の取材日誌、この聞き取りをしている人物のファイルといった資料的なテキストも挿入。真相はさらに混迷の度合いを深めていくのです。
こういうドキュメンタリー・タッチの犯罪小説といえば、ヒラリー・ウォーの傑作『この町の誰かが』(創元推理文庫)他、多くの先行作品があるけれど、この小説はもっと不気味な仕上がりになっています。なぜか。ミステリーという文脈の上では、恩田陸は何の謎も解いてくれていないからです。世の中には自分には理解できないことがたくさんあり、真相は人の数ほどある。なのに、理解できないからといって人は腹を立てたり、その対象を排除したりしようとする。自分が何もわかっていないということを理解しようとしない。『ユージニア』は、そのわからなさを巡るあれこれを、“腑に落ちる”解釈を拒否するスタイルで描いた小説だから、読後こんなにも読む者を居心地の悪い気分にさせるのではないでしょうか。
わからないという状態は人を不安にさせます。けれども、わからないものをわかった気になることは、その安易さがもたらす誤解や齟齬(そご)を考えると、不安を超えて怖ろしい。そうした不安や恐怖の因となるわからなさの核にいるのが、医者一家の盲目の娘でカリスマ的な魅力を放つ緋紗子です。すべての人物が彼女の周りを衛星のように回り、引力で引き寄せられながらも決して近づくことは許されないでいる。彼女の人物造型ひとつ取っても、これは傑作にふさわしい小説に違いありません。
最後に忠告をひとつ。乗り物に酔いやすい方は、決して電車の中で読まれませんように。凝りに凝った造りになっているこの本には、わざと文字組を歪ませるという仕掛けが施されているんです。虚実のあわいで宙づりにされるような不安定さ、そんな読み心地を一層強めんとする装幀家・祖父江慎の意欲も併せて、手元に置いておきたくなる一冊なんであります。
【この書評が収録されている書籍】
惨劇の舞台は町の名家として知られる医者の家。ある夏の日、その屋敷で催された祝宴で、届けられた酒やジュースに混入されていた毒物によって一七名が死亡するという事件が発生。後に犯人は見つかるものの、すでに自殺しており、動機がわからないまま事件は一応の決着をみます。一〇年後、事件を取材した本が出版されベストセラーに。著者は少女の頃に惨劇の屋敷の近所に住んでおり、危うく難を逃れた女性でした。
それからさらに時を経た今、すでに遠い過去となった事件の関係者やベストセラーの著者、生き残ったお手伝いさんの娘、刑事、自殺した犯人をよく知る人などに聞き取りをする人物が現れます。実行犯は自殺した男かもしれないけれど、それを示唆した者がいるのではないか……。謎を残す事件について語る幾人もの証人。しかし、そのどれもが主観によっているために、多少のうさん臭さが伴ってしまうのです。いわゆる“信用ならざる語り手”というやつですね。そうした一人称で語られる聞き取りのパートの合間に、かつて事件について書かれたベストセラーからの抜粋やその著者の取材日誌、この聞き取りをしている人物のファイルといった資料的なテキストも挿入。真相はさらに混迷の度合いを深めていくのです。
こういうドキュメンタリー・タッチの犯罪小説といえば、ヒラリー・ウォーの傑作『この町の誰かが』(創元推理文庫)他、多くの先行作品があるけれど、この小説はもっと不気味な仕上がりになっています。なぜか。ミステリーという文脈の上では、恩田陸は何の謎も解いてくれていないからです。世の中には自分には理解できないことがたくさんあり、真相は人の数ほどある。なのに、理解できないからといって人は腹を立てたり、その対象を排除したりしようとする。自分が何もわかっていないということを理解しようとしない。『ユージニア』は、そのわからなさを巡るあれこれを、“腑に落ちる”解釈を拒否するスタイルで描いた小説だから、読後こんなにも読む者を居心地の悪い気分にさせるのではないでしょうか。
わからないという状態は人を不安にさせます。けれども、わからないものをわかった気になることは、その安易さがもたらす誤解や齟齬(そご)を考えると、不安を超えて怖ろしい。そうした不安や恐怖の因となるわからなさの核にいるのが、医者一家の盲目の娘でカリスマ的な魅力を放つ緋紗子です。すべての人物が彼女の周りを衛星のように回り、引力で引き寄せられながらも決して近づくことは許されないでいる。彼女の人物造型ひとつ取っても、これは傑作にふさわしい小説に違いありません。
最後に忠告をひとつ。乗り物に酔いやすい方は、決して電車の中で読まれませんように。凝りに凝った造りになっているこの本には、わざと文字組を歪ませるという仕掛けが施されているんです。虚実のあわいで宙づりにされるような不安定さ、そんな読み心地を一層強めんとする装幀家・祖父江慎の意欲も併せて、手元に置いておきたくなる一冊なんであります。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
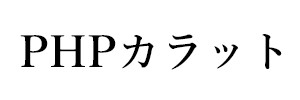
PHPカラット(終刊) 2005年6月
ALL REVIEWSをフォローする











































