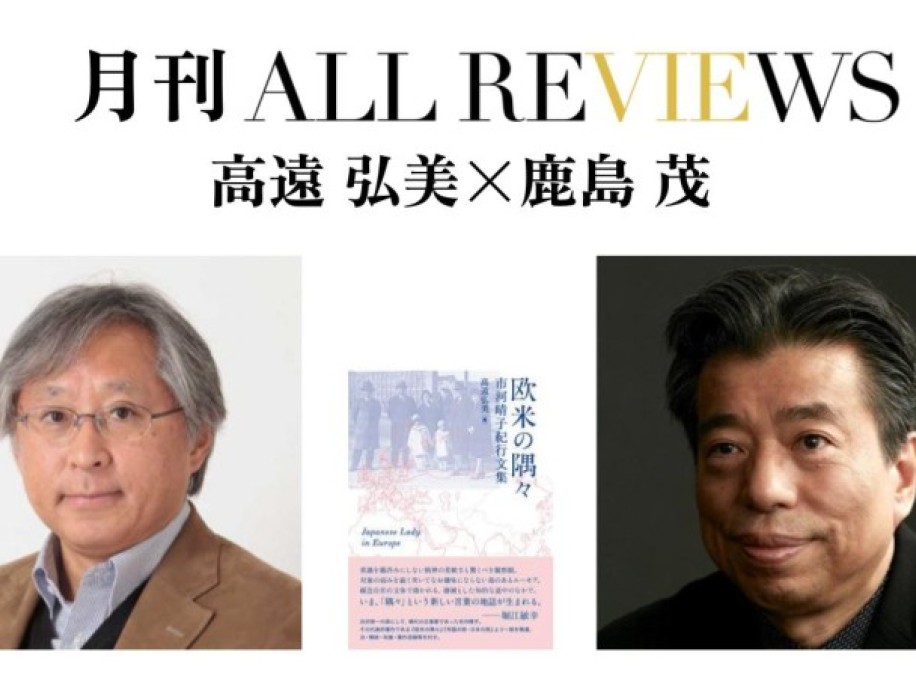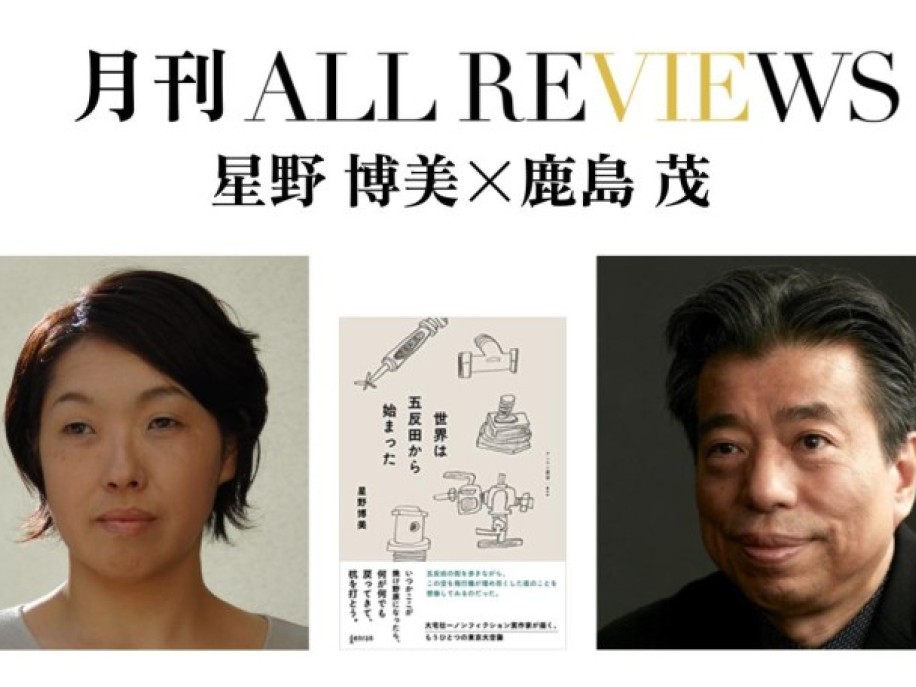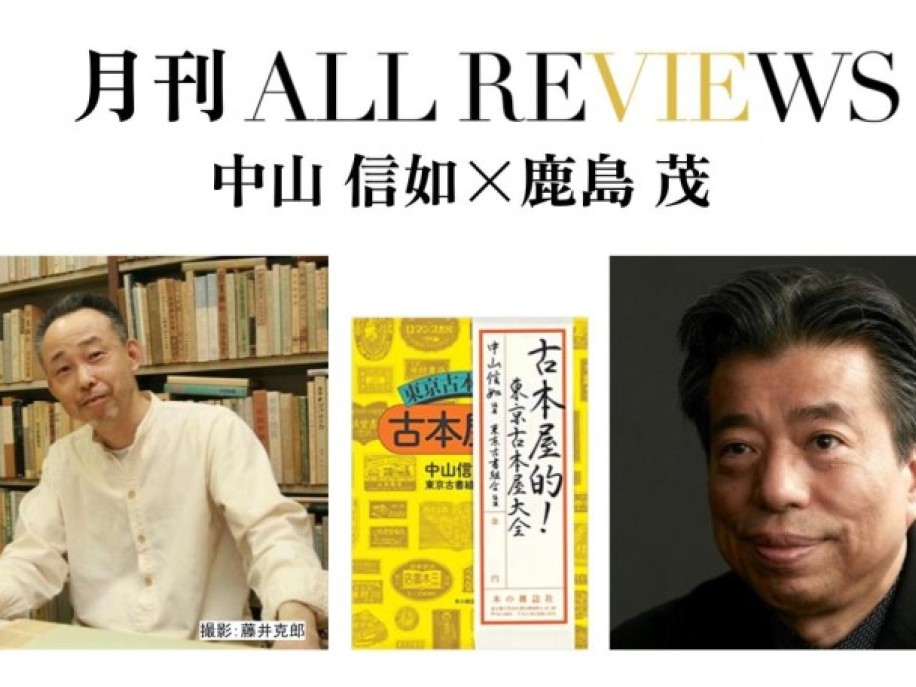後書き
『セーラー服とエッフェル塔』(文藝春秋)
見渡せば、世の中、じつに多くの不思議や謎に満ちている。
ただ、大多数の人はそれを不思議とも謎とも疑ってみないだけである。
たとえば、女性の乳房はなぜ膨らんでいて、男性はそれに愛着を覚えるのかという不思議、また男性のペニスはなにゆえに、勃起時に平均十三センチにも達するのかという疑問。
これらの問題は、それ自体しか見ない人間にとっては、疑問でもなんでもない、まったく自明の事柄だとう。だが、しかるべき本を読んでみると、それらは、ほどんと永遠に解けないような巨大な疑問として研究者の前に立ちはだかっていることがわかる。なぜなら、人類以外で乳房が常時膨らんでいる哺乳類はほとんどいないし、またゴリラのペニスは勃起時でもわずかに三センチであると調べがついているからである。
また、日本だけに定着して、いまだに根強い人気を誇っているセーラー服というもの。これも、いったん考え出すと、いかにも多くの謎に包まれていることが判明する。なぜ、日本でだけセーラー服が女学校の制服となり、男たちのエロティックな夢想の対象となったのか、その経路がよくわからない。
さらに日本でだけ独自の発展を遂げたSMの亀甲縛りというもの。いったい、このいとも珍奇なる緊縛法は、なにを契機として日本に誕生したのか? あるいは、情死・心中という過激なる愛の解決法が日本特有なのはなにゆえなのか?
疑問がわいてくるのは、むろん、こうしたエロスと結びついた領域にはとどまらない。日本人が外国語の会話が下手な原因はなんなのか? イギリス人とフランス人は、なにゆえに、牛肉の食べ方やコーヒー・紅茶の飲み方でかくも対象的なちがいをみせるのか?
さらには、キリストが血まみれの残酷な姿で十字架にかけられているのは、いったいなんのためなのかという大疑問に至るまで。
このように、自明の事象として、多くの人たちにとっては問題とさえならないことが、本を読むことで、まず大きな疑問としてあつかわれているのを知ることができる。さらに、著者たちが懸命に仮説を構築し、答えを出そうと努力している姿に接することができる。
もちろん、いくら本をあたっても未解決のままの疑問も少なくない。しかし、最低でも、それらが、だれかの手によって疑問として呈されていることを知ることは可能だし、それを手掛かりに、独自の仮説を大きく膨らませることも許されるのである。
ことほどさように、本というのは、まことにもってありがたいものであり、かけがえのない人類の財産なのである。私は、これらの大問題をあつかった本に接するたびに書評にとりあげ、できるかぎり紹介につとめてきたつもりである。
しかるに、昨今では、どうやら、こうした努力はすべて虚しく、本は一ヶ月もしなういうちに書店の棚から消えてゆく。
それとともに、あらゆることに疑問をいだき、まず前提を疑ってかかる懐疑的精神も衰えていくように思える。
どんな矮小な事柄にも、またいかに壮大な事象にも、ひたすら懐疑的精神をもって臨むべし、これが近代合理精神の出発点ではなかったか?
こうした危惧から執筆を思い立ったのが本書である、と、いいたいところだが、じつをいえば、そんなに大それたことではなく、冒頭でも触れたように、私自身、妙なことに対しても仮説癖が働いて、そのたびに、手あたり次第に本を乱読して、センス・オブ・ワンダーを味わってきたにすぎない。
ただ、ひとつだけいいたいのは、仮説への手掛かりも、センス・オブ・ワンダーの発見も、たいていは本のうちにあるということである。
したがって、本書は少し時間差をおいた、真におもしろい本への案内、紹介であるということができる。
ただ、大多数の人はそれを不思議とも謎とも疑ってみないだけである。
たとえば、女性の乳房はなぜ膨らんでいて、男性はそれに愛着を覚えるのかという不思議、また男性のペニスはなにゆえに、勃起時に平均十三センチにも達するのかという疑問。
これらの問題は、それ自体しか見ない人間にとっては、疑問でもなんでもない、まったく自明の事柄だとう。だが、しかるべき本を読んでみると、それらは、ほどんと永遠に解けないような巨大な疑問として研究者の前に立ちはだかっていることがわかる。なぜなら、人類以外で乳房が常時膨らんでいる哺乳類はほとんどいないし、またゴリラのペニスは勃起時でもわずかに三センチであると調べがついているからである。
また、日本だけに定着して、いまだに根強い人気を誇っているセーラー服というもの。これも、いったん考え出すと、いかにも多くの謎に包まれていることが判明する。なぜ、日本でだけセーラー服が女学校の制服となり、男たちのエロティックな夢想の対象となったのか、その経路がよくわからない。
さらに日本でだけ独自の発展を遂げたSMの亀甲縛りというもの。いったい、このいとも珍奇なる緊縛法は、なにを契機として日本に誕生したのか? あるいは、情死・心中という過激なる愛の解決法が日本特有なのはなにゆえなのか?
疑問がわいてくるのは、むろん、こうしたエロスと結びついた領域にはとどまらない。日本人が外国語の会話が下手な原因はなんなのか? イギリス人とフランス人は、なにゆえに、牛肉の食べ方やコーヒー・紅茶の飲み方でかくも対象的なちがいをみせるのか?
さらには、キリストが血まみれの残酷な姿で十字架にかけられているのは、いったいなんのためなのかという大疑問に至るまで。
このように、自明の事象として、多くの人たちにとっては問題とさえならないことが、本を読むことで、まず大きな疑問としてあつかわれているのを知ることができる。さらに、著者たちが懸命に仮説を構築し、答えを出そうと努力している姿に接することができる。
もちろん、いくら本をあたっても未解決のままの疑問も少なくない。しかし、最低でも、それらが、だれかの手によって疑問として呈されていることを知ることは可能だし、それを手掛かりに、独自の仮説を大きく膨らませることも許されるのである。
ことほどさように、本というのは、まことにもってありがたいものであり、かけがえのない人類の財産なのである。私は、これらの大問題をあつかった本に接するたびに書評にとりあげ、できるかぎり紹介につとめてきたつもりである。
しかるに、昨今では、どうやら、こうした努力はすべて虚しく、本は一ヶ月もしなういうちに書店の棚から消えてゆく。
それとともに、あらゆることに疑問をいだき、まず前提を疑ってかかる懐疑的精神も衰えていくように思える。
どんな矮小な事柄にも、またいかに壮大な事象にも、ひたすら懐疑的精神をもって臨むべし、これが近代合理精神の出発点ではなかったか?
こうした危惧から執筆を思い立ったのが本書である、と、いいたいところだが、じつをいえば、そんなに大それたことではなく、冒頭でも触れたように、私自身、妙なことに対しても仮説癖が働いて、そのたびに、手あたり次第に本を乱読して、センス・オブ・ワンダーを味わってきたにすぎない。
ただ、ひとつだけいいたいのは、仮説への手掛かりも、センス・オブ・ワンダーの発見も、たいていは本のうちにあるということである。
したがって、本書は少し時間差をおいた、真におもしろい本への案内、紹介であるということができる。
ALL REVIEWSをフォローする