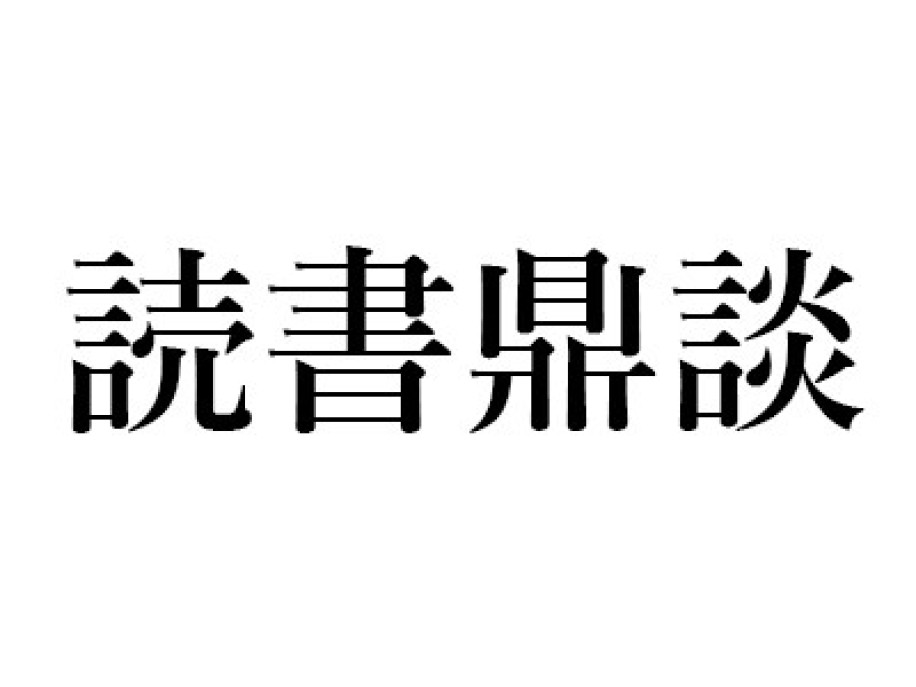書評
『母・娘・祖母が共存するために』(朝日新聞出版)
娘を股裂き状態にする母の要求
二〇〇四年に新聞の文芸時評を担当したときのことだった。女性作家たちの関心が母と娘の関係に集中していると気づいたのである。志賀直哉の『和解』が父と息子の、安岡章太郎の『海辺の光景』が母と息子の、それぞれエディプス的な関係を描いていたのに対し、当時三〇代だった団塊ジュニア世代の女性作家はそろいもそろって母と娘の難しい関係を自己のテーマとしていたのだ。以来、この問題を解く手掛かりとなるような本を探したが、目についたのは原宿カウンセリングセンター所長である著者のアダルト・チルドレンに関する一連の著作であった。すなわち摂食障害や自傷行為などの問題を抱えてカウンセリングにやってきた団塊ジュニア世代の女性たちから聞き取りをするうちに、著者は、彼女たちの生きづらさの原因が母親が幼い娘に繰り返し語った夫への失望や愚痴、あるいは復讐としての娘教育などから来ている事実を見出し、こうした母娘関係は普遍的ではなく、戦後日本に特殊的なものだったのではないかと仮説を立てたのである。
まず、前提となるのは、彼女たちの母である団塊世代の女性たちが戦後の民主化政策で生まれたロマンチック・ラブ・イデオロギー(RLI)の信奉者で、恋愛と性と結婚が三位一体となった理想的結婚生活を夢見たこと。その夢が、仕事一途で家庭は妻に任せ切りにした夫に裏切られたこ とから、娘を人質にとった団塊母親のリベンジが始まったのである。おとうさんなんかと結婚したのが人生最大の誤りであると繰り返し幼い娘に語り、最後は「あんたさえいなければ」と犠牲を強調して娘に罪悪感を喚起するいっぽう、娘にリベンジを強要して「とにかく資格を取りなさい」「手に職をつけなさい」と説き、猛勉強を強いるが、その目的は娘を洗脳して、「墓守娘」となれと命じることであった。
核家族における子どもにとっては、仕事で不在の父をのぞけば母しか存在しない。母がいなければ生存できない非力さとは、(中略)つまり神にも等しい存在であることを意味する。その母が2歳のころから日常的に自分の不幸を語って聞かせれば、(中略)[娘]は母を守らなければ、 私だけは母を裏切らないようにしなければ、と誓うのである。
だが、こうした「不幸語り」のシャワーという「虐待」を受けた団塊ジュニア世代の娘たちが母親の敷いた路線通りに大学を出てキャリア・ウーマンとなり、三〇代に差しかかる頃となると、母親は要求を変化させる。孫の顔が見たいと言い出すのである。
摂食障害の女性たちが口々に訴えていたのは「母の要求は私を股裂き状態にするんです」ということだった。
しかし、団塊母親はキャリア・ウーマンになれという要求と結婚・出産で女の幸せを手にしろという要求が娘を股裂きにしていることを理解していない。そこで、娘は母親との距離を置こうと努めるが、孫が誕生すると母親と再接近せざるをえなくなり、母娘の間に再び緊張状態が生じる。かくて、母・娘問題は母・娘・孫問題へと拡大してゆくのである。終章にはタイトルにあるように「母・娘・祖母が共存するために」どうすればいいか、それぞれの立場に立った提言がなされているが、しかし、決定的な解決策はあり得ない。なぜなら、真の原因は経済的発展という至上目的のために家庭から父親を「召集」して、不在にした戦後日本の社会構造にあるのだから。
ALL REVIEWSをフォローする