書評
『秋の花』(東京創元社)
母だからできること
北村薫さんの女子大生「私」を主人公とする推理小説は、多くのファンを持っている。私もそのひとりである。勉強家で男の子みたいな「私」と、おだやかで、すばらしく頭の切れる中年の落語家「円紫さん」が二人で組んで、謎解きをする。
どの作品にも、成長にともなうさまざまなテーマが含まれているのだが、シリーズ三作めの長編『秋の花』(創元推理文庫)では、ラストの方に「許す」という言葉が出てきたのが、印象的だった。
「許す」は、ふだんはまず使うことがない語だ。
「突然、お手紙差し上げる失礼をお許し下さい」
「お許しいただければ、私の方からお宅に伺います」
くらいは書いたり、言ったりする。が、あくまで挨拶としてであって、そうした決まり文句以上の意味を持たせたことはない。
戦争もない、衣食足りた時代に生まれ、これといった事件にも巻き込まれず、ごくふつうに育ってきた私は、自分の存在をかけるような「許す、許される」の関係に立ち至ったことがないのが、現実である。
なので、物語の中の言葉葉は、私の日常生活にはない、重みをもって感じられた。
あらすじは次のようなもの。「私」の出身校である女子高で、文化祭の準備中、ひとりの生徒が死ぬ。屋上から転落して。自殺か、他殺か。遺書もなく、屋上には誰もいなかったことから、不可解な事故死とされる。
亡くなった少女の幼なじみは、その日から、魂の抜けた人となった。吹き降りの中、濡れて滴が服をつたうまでになっても、なおも佇(たたず)む。まるで自らを罰するように。
(ALL REVIEWS事務局注:以下、ネタバレあり)
文化祭に使う垂れ幕を、死んだ子が屋上から吊し、下の階から彼女が引っ張った。上ではちょうど、手すりから身を乗り出したときだった。目の前を落ちていった友だち。
罪の意識に苦しみ、真相を言えなかった自分を責め、雨の川に身を投げようとしたところを「私」と「円紫さん」が助ける。
ラストシーンは、ここからだ。二人は女の子を、死んだ子の母のところに連れていく。すべてを母に話した上で。母は黙って、濡れた服を脱がせ、裸の彼女を、バスタオルでくるんで、抱きとる。
「円紫さん」に「私」は問う。ここへ来たのは、彼女を許せるのは、死んだ子のお母さんだけだからですか、と。「円紫さん」は答える。自分なら、許すことは出来そうにない。ただ、
「救うことは出来る。そして、救わなければならない、と思います。親だから、余計、そう思います」
殺した相手の母の手によって、生まれたままの姿に戻るシーンは、「再生」を表し、象徴的だ。女の子の「死」からはじまった物語は、もうひとりの子の、あらたな「生」へつながろうとしている。ふたつの命をつなぐのは、母親だ。
母親もまた、真相を知ることで、先へ進めるのだろう。娘は自ら命を絶ったのではない、事故死だったのだと、知って。
二人が対面した部屋に、複製画が飾ってあったことが、ほんの二行ほど書かれている。夕暮れどき、針の穴に糸を通そうとする女性の絵、背景描写のように、さらりとふれてあるだけだが、この絵には、すごく意味がある。
夕暮れの針の穴は、暗くて見えにくい「狭き門」だ。糸を通そうとするのは、向こう側へ行こうとする「意志」の現れだ。わが子を殺した子どもとともに、「狭き門」を抜ける。その子にとっても、亡き子にとっても、母親にとっても、それが唯一の救済への道だから。
二人を残し、家を後にしようとする「円紫さん」と「私」を、外へ追ってきて、着替えさせた子のようすを告げる母。
「眠りました」
そのときの母の表情は、聖母像のようであっただろう。
困難を引き受ける、強くて静かな母の姿に、
(親だからできることって、あるのだな)
と思うと同時に、「円紫さん」が若い「私」に言った、
「あなたは、まだ人の親になったことがありません」
との言葉が、自分に向けられたかのように、妙に胸に響いたのだった。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
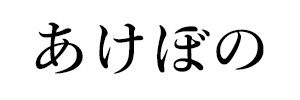
あけぼの(終刊) 2000年7月
ALL REVIEWSをフォローする





































