書評
『ナポレオンの死』(東京創元社)
大手書店をのぞくと、当たり前の話なんだけれど本が山とある。そんな中から、どうやって「わたしの一冊」を見つけ出したらいいのか。ベストセラーは全面的には信頼できない。断言してもいいけれど、そのうちの七割は読む価値ゼロのクズ本なんである。やっぱり読み巧者の書評を頼るのが一番無難だろう。あと、海外文学に関しては訳者で判断するのも手っ取り早い。
アゴタ・クリストフの『悪童日記』(ハヤカワepi文庫)で衝撃的な翻訳家デビュー。以降、精力的にフランス文学の紹介に取り組んでいる堀茂樹氏は、全幅の信頼を置ける名翻訳家なんである。ゆえに、『ナポレオンの死』もまた然り。シモン・レイスという未知の作家の作品だったものの、読み始めてみると、たった百五十ページ弱しかない短さにブーイングを上げたくなるほどの面白さ。氏のメキキストぶりに、今さらながら感心してしまった次第なのだ。
実は、ナポレオンはセント=ヘレナ島で死んだのではなかった。ある巧妙な謀略によって彼は島を脱走し、パリに戻ることができたのである。しかし、ナポレオンが再び歴史の表舞台に現れることはなかった。彼は脱走後、どんな人生を送ったのか。そして、皇帝ではなくなってしまった身で、何を見聞きし、何を学んだのか――。
いわゆる歴史改変小説の体裁を借りた本書で描かれているのは、一人の傑物の成長物語だ。天才的な頭脳をもって、欧州の覇者を夢みたナポレオン。しかし、人間としての彼はどうだったのだろう。セント=ヘレナ島に流される前の彼は、人間としてあまりにも未成熟だったのではないか。歴史を変えるほどの力を有した天才に向かって、「エゴイストでしかなかったあなたに、自分が本当は何物なのか、そして、あなたにとっては単なる手駒にすぎなかった民衆という名の他者の本当の姿を学ぶ機会をあげましょう」と差し出したのが、この物語なのではないかとわたしは思う。そして、ナポレオンの遅ればせの成長を描くことで、作者のレイスは現代を生きる権力者たちへも同じ問いかけをしているのではないか。
とまあ、四角四面な話はさておき、本書の魅力は物語の無類の面白さにあるのだから、まずはナポレオンが遭遇する事件の数々をお楽しみください。後ろについている解説も必読! 堀氏が手がけた本はどれもそうなのだが、書評家泣かせといってもいいほど、作品に関するすべてを網羅して緻密かつ分析的なのだ。そういう意味でも、これは完壁な海外“翻訳”小説なんである。
【この書評が収録されている書籍】
アゴタ・クリストフの『悪童日記』(ハヤカワepi文庫)で衝撃的な翻訳家デビュー。以降、精力的にフランス文学の紹介に取り組んでいる堀茂樹氏は、全幅の信頼を置ける名翻訳家なんである。ゆえに、『ナポレオンの死』もまた然り。シモン・レイスという未知の作家の作品だったものの、読み始めてみると、たった百五十ページ弱しかない短さにブーイングを上げたくなるほどの面白さ。氏のメキキストぶりに、今さらながら感心してしまった次第なのだ。
実は、ナポレオンはセント=ヘレナ島で死んだのではなかった。ある巧妙な謀略によって彼は島を脱走し、パリに戻ることができたのである。しかし、ナポレオンが再び歴史の表舞台に現れることはなかった。彼は脱走後、どんな人生を送ったのか。そして、皇帝ではなくなってしまった身で、何を見聞きし、何を学んだのか――。
いわゆる歴史改変小説の体裁を借りた本書で描かれているのは、一人の傑物の成長物語だ。天才的な頭脳をもって、欧州の覇者を夢みたナポレオン。しかし、人間としての彼はどうだったのだろう。セント=ヘレナ島に流される前の彼は、人間としてあまりにも未成熟だったのではないか。歴史を変えるほどの力を有した天才に向かって、「エゴイストでしかなかったあなたに、自分が本当は何物なのか、そして、あなたにとっては単なる手駒にすぎなかった民衆という名の他者の本当の姿を学ぶ機会をあげましょう」と差し出したのが、この物語なのではないかとわたしは思う。そして、ナポレオンの遅ればせの成長を描くことで、作者のレイスは現代を生きる権力者たちへも同じ問いかけをしているのではないか。
とまあ、四角四面な話はさておき、本書の魅力は物語の無類の面白さにあるのだから、まずはナポレオンが遭遇する事件の数々をお楽しみください。後ろについている解説も必読! 堀氏が手がけた本はどれもそうなのだが、書評家泣かせといってもいいほど、作品に関するすべてを網羅して緻密かつ分析的なのだ。そういう意味でも、これは完壁な海外“翻訳”小説なんである。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
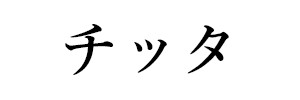
チッタ(終刊) 1997年8月号
ALL REVIEWSをフォローする








































