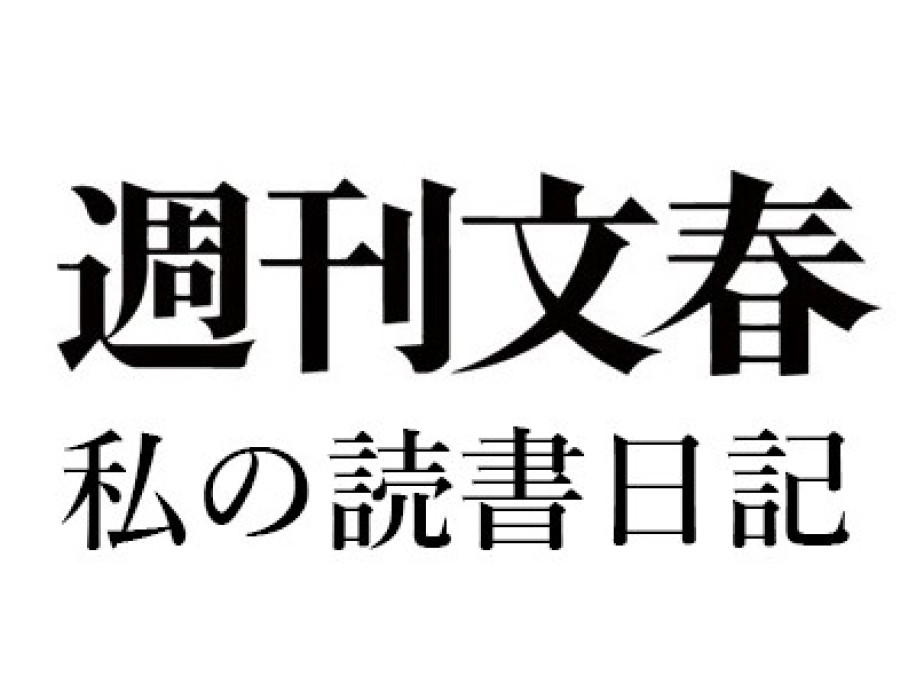書評
『死の蔵書』(早川書房)
古本と現代文学
仮に、夏目漱石の『吾輩は猫である』の初版本があったとする。そして、その初版本は、漱石が署名して森鴎外に贈ったやつで、裏表紙には鴎外の読後感がびっしり書いてある……さて、その本の鑑定値は? ――なんてことばかりしばらく考えていた。ジョン・ダニングの『死の蔵書』(宮脇孝雄訳、ハヤカワ文庫)を読んだせいである。『死の蔵書』の主人公はデンヴァー警察殺人課巡査部長で、作品の途中から、古本(正確にいうなら古書稀覯本)屋になってしまう。作者はいったんミステリー作家としてデビューしたが、一度ペンを置き、古本屋になった後(いまもやってるらしいが)、この作品で再デビューしている。ちなみに、この作品中で殺されるのは古本のバイヤーというか仲介屋。関係者もみんな古本屋。証拠も古本なら、殺人の理由も古本、最後のトリックももちろん古本がらみ、という古本ずくめミステリーなのである。それでもって、帯に「本書には、本好きの心をうずかせる驚くべき知識が詰まっています」と印刷されているとくれば、本好きのわたしとしては手を出さないわけにいかないのである。
古本といっても、『死の蔵書』がとり上げているのは、近・現代文学が多い。そう、我々がふだん読んでいる作者(の初版本やサイン本)が中心になっている。この場合、古本の価値が、作者の文学的価値と相当関係深いところがミソで、どうも作者は古本屋兼批評家兼文学ファンとしての日頃の欝憤を主人公に代弁させているようなのだ。
ジャネット・デイリーが一年中ベストセラー・リストに顔を出しているような社会は、どこかに重大な欠陥があるのだろう。といっても、それを証明することはできない。事実なのだから仕方がない、というだけだ。たまには怖い小説を読みたくなるが、屑ばかりではどうしようもない。こんな子供だましが何千万部も売れているのが、実は一番の恐怖かもしれない。
この手の本を買う連中は、実はあまり本が好きではないのだ。それが私のたどりついた結論だった。キング・ファンやクーンツ・ファンが、じっくり本を選んでいるところなど見たことがない。ルビーの店で、たまたまその現場を見たこともある。一人の男が入口の扉を開けた。だが、中に入ろうとはしなかった。外に立ったまま、戸口に顔を突っ込んで、三つの質問をしただけだ。キングある? クーンツある? パーカーある?
ところで、ジョン・ダニングによれば、現代文学でも古書として大変価値が出てくるものがある。初版本で、作家あるいは作品として価値があり、直筆のサインがあり、さらに歴史的価値のある誰かの直筆が付け加えられている美本、というのがその条件。
なるほど。だが、いまから古本屋に行ってそういう条件の本を探そうと思っても、無理。となれば、自分で作ってみてはどうか。幸い、わたしの本棚には、吉本ばなな先生とか島田雅彦先生とか奥泉光先生とか古井由吉先生といった方々からいただいた美麗初版サイン本がある。
これに、わたしが直筆の感想をしたため、さらに三十年ほど封印する。いいワインを製造するのと同じプロセスである。いまあげた先生方は、間違いなく歴史に名を残す作家なので、これで感想を書いたわたしもそういう作家になっていれば、この美麗初版サイン本には途方もない価値が出ている可能性があるではないか。よし、頑張っていい作家になり、初版サイン本の価値を上げよう!
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする