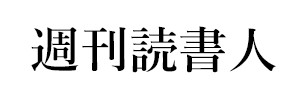書評
『まわり舞台の上で』(文遊社)
一人の異才を通じて見た戦後日本の精神史
荒木一郎はその多才ぶりで知られるが、どちらかと言えば通好みの存在で、映画やテレビドラマ、音楽、小説という具合に活動がいくつものジャンルに跨がっていることもあって、全体像がよくわからない人物であった。おまけに一九九〇年代以降は活動とメディア露出自体がめっきり減る。評者の世代(一九六五年生まれ)からすると、なかば伝説の存在に近い感覚がある。二〇十六年は荒木の歌手デビュー五十周年に当たる。本書はそれを期に、荒木自身が、多岐にわたる活動と波風の多い人生について語ったものだ。ジャンル別に三人のインタビュアーが起用されている。映画・テレビドラマについては映画評論家の野村正昭、音楽については音楽評論家の小川真一、小説については本書の版元である文遊社の久山めぐみが、それぞれ荒木から話を引き出している。
野村と小川は短い荒木一郎論も寄せている。巻末には荒木の小説『ありんこアフター・ダーク』を巡る荒木と亀和田武の対談に加え、作品年譜と、作品の詳細についてのインタビューも載せられている。
これ以上は望むべくもない、荒木一郎に関する一次資料にしてエンサイクロペディアといった趣きの大著で、あらためてその多芸多才ぶりに驚かされると同時に、メディアを通じて見た荒木一郎は、彼の全体のほんの氷山の一角でしかないことを知らされる。
役者やシンガーソングライターのような表に出る仕事だけでなく、プロデュースや楽曲提供、映画やドラマの劇伴なども数多く手掛けている。この女優をあの映画の主役にどうかといったコーディネーターのようなこともしきりにやっている。小説だけでなく漫画原作まで書いているし、干されていた時期にはポルノ女優の事務所経営なんてことにまで手を伸ばしている。
ファンには周知のことかもしれないが意外だったのは、荒木自身としては、やりたかったのはあくまで役者であって、歌手をはじめとする音楽活動は周囲が望むのに応えていただけの余技的なものだとされていることだ。
「もともと、「歌手をやっていきたい」って気持ちがないじゃない。(…)「やらなくていい」って言われたら、もうやらなくていいんだよ」
他人に対する口の悪い評価も面白い。「伊佐山ひろ子に会ったときびっくりしたけどね。何でこんなブスが主役やるんだと思ってさ(笑)」「沢田〔研二〕っていうのは、ナベプロによって作られたスターであり、要するにイエスマンだから」「村上春樹がチャンドラーを訳したのを買ってきてみたときに、もうひどくて。やっぱり全然、何にも分かってないなと」などなど……。
歯に衣着せぬ物言いは「ホサれたときに、「日本の損失だ」って言ったんだよね。「俺はいいけど、日本が損する」」と言ってのける自分の才能に対する絶対的な自信によるものだろう。生意気だったせいもあって、憎悪されたり裏切られたり理不尽な目にも少なからず遭っているのだが、人を責めず、「マイナスなことも、人生をクリエイティブにする一つの要素」と捉え次の活動へと飄々と移っていく。その機転は、タフさというより、「不良」という自己規定から来ている。
荒木の言う「不良」とは、エゴイストであることを突き詰めた結果、人の役に立つ人間であろうとする精神のことだ。この「不良」を指針に振り返ってみれば、ときに行き当たりばったりにも見える荒木の活動が、実は最初から一貫していたことがわかる。一人の異才を通じて見た戦後日本の精神史である。
ALL REVIEWSをフォローする