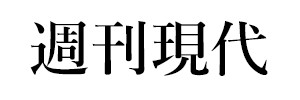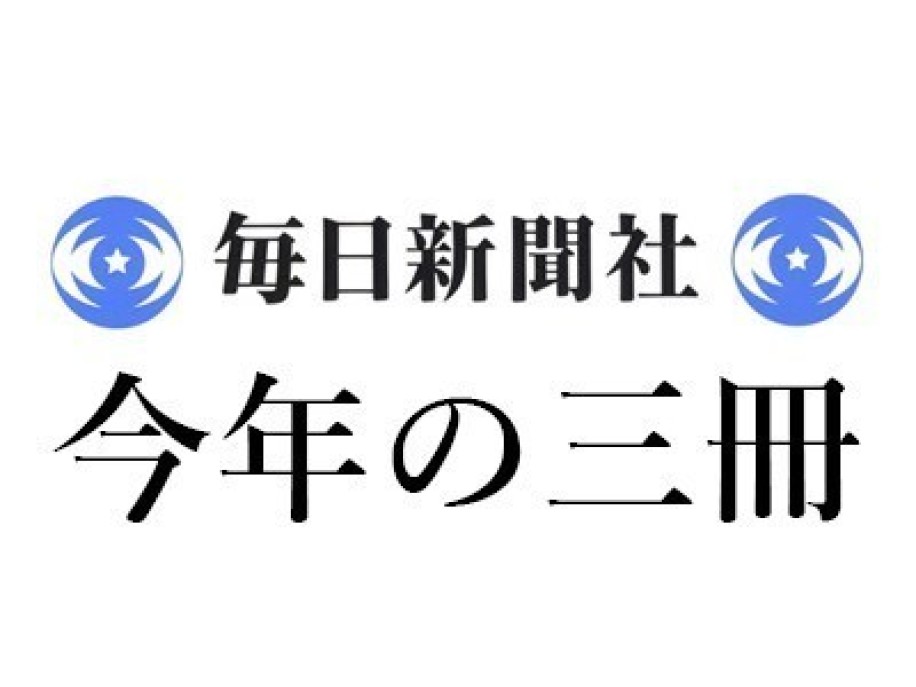書評
『七人の鬼ごっこ』(光文社)
無邪気な調べの童謡が招く連続殺人――精緻な推理と魔力的世界を融合した快作
謎解き小説は、余りの出ない割り算であってもらいたい。不思議な謎が、疑問の余地なく解き明かされることに、読者は大きな快感を覚えるからだ。恐怖小説は、虚数解の出る計算のように、現実からかけ離れたものであってもらいたい。言葉の魔力が支配する空間に閉じこめられることを、不思議を尊ぶ読者は喜ぶからだ。
こうした相矛盾する嗜好を同時に満足させようとして方策を模索し、新しい途を切り拓き続けているのが、三津田信三という作家である。新作『七人の鬼ごっこ』は、その三津田が「記憶の犯罪」というテーマに取り組んだ、意欲的な作品だ。
自殺の決意を固め、一つの賭けをした男がいた。一晩に一回幼馴染の友人に電話をかけ、つながったらその日命を絶つことはしない。七日七晩それを続けられたら、もう一度人生をやり直そう。しかし友人の数が足らず、彼は六日目の相手に「生命の電話」を選んだ。電話を受けた相談員の沼田八重は、事態を重く見て精神保健福祉センターの職員・常葉良光(ときわよしみつ)に連絡をとる。七日目の晩、常葉は自殺の予定地と思われる、摩館(まだて)市の瓢箪(ひょうたん)山へと駆けつけた。だが彼がそこで見たのは、崖から落ちた人間が残したと思しき、血のしみだった。
物語は、自殺を予告してきた男、多門(たもん)英介の幼馴染である速水(はやみ)晃介の視点から綴られていく。刑事の来訪を受けた速水は、自殺を思わせる状態で多門が姿を消したことを告げられる。だが現場の状況には不可解な点があり、他殺の可能性も捨てきれないという。その場合もっとも疑わしいのは、多門から電話を受けた五人の幼馴染なのだ。作家である速水は、やはり幼馴染の一人である大仁多達芳(おおにたたつよし)と連絡を取りながら事件の謎を解こうとする。
謎の電話を受けた事件の関係者が、次々に怪死を遂げていく。彼らはその電話で、「だぁーれまさんがぁ、こぉーろしたぁ……」と歌う、子供の声を聞いていた。その歌声が人々の封印された過去を暴きだすのである。
殺人事件の根底には、もはや原形をとどめないほどに改変された過去の出来事がある。人間の記憶は都合の悪いことを意識の外へと弾き出す、不完全なものだということを作者はよく理解している。事件のねじれは、人々の記憶の歪みを反映したものなのだ。無邪気な調べの童謡が、凄惨さをさらに際立たせている。
ALL REVIEWSをフォローする