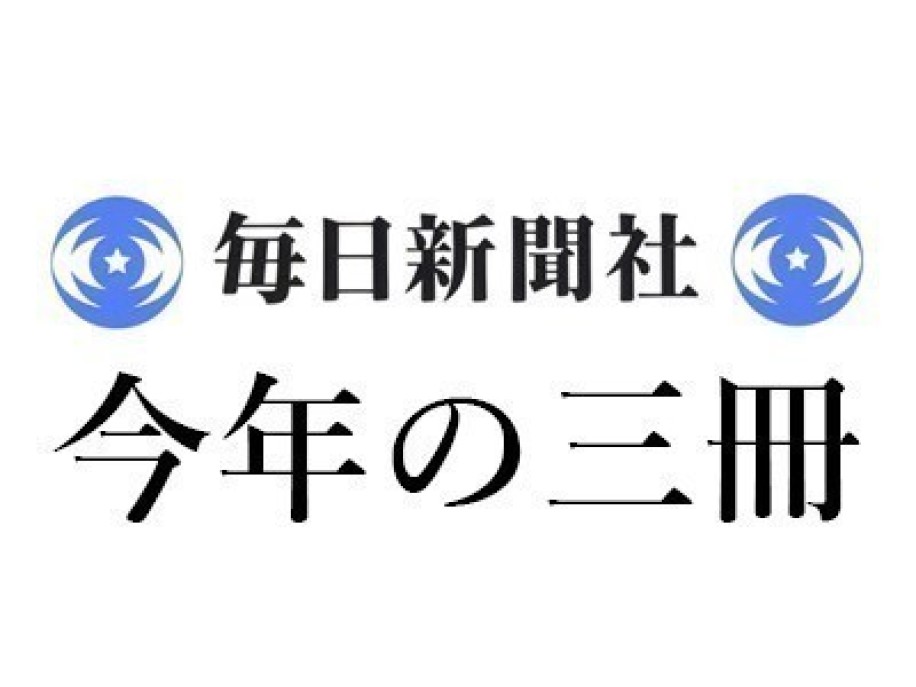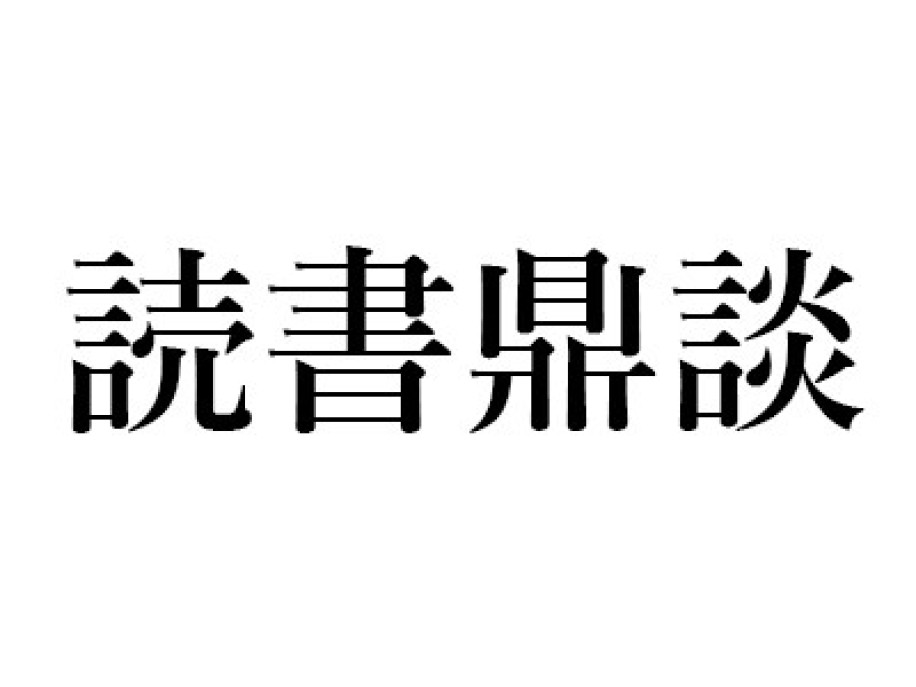書評
『群雄創世紀―信玄・氏綱・元就・家康』(朝日新聞社)
これは、もしかすると日本の歴史学に不可逆的な変化をもたらす本かもしれない。なぜなら、日本の歴史学ではかつて用いられたことのない独創的な方法論が示されているからだ。
といっても難解な歴史書では決してない。なにしろ「ふうん、川中島ってそういうことだったの、なあるほど、だから、あんなに有名なんだ」といった軽い口語文体で書かれているからである。だが見かけとは裏腹に、内容は時代を画するだけの重厚さを備えている。
テーマは帯にあるとおり「戦国大名の英雄伝説は、いつ生まれ、だれが育てたか」を探ることである。しかし、こうした主題なら、あるいは過去にだれかが手を染めているかもしれない。ユニークなのはむしろ、これまで史料としては使い物にならないとされてきた軍記物などの「伝説」に意外な角度から光を当て、そうした伝説相互の差異の中から浮かびあがる偏差に歴史の定説を覆す真実を見いだそうとした点である。
たとえば、著者は、歴史的には重要な戦いとはいえない川中島の合戦が、伝説ではかくも名高いものになったのはなぜかと問いかけ、それはこの合戦が信玄と謙信との言説の戦いでもあったためではないかと推測する。そして、その裏付けとして、両雄が部下の武勲を証明するために出した「感状」や、願いを神前に奉納する「願文」といった一次史料を調べあげ、彼らが、これらの文書という形式を借りて、世間、とりわけ領地の民にむけて自らの正当性や勇敢さを訴えるプロパガンダ合戦を展開して、政権への求心力を加速しようとしたことを証明する。
伝説といえば、川中島に劣らぬほど有名なのが、毛利元就が三人の息子に与えたという三本の矢の話である。伝説のルーツ探しを始めた著者は『毛利家文書』の元就の書状「日頼様御一通」に行き着くが、そこでふと、なぜこの書状だけが選ばれて有名になったのかと考える。「元就のわが子を思うせつせつたる心情の発露が万人の胸を揺さぶって語り継がれるに至ったのだと、ロマンチックに解釈されているが、ほんとうにそうだろうか」。そこで、この手紙を選んで家中に公開した輝元(元就の嫡子)に注目する。というのも、手紙公開の時期が、天下分け目の関ケ原合戦の時と重なるからだ。すなわち、西軍に加担して敗れた輝元は、お家取り潰(つぶ)しという家康の桐喝(どうかつ)におびえ、毛利一族団結のシンボルとして、この「日頼様御一通」を急遽(きゅうきょ)かつぎ出すことを思いついたのである。
毛利元就に関しては、これ以外にも元就ファンが真っ青になりそうな驚くべき偶像破壊的新説が鋭い推理と綿密な実証によって説得力をもって展開されているが、それは読者が本書を手に取るときのお楽しみとすることにしよう。それほどにこの部分は「すごい」のだ。ほかに北条氏綱、徳川家康などについても、鋭い伝説の解読作業が行われている。
教訓。伝説とは、伝説を信じさせようと努力した人に対して、未来が与える報酬である。
【この書評が収録されている書籍】
といっても難解な歴史書では決してない。なにしろ「ふうん、川中島ってそういうことだったの、なあるほど、だから、あんなに有名なんだ」といった軽い口語文体で書かれているからである。だが見かけとは裏腹に、内容は時代を画するだけの重厚さを備えている。
テーマは帯にあるとおり「戦国大名の英雄伝説は、いつ生まれ、だれが育てたか」を探ることである。しかし、こうした主題なら、あるいは過去にだれかが手を染めているかもしれない。ユニークなのはむしろ、これまで史料としては使い物にならないとされてきた軍記物などの「伝説」に意外な角度から光を当て、そうした伝説相互の差異の中から浮かびあがる偏差に歴史の定説を覆す真実を見いだそうとした点である。
たとえば、著者は、歴史的には重要な戦いとはいえない川中島の合戦が、伝説ではかくも名高いものになったのはなぜかと問いかけ、それはこの合戦が信玄と謙信との言説の戦いでもあったためではないかと推測する。そして、その裏付けとして、両雄が部下の武勲を証明するために出した「感状」や、願いを神前に奉納する「願文」といった一次史料を調べあげ、彼らが、これらの文書という形式を借りて、世間、とりわけ領地の民にむけて自らの正当性や勇敢さを訴えるプロパガンダ合戦を展開して、政権への求心力を加速しようとしたことを証明する。
川中島の合戦は、民意を結集するための核として機能したというわけである。(……)そして、そうした機能を果たした戦いであったからこそ、人々の脳裏にこの合戦の記憶が強く刻印され、時を経て大会戦の伝説へと結晶してゆくこととなったに相違ない。やはり伝説が誕生するには、それなりのわけがあるのである。
伝説といえば、川中島に劣らぬほど有名なのが、毛利元就が三人の息子に与えたという三本の矢の話である。伝説のルーツ探しを始めた著者は『毛利家文書』の元就の書状「日頼様御一通」に行き着くが、そこでふと、なぜこの書状だけが選ばれて有名になったのかと考える。「元就のわが子を思うせつせつたる心情の発露が万人の胸を揺さぶって語り継がれるに至ったのだと、ロマンチックに解釈されているが、ほんとうにそうだろうか」。そこで、この手紙を選んで家中に公開した輝元(元就の嫡子)に注目する。というのも、手紙公開の時期が、天下分け目の関ケ原合戦の時と重なるからだ。すなわち、西軍に加担して敗れた輝元は、お家取り潰(つぶ)しという家康の桐喝(どうかつ)におびえ、毛利一族団結のシンボルとして、この「日頼様御一通」を急遽(きゅうきょ)かつぎ出すことを思いついたのである。
毛利元就に関しては、これ以外にも元就ファンが真っ青になりそうな驚くべき偶像破壊的新説が鋭い推理と綿密な実証によって説得力をもって展開されているが、それは読者が本書を手に取るときのお楽しみとすることにしよう。それほどにこの部分は「すごい」のだ。ほかに北条氏綱、徳川家康などについても、鋭い伝説の解読作業が行われている。
教訓。伝説とは、伝説を信じさせようと努力した人に対して、未来が与える報酬である。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする