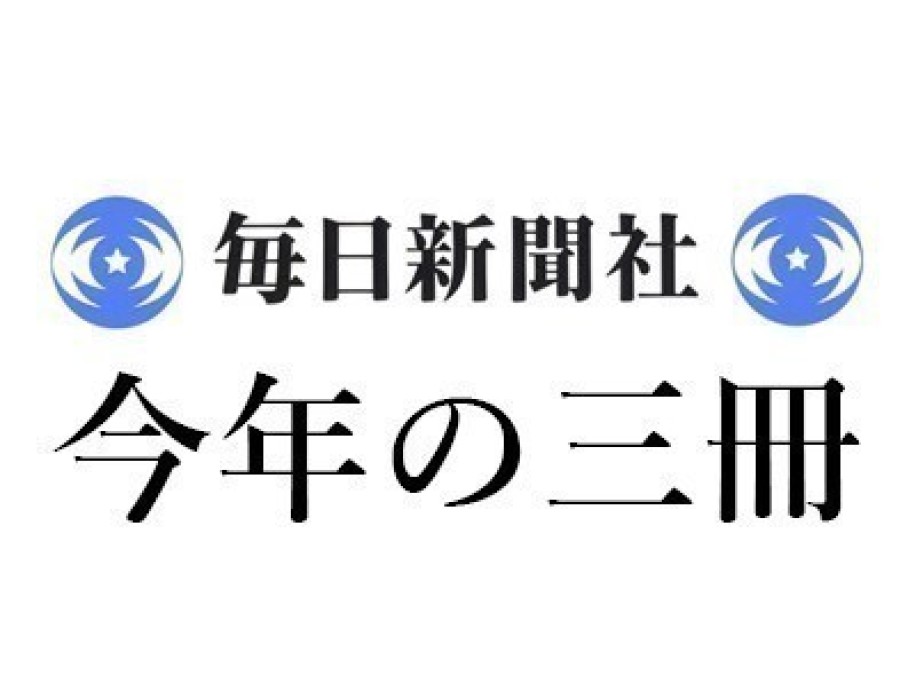書評
『疾走のメトロポリス―速度の都市、メディアの都市』(INAX)
自動車という現代テクノロジーのチャンピオンが社会の前面に登場したのは、一般には十九世紀末の一八九〇年代ということになっている。ところが、本書によれば、実際には、それよりも一世紀早く、十八世紀の末頃には、自動車の試作品が作られ、一八二〇年代には、早くも商業的な運行を開始していたという。ただし、動力は蒸気、つまり蒸気自動車だった。なかでも、イギリスのガーニーの発明した蒸気自動車は、線路の敷設のための設備投資もいらなかったため、前途は蒸気機関車よりもはるかに有望であるかに見えた。
だが結局、蒸気自動車は見捨てられ、蒸気機関車が時代の覇者となった。なぜか? 著者はその原因を新しい交通システムを受け入れるべきニッチ(マーケットのすき間)の問題に求める。すなわち蒸気機関車は、まったくあたらしい敷地に専用の軌道を敷設したため、既得権に固執するニッチ先住者と争う必要がなかったのに対して、蒸気自動車には、舗装道路を独占使用する乗合馬車という強敵がおり、しかも、道路自体も多くの経営母体によって私有されていた。その結果、蒸気自動車は乗合馬車との競争に敗れ、歴史に足跡を残すことはなかった。
自動車が復活するのは十九世紀も世紀末になってからのことである。復活の原因は、エンジンの燃料がガソリンに切り替わって小型軽量化したこともあるが、それ以上に、道路から乗合馬車が姿を消してニッチ先住者がいなくなったことにある。だが公共の乗り物としての役割はすでに鉄道が果たしていたので、自動車はもっぱらその活路を個人的な用途のほうに求めることになる。ひとことでいえば自動車は、パーソナルな消費という観念が生まれたときに初めてそのニッチを見いだしたのである。とはいえ、自動車は一九二〇年代までは、金持ちの遊び道具、贅沢(ぜいたく)品であり、本格的な消資マーケットを見いだすには至らなかった。
同じことは、通信の分野についてもいえる。一八四〇年頃に電信が登場したとき、遠隔通信のニッチはすでに腕木通信によって独占されていた。そのため、電信は既存のネットワークと競合しない鉄道の運航管理に活路を求めることになる。また、無線通信が世紀末に出現したときも同じことが起こった。つまり、ニッチは電信のネットワークによって占領されていたため、使用は船舶、あるいは戦場といった特殊なものに限られていたのである。無線はむしろマニアのための遊具だった。
つまり自動車にしろ無線にしろ、基幹システムとは競合しないニッチを見いだしはしたが、その基盤は一部の限られた消費者に支えられたものにすぎなかった。著者は、新しいシステムのこうした段階の消費をパンクな(特出した)消費と呼ぶ。この段階にあっては、熱烈なマニアが相手なので、技術は深化するが、マーケットは閉鎖的である。いっぽう、基幹システムの側では、マーケットが成熟してしまっているので、機能の過剰化や大型化といったシステムのバロック化(付加価値化)で消費を掘り起こそうとする。こうした双方の状態が煮詰まったとき、そこに、ポップな(大衆的な)消費が生まれる。それは、自動車についていえば、T型フォードの登場であり、無線で言えば、双方通行性を放棄したラジオの出現というかたちを取る。だが著者によれば、新しいシステムのこうしたポップな消費が生まれるにはパンクな消費の段階で、これを育成するマニア、および彼らの連帯を支えるメディア・コミュニティーを必要とする。そして、このコミュニティーがリゾーム的(根茎的)に増殖し、やがて、そこからパーソナルな消費単位としての家族が浮上したとき、ポップ消費が生まれるのである。
このように、本書は、従来の科学史、産業史では顧みられなかった消費やニッチ、あるいはマニア的共同体というマーケティング的要素をあらたに導入することで、とにかく無味乾燥になりがちの科学技術史を一気に人間的な領域に取り込むことに成功している。こうした問題を扱った「バロックな消費とパンクな消費」、その応用編である「蒸気自動車の十九世紀」「メディア・コミュニティーとしての無線文化」の章は、シヴェルブシュの著作を読むような面白さにあふれている。また都市計画や宇宙旅行、あるいは地下都市、宇宙ステーションといった、近代テクノロジーの成果が、ヒュー・フェリス、ツィルコフスキー、ゴダート、オーベルトなどの発明家たちの哲学的・宗教的夢想から生み出されたものであることを指摘した各章、さらにボーア戦争のゲリラ戦の英雄バーデン・パウエルの組織したボーイ・スカウトが、没イデオロギー的な技術偏重主義によって少年たちの心を捕らえたとする主張も極めて刺激的である。
二次資料が中心であることと、横文字趣味がマイナスといえばマイナスだが、これまでの科学史家にはない新鮮な脱領域的観点を提示した点で、本書は高く評価されるべきだろう。
【この書評が収録されている書籍】
だが結局、蒸気自動車は見捨てられ、蒸気機関車が時代の覇者となった。なぜか? 著者はその原因を新しい交通システムを受け入れるべきニッチ(マーケットのすき間)の問題に求める。すなわち蒸気機関車は、まったくあたらしい敷地に専用の軌道を敷設したため、既得権に固執するニッチ先住者と争う必要がなかったのに対して、蒸気自動車には、舗装道路を独占使用する乗合馬車という強敵がおり、しかも、道路自体も多くの経営母体によって私有されていた。その結果、蒸気自動車は乗合馬車との競争に敗れ、歴史に足跡を残すことはなかった。
自動車が復活するのは十九世紀も世紀末になってからのことである。復活の原因は、エンジンの燃料がガソリンに切り替わって小型軽量化したこともあるが、それ以上に、道路から乗合馬車が姿を消してニッチ先住者がいなくなったことにある。だが公共の乗り物としての役割はすでに鉄道が果たしていたので、自動車はもっぱらその活路を個人的な用途のほうに求めることになる。ひとことでいえば自動車は、パーソナルな消費という観念が生まれたときに初めてそのニッチを見いだしたのである。とはいえ、自動車は一九二〇年代までは、金持ちの遊び道具、贅沢(ぜいたく)品であり、本格的な消資マーケットを見いだすには至らなかった。
同じことは、通信の分野についてもいえる。一八四〇年頃に電信が登場したとき、遠隔通信のニッチはすでに腕木通信によって独占されていた。そのため、電信は既存のネットワークと競合しない鉄道の運航管理に活路を求めることになる。また、無線通信が世紀末に出現したときも同じことが起こった。つまり、ニッチは電信のネットワークによって占領されていたため、使用は船舶、あるいは戦場といった特殊なものに限られていたのである。無線はむしろマニアのための遊具だった。
つまり自動車にしろ無線にしろ、基幹システムとは競合しないニッチを見いだしはしたが、その基盤は一部の限られた消費者に支えられたものにすぎなかった。著者は、新しいシステムのこうした段階の消費をパンクな(特出した)消費と呼ぶ。この段階にあっては、熱烈なマニアが相手なので、技術は深化するが、マーケットは閉鎖的である。いっぽう、基幹システムの側では、マーケットが成熟してしまっているので、機能の過剰化や大型化といったシステムのバロック化(付加価値化)で消費を掘り起こそうとする。こうした双方の状態が煮詰まったとき、そこに、ポップな(大衆的な)消費が生まれる。それは、自動車についていえば、T型フォードの登場であり、無線で言えば、双方通行性を放棄したラジオの出現というかたちを取る。だが著者によれば、新しいシステムのこうしたポップな消費が生まれるにはパンクな消費の段階で、これを育成するマニア、および彼らの連帯を支えるメディア・コミュニティーを必要とする。そして、このコミュニティーがリゾーム的(根茎的)に増殖し、やがて、そこからパーソナルな消費単位としての家族が浮上したとき、ポップ消費が生まれるのである。
このように、本書は、従来の科学史、産業史では顧みられなかった消費やニッチ、あるいはマニア的共同体というマーケティング的要素をあらたに導入することで、とにかく無味乾燥になりがちの科学技術史を一気に人間的な領域に取り込むことに成功している。こうした問題を扱った「バロックな消費とパンクな消費」、その応用編である「蒸気自動車の十九世紀」「メディア・コミュニティーとしての無線文化」の章は、シヴェルブシュの著作を読むような面白さにあふれている。また都市計画や宇宙旅行、あるいは地下都市、宇宙ステーションといった、近代テクノロジーの成果が、ヒュー・フェリス、ツィルコフスキー、ゴダート、オーベルトなどの発明家たちの哲学的・宗教的夢想から生み出されたものであることを指摘した各章、さらにボーア戦争のゲリラ戦の英雄バーデン・パウエルの組織したボーイ・スカウトが、没イデオロギー的な技術偏重主義によって少年たちの心を捕らえたとする主張も極めて刺激的である。
二次資料が中心であることと、横文字趣味がマイナスといえばマイナスだが、これまでの科学史家にはない新鮮な脱領域的観点を提示した点で、本書は高く評価されるべきだろう。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする