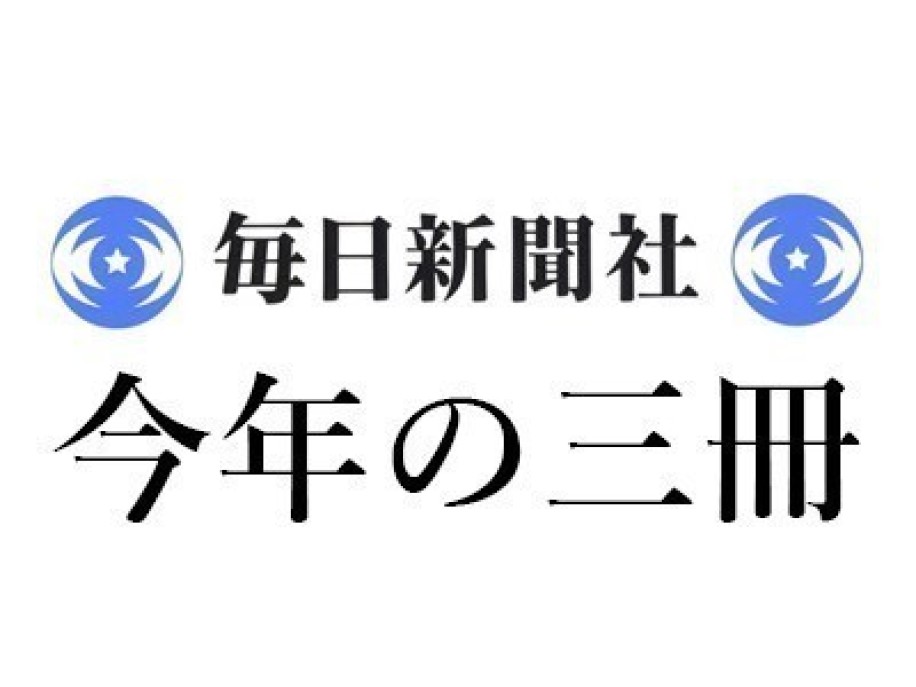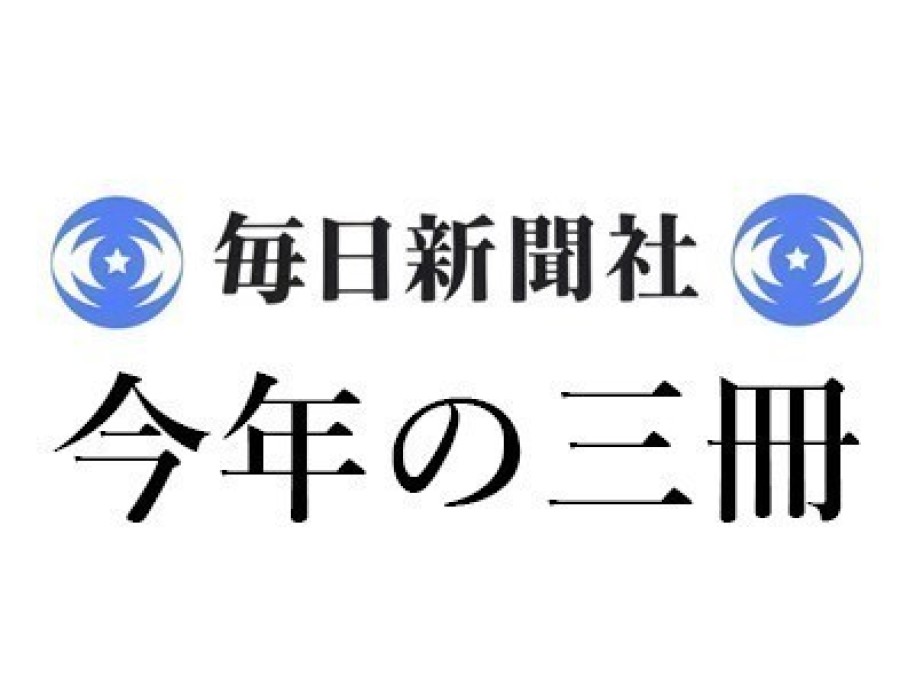書評
『嘆きの花園―歌集』(ジャテック出版)
「同時代」のようなもの
いまぼくはこの原稿を、パリのホテルの一室で書きはじめたところだ。朝三時、東京は午前十時だろうか。『ゴーストバスターズ』も再校ゲラを戻して、ついに完全に著者の手元を離れた。もう、ぼくのところに戻ってくることはない。書いていた頃のことがまるで遠い昔のような気がする。読者のみなさんには今月末にはお届けできるだろう。
およそ九年にわたる「ゴースト」との付き合いが終わり、ぼくの頭の中はもっぱら連載している長編『日本文学盛衰史』の舞台となる「明治」、それも三十八年から四十五年頃の「明治」で占められるようになった。それは近代日本でもっとも魅力的な、そして可能性に富んだ時代だった、そういう思いが、書き進むにつれ強くなってゆく。そしてさらに、遥か遠い過去のできごとであるのに、なぜか「同時代」という言葉が身にしみてならない。明治末の作家や作品に「同時代」性を感じても、逆にいまの作家や作品から感じることが少ないのはなぜなのか、そのこともまた少しずつ書いてゆくつもりだ。
まだ、夜は明けてこない。こちらに持ってきた仕事ははかどらず、ぼくはさっきから、ぼんやり藤原龍一郎のいちばん新しい歌集『嘆きの花園』(ジャテック出版)の頁をめくっている。
もしも、ぼくが小説ではなく短歌を作ることを選んでいたら、彼の歌のようなものを書いたかもしれない。そんな気がして、実は彼の歌を読むのはいつも少し恥ずかしい。
ハヤカワ・ミステリ648コーネル・ウールリッチ著稲葉由紀訳『ぎろちん』
伊藤整『日本文壇史』読み継ぎて孤立無援はわれのみならず
同時代的都会的感性のサイコ・ホラーに読み疲れたる
で、こんな歌を読むと、ぼくは心の底から共感し、これはそもそも「同時代」というものがほんとうは何を指しているのか、彼にとって(彼の世代にとって)「同時代」という言葉がどんな意味を持っているのかということを歌っているのだが、わかっていただけるであろうか。
二首目に出てくる伊藤整の『日本文壇史』は、近代文学百余年の中でもベスト3に入るべき超名作だが、実のところ、これは文学(文壇)史を飾ってきた数百人の作家の生涯をごくごく簡明にそしてただひたすら書き連ねただけの作品にすぎない。しかし、これを読むと誰だって異様な感銘を受けてしまうのは、この不思議な文学(文壇)史の底に流れている「作品よりそれを書いた作家の生涯の方が面白い」というペシミズムのせいだろう。生涯で数行の記述しか与えられない作家が次々と現れては消えてゆく。痛切な経験も作品として評価され残ってゆけば作家も救済されるのだが「あんたの下手な一冊より、数行で書けてしまうあんたの生涯の方が立派な作品だよ」といわれてしまえば作家の立つ瀬がない。立つ瀬がなくなってしまえば、作家が残すのは名前と作品名だけになる。他にいったい何が残るっていうの? これはもうどん詰まりのニヒリズムではあるまいか。
最後に残るのは固有名詞。動詞も形容詞も副詞もいらない。作品を豊かにするものはなにもいらない。それが藤原龍一郎の「同時代」なのである。
「同時代」は「感性」という言葉と対で使われるものだった。そんなもの疲れるだけじゃないかと藤原はいう。伊藤整もいう。ぼくだっていうさ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする