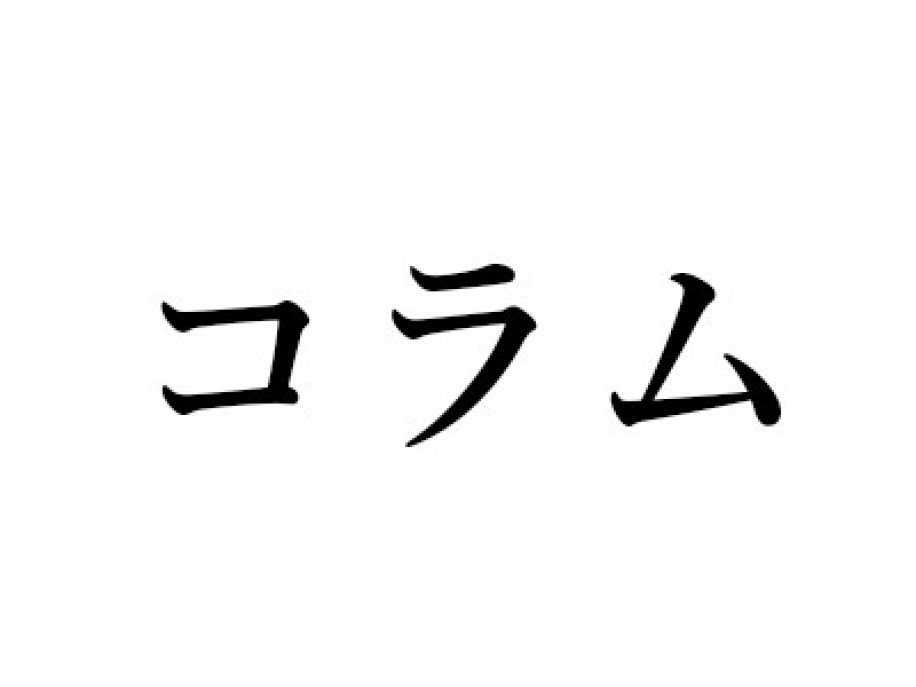書評
『日本語の外へ』(角川書店)
人生のすべては母国語のなかにある
「過剰に情緒的文芸的だった一九六〇年代という時代をどうにかこうにかやり過ごした身としては、片岡義男の文体と書き言葉は衝撃だった。しかし、当時はまだ細々と生き残っていた『文壇』と文壇的センスは、うかつにも片岡義男という日本語表現上の事件に気づくことなく黙殺した。かえすがえすも惜しむべきことである」と関川夏央は書いている。片岡義男は心理描写を排した極度にシンプルな言葉づかいの、不思議な乾いた抒情を感じさせる小説で多くの読者を得た。彼の小説は日本文学の中にまったく類を見ないものであったが、ほとんど論じられたことがなかった。それはなぜだったろう。
「売れる」エンタテインメント文学としてはなから批評の対象にされなかったからだろうか。あるいは、作品の核にある未知の何かが「文壇」的批評を怯えさせ、無意識のうちに遠ざけられたからだろうか。
だが、謎は謎のまま残り、時だけが流れた。そして、片岡義男は六百頁を超える巨大な評論『日本語の外へ』(筑摩書房)を持ってぼくたちの前に姿を現したのである。
ぼくは『日本語の外へ』を読みながら、一九九七年は片岡義男のこの本と加藤典洋の『敗戦後論』(講談社)の二冊の出現によって画期的な年として記憶されることになるだろうと思った。この二冊は「戦後」という特殊な時空間を、他人の歴史ではなくそこに生きる者として解き明かそうとし、ついにそのことに成功したからである。
『日本語の外へ』の白眉は後半の第二部「日本語」だ。第一部で「アメリカ」という文化を語った片岡義男は、第二部で英語と比較しつつ日本語の本質に激しく迫ってゆく。「戦後」の、いや現在の日本のすべての問題の根源には日本語が横たわっているからだ。
言葉はものすごく不自然なものだ。そして、その不自然さにおいて、まさにそれは人間のものだ。……。そしてこのようにして身につけた複雑なルールを、その精緻さのままに駆使できるようになった言葉つまり母国語は、その人のすべてだ。その人という、そのようにしてそこにそうある存在、そしてその人がこうありたいと思う願望などすべては、その人が身につけた母国語のなかにある。
すべての言語はそれぞれの美点と歪みを持つ。だから、日本語のなかで生きるぼくたちは、日本語という歪みを通してしか考えられない、そう、日本語の歪みのなかでしか生きられない。「戦後」という時空間は、実はその「歪み」そのものなのである。では、ぼくたちはついにその「歪み」から自由になることはないのだろうか。
そんなことはない、と作者はいう。「歪み」を知り、そのことを熟知した上で「歪み」を駆使しながら、日本語の外へ出ていくことによってのみ、ぼくたちは「歪み」から自由になることができる、と作者はいう。
僕の背後のぜんたいから、非常に明るい光が射して僕の全身をかすめてとおり越し、前方に向けて走り去って消えた。ほんの一瞬の、しかし強力に明るいその光に対して、子供は子供らしく反応した。誰かがうしろから懐中電灯を照らしたのだ、と僕は思った。僕は振り返った。道を歩いている人はひとりもいなかった。
一九四五年、八月六日、午前八時十三、四分頃、片岡義男は岩国の自宅の近くで鮮烈な光を浴びる。それは広島に投下された原爆の閃光だった。
政治とも「戦後」ともいちばん遠いと思われた片岡義男の肉声をようやくぼくたちはいま聞こうとしている。
【単行本】
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする