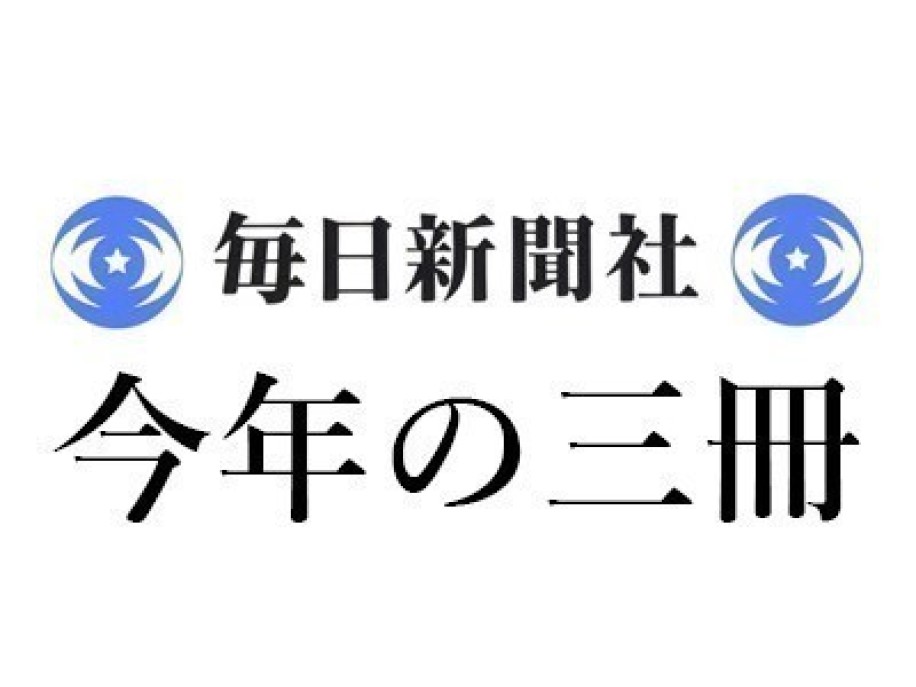書評
『生きものの風景―あるナチュラリストの自然誌』(東京創元社)
緑陰に憩う
読書が時と場所を選ぶものなら、この本は旅に持って出て湖畔の緑陰で読みたい。全国で百人ほどしかいないレンジャー(国立公園管理官)。この地味だが魅惑的な仕事のなかで親しんだ各地の自然や生物の思い出をつづっているのが百武充の『生きものの風景――あるナチュラリストの自然誌』(主婦と生活社)だ。コガラのツピーツピーというためらいがちのさえずりから始まり、黄金色のフクジュソウ、赤紫のカタクリ、そして林床をニリンソウが白く埋めつくす十和田の春。幻のシマフクロウに会って、その影を目が痛くなり涙がとまらなくなるまで見つめ続けた知床の冬。あるときは築別駅で赤いセーターの男が不意に口笛を吹く。まったく意外なシベリウスの第二交響曲が、根室の針葉樹林の静けさに重なっていく。
ぼくという一人称で語られる文章は若々しく、視覚的で、樹々の匂いや風や鳥の鳴き声も感じさせる。しかもたんに旅人が切り取った風景ではない。餌台にくるカケスがトウキビを一粒くわえてはなんとかもう一粒持っていけないかと小首をかしげて思案する姿など、生き物の生活を見、野性に干渉すまいと自制しながらも、個体に仇名(あだな)をつけてつきあっている姿がうらやましい。
北方志向の著者は北海道再赴任を望んだのだが、転勤先は南も南、石垣島だった。ここからはビーチパラソル華やかな砂浜で寝ころんで読むのもいい。バンナ岳の夜の底から浮かび上がる数千のホタル。海を泳いでいると目の前を横ぎる小魚の群れは水の色に溶け込んで、無数の黒い目だけが動いてみえる。ここにも素晴らしい自然があった。しかしオニヒトデの大発生、開発による赤土の流入で、海は見事なアザミサンゴの墓場となっていく。
「かけがえのない沖縄の自然は、どうなってゆくのだろうか。そして離島のさらに離島といわれ、中央との格差がそれだけ大きな八重山の人々は、そのことをどう考えているのだろうか」という著者の複雑な気持ちは、都会人が安易に自然保護を口にするのとは遠く隔たっている。外から来た者でもあり、内にいる者でもあるレンジャーは、悩み深い大変な仕事なのだ。
文章中には現時点での動・植物学の成果がさりげなくちりばめられ、さらに著者による挿画やカラー写真もあって、なんともゼイタクで味の濃い一冊だ。望みに反して、カンカン照りの東京で読んだのだけれど、すだれ越しの風が心なしか涼しく感じられた。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする