書評
『新装版 されどわれらが日々』(文藝春秋)
私の知らない、あの季節
私は一九七〇年を高校生で迎えた。都立では高校全共闘が盛んにやっていて、私の小学校時代の男友だちもある事件で捕まり、ムショへの長い旅に出ていた。しかし、私のいた女子高では制服廃止運動が起きたくらいで、他校の紛争を横目で眺めながら、私たちは柴田翔著『されどわれらが日々―』(文春文庫)の読書会をもった。初読で感じたのは、なんと駒場や本郷という言葉がよく出てくるのだろう、ということだ。まるで普通名詞のように。野尻湖の東大寮や芝白金の東大女子寮も登場する。そのことに憧れの裏返しのような反発を覚えた。
そしてつづく『贈る言葉』はとくにそうなのだけれど、私が受けようと思っていた大学に入ると、女子は不幸になるのだな、と暗然とした。『されど~』で自殺する梶井優子。
「ねえ、あなたに判るかしら。女の子が、高校に入った頃から、もう何を思い、何を待っているか……それでいてこわがるなんて」
この言葉は痛切だった。
「抱かれたことのない、接吻されたことさえない二十一歳! 何て醜いの!」
その醜さ、重さを、読書会の全員が感じていた。私たちは自分を持てあましていた。禁欲は惨めで暗い。しかし性の解放の明るさの末に待ちうけるのが、多くの場合異様な手術台、光る器具であることも、すでに遠藤周作『わたしが・棄てた・女』や石原慎太郎『太陽の季節』などで知っていたはずである。
「結末は、いつも女が処理しなければならないのです」
この小説は私の生まれる二年前の血のメーデー事件、そして山村工作隊、「球根栽培法」などに代表される日本共産党の軍事方針、六全協で左翼冒険主義が批判され、「党がまちがうはずはない」と信じていた学生党員が挫折してゆく、その荒廃を描いている。主人公節子は女子大から駒場の歴研に参加して政治運動により深くコミットするが、その婚約者の文夫は、「何事も経験だと思って」一、二回のデモへは行く程度で、英文学の大学院にすすむ。
その時代を生きないでいうのは傲慢だが、なんで二十代前半で、こんなに老い、人生をあきらめてしまうのか、そのことが腹立たしかった。
私たちは徹底的に、節子の立場で読んだ。自分が妊娠させた女子学生の自殺を長々と語る文夫の自慰的な甘えは許しがたい。なぜ新しい恋人に過去の女性関係を語りたがるのか、わからない。なぜ、男が語り手で、女はつねに聞き手、なのだろう。そうした男性の自己中心主義はこの小説全体に流れていると感じた。
宮下という英文科の助手はいう。「女の人は、昔風な言い方になりますけれども、男に仕えてくれなければいけないと思うんですよ。その代り、ぼくは自分の妻を裏切るようなことは絶対しません。将来、ぼくが博士論文を出す時には、世間から何と言われようとも、その扉には、「黙々として尽して呉れた妻へ」という献辞を、必ず入れようと思っています」、「女の人の幸福は学問をする所などにはありません」
その彼を度しがたい、と見たにちがいない文夫も、なにほど違っていただろうか。
たとえば、同じ四年制の大学を出たのに、彼は婚約者を「英語とタイプと、それに少しばかりのフランス語ができ、翻訳兼タイピストとして、ある商事会社に勤めていた」と表現する。この下目に見ている感じが嫌だった。
年は一つ違いで、夫婦になるというのに、文夫は「なんだい」「本気かい」と話し、節子は「あなた、お気がつきにならなかった?」「送ってきて下さるわね」といつも敬語を用いる。この不対等性に、関係は象徴され、異和感を感じた。
「私、こうやって、一生あなたのお食事、作って上げるのかしら」
とものうげに節子が問うても、文夫は
「奥様稼業が厭なら、一生勤めていたっていいよ」
と、まるで珍腐なことをいう。
性別役割分担は私にとっては本書の大切なモチーフであり、後半、再び、
「私、こうやって、一生あなたのお食事作って上げるのかしら」
と節子が絶望的ともいえる響きでくり返しても、
「作ってほしいと思っているんだよ」
と文夫は弁解するように答えるだけだ。遠戚でもあった二人が小さい頃、積木を積むとき、文夫はそれに熱中して節子をおきざりにした。業績を上げるため研究に没頭する男性は、女性を振り返らない。女性によって変わることもなく、女性の側に身をおいて、共に生きることなどあるのだろうか。
心とつながろうとしたのに、身体しか得られなかった。そのとき節子はこの結婚ははじめから間違っている、と感じ、一人旅立つ。ある男友達は、「あの小説でなぜ別れる必要があるかわからない」といったが、私は断然、別れるべきだ、と読み直してもそう思った。
宮下のような度しがたい連中はいまなお大学に跋扈しているし、企業に身をおいて過去を懐旧のうちに語ろうとする人々には、共感を持ち得ない。革命か小市民的生活か、あれかこれかでは淋しすぎる。それでも私がこの本を愛するのは、女性の自立の書として読めるからである。ただ、節子のような性急で清算的な方法でなく、も少しいいかげんに、しぶとく、あきらめることを拒否したい、と思うばかりである。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
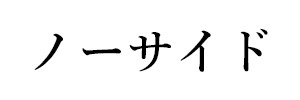
ノーサイド(終刊) 1993年~1996年
ALL REVIEWSをフォローする










































