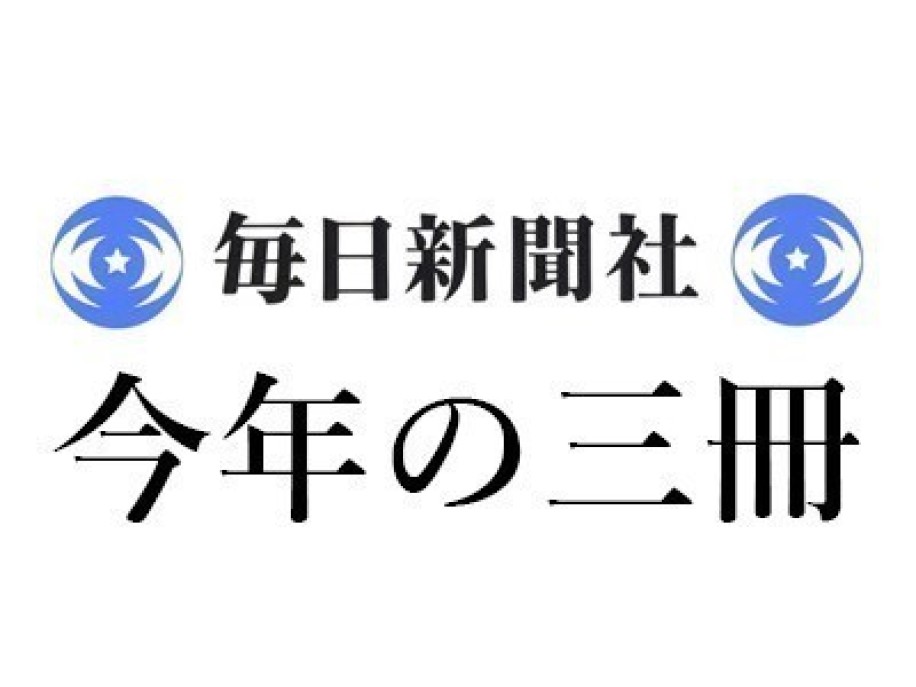書評
『六〇〇〇度の愛』(新潮社)
キタ――! テルちゃん(宮本輝)、キタ――ッ! んな感じなんでありますの。すでに第一三三回芥川賞の結果も出ている時期に、第十八回三島賞の選評を云々するのは気が引けるんですけども、三島賞は年一回のお祭りですもの、許して下さいまし。
テルちゃん曰く。
そのとーりっ! たまにゃあいいこと云うじゃんね。ところが、その後がいけませんの。
〈三つのリング〉って、あなた、〈長崎の原爆〉〈ロシア正教〉〈アトピーに悩む青年〉〈女主人公〉…………四つじゃん!
というわけで、相変わらず前衛がわからないテルちゃんと、未読の方のために鹿島田さんの受賞作がどんな手法で書かれたのかを、わたくしのわかる範囲でお伝えいたしますと、これは幼い我が子を隣人に預けたまま、一人長崎に飛んだ女性の数日間の行動と意識を、〈女〉という三人称と〈私〉という一人称による、デュラスの『愛人』を念頭においたかのような〈言葉の河〉を流されていく文体をもって描いた小説なんですの。
自分を束縛する母と、アルコール依存症の果てに飛び降り自殺をした兄の思い出。長崎のホテルで出会うアトピー性皮膚炎による無数の傷を体に刻印した青年との情事。そうした個人の意識と時間の中に、ときおり原爆という大文字の歴史的記憶と時間がまぎれこむ。佯狂者と呼ばれる、財産や家や家族を捨て祈りの生活によってのみ生きたロシア正教の聖人のイメージが、登場人物の面影にふいに重なる。過去も現在も、歴史上の大きな時間も個人の平凡な時間も、賢者も愚者も、愛も憎しみも、〈世界という海〉へと流れこむ〈言葉の河〉によってただ一様に流されてゆく。一個人の精神では捉えきれようもない広漠とした時間と、それゆえに生まれる虚無を、緊迫感を保ち続ける文体で語り尽くさんとした、これは誠実な実験小説なんであります。
で、ですね。言葉の河ならぬ泥の河で知られるテルちゃんこそ、芥川賞選考委員をこれからもお務めになられますなら、“歴史や時代の変化とは無関係に読みつがれている”言語芸術としての小説をお読みになってはいかがかと進言させていただきとうございますの。フラン・オブライエン『スウィム・トゥー・バーズにて』、ウルフ『波』、シモン『アカシア』、ペレック『人生 使用法』、ナボコフ『セバスチャン・ナイトの真実の生涯』、サラマーゴ『修道院回想録』、バース『やぎ少年ジャイルズ』、ピンチョン『重力の虹』、莫言『酒国』、残雪『突囲表演』、笙野頼子『金毘羅』あたりからぜひ。
【この書評が収録されている書籍】
テルちゃん曰く。
(文学作品において、ほんの少し抜きん出るにはどうしたらいいかというと)おそらく、古今東西の抜きん出た小説を読むのがいちばんいいのである。(略)言い換えれば、最近の新しい書き手が、歴史や時代の変化とは無関係に読みつがれている作品に触れることなく、小説に手を染めてしまったという現実がはっきりと浮かびあがってくる。
えらそうな言い方をさせていただくならば、小説家として基本的な勉強をせずに、小説を書き始めた人たちが、新しい書き手としてもてはやされているということになる。
そのとーりっ! たまにゃあいいこと云うじゃんね。ところが、その後がいけませんの。
受賞作となった鹿島田真希氏の「六〇〇〇度の愛」は、私には支離滅裂な三つのリングが最後までつながらないまま、何が何だかわからないまま終わったという印象しか受けなかった。/長崎の原爆、ロシア正教、アトピーに悩む青年、幼児をふいに隣家に預けて衝動的にひとり旅に出た女主人公……
〈三つのリング〉って、あなた、〈長崎の原爆〉〈ロシア正教〉〈アトピーに悩む青年〉〈女主人公〉…………四つじゃん!
というわけで、相変わらず前衛がわからないテルちゃんと、未読の方のために鹿島田さんの受賞作がどんな手法で書かれたのかを、わたくしのわかる範囲でお伝えいたしますと、これは幼い我が子を隣人に預けたまま、一人長崎に飛んだ女性の数日間の行動と意識を、〈女〉という三人称と〈私〉という一人称による、デュラスの『愛人』を念頭においたかのような〈言葉の河〉を流されていく文体をもって描いた小説なんですの。
自分を束縛する母と、アルコール依存症の果てに飛び降り自殺をした兄の思い出。長崎のホテルで出会うアトピー性皮膚炎による無数の傷を体に刻印した青年との情事。そうした個人の意識と時間の中に、ときおり原爆という大文字の歴史的記憶と時間がまぎれこむ。佯狂者と呼ばれる、財産や家や家族を捨て祈りの生活によってのみ生きたロシア正教の聖人のイメージが、登場人物の面影にふいに重なる。過去も現在も、歴史上の大きな時間も個人の平凡な時間も、賢者も愚者も、愛も憎しみも、〈世界という海〉へと流れこむ〈言葉の河〉によってただ一様に流されてゆく。一個人の精神では捉えきれようもない広漠とした時間と、それゆえに生まれる虚無を、緊迫感を保ち続ける文体で語り尽くさんとした、これは誠実な実験小説なんであります。
で、ですね。言葉の河ならぬ泥の河で知られるテルちゃんこそ、芥川賞選考委員をこれからもお務めになられますなら、“歴史や時代の変化とは無関係に読みつがれている”言語芸術としての小説をお読みになってはいかがかと進言させていただきとうございますの。フラン・オブライエン『スウィム・トゥー・バーズにて』、ウルフ『波』、シモン『アカシア』、ペレック『人生 使用法』、ナボコフ『セバスチャン・ナイトの真実の生涯』、サラマーゴ『修道院回想録』、バース『やぎ少年ジャイルズ』、ピンチョン『重力の虹』、莫言『酒国』、残雪『突囲表演』、笙野頼子『金毘羅』あたりからぜひ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする