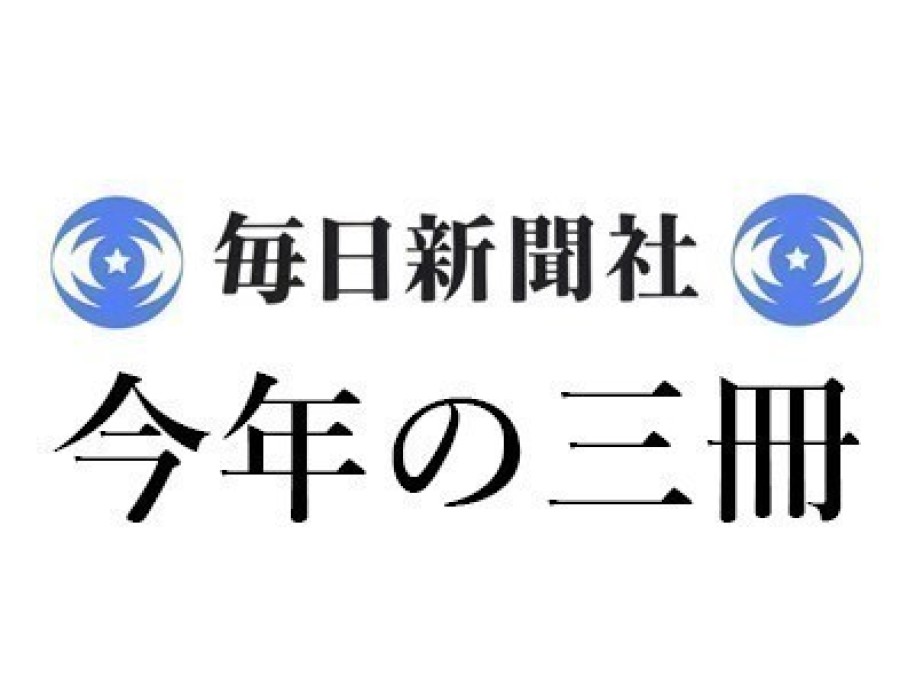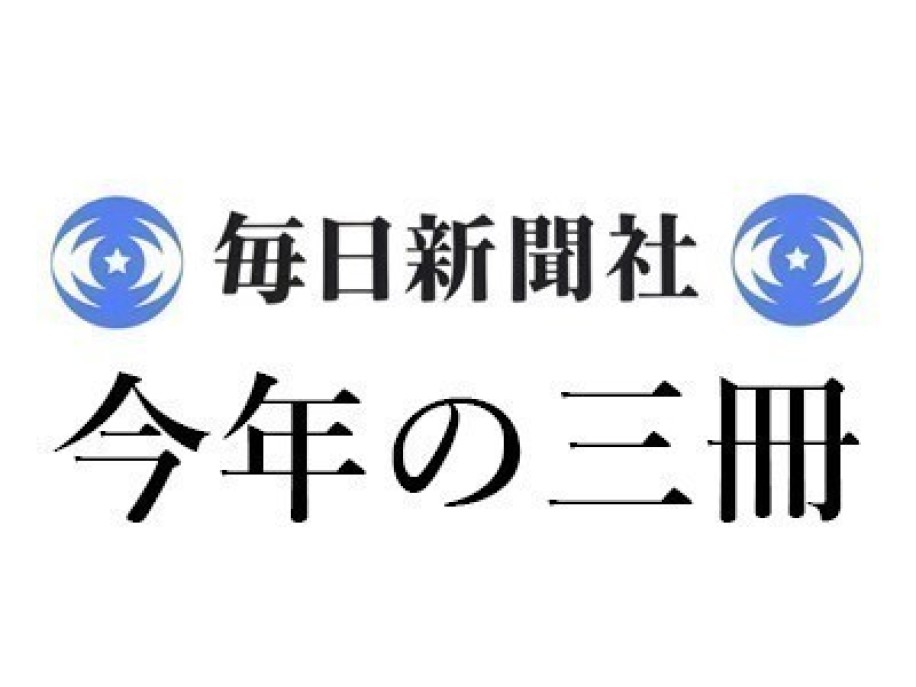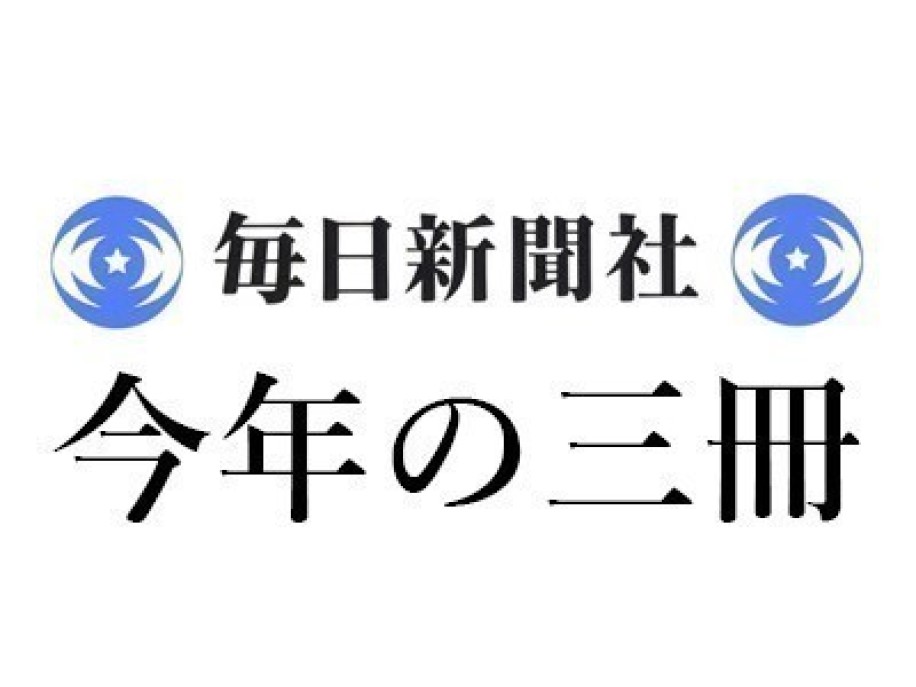書評
『気候と人間の歴史・入門 【中世から現代まで】』(藤原書店)
歴史的事件に気象が与えた影響を探る
地球温暖化の問題が大きな現代的課題となっているが、歴史的にこの問題についてどう考えたらよいのだろうか。この点について、歴史と気候の関係を追究してきたフランスのアナール派の著者が、三十二の質問に答える形でわかりやすく記したのが『気候と人間の歴史・入門』である。
まずは気候の歴史の研究法について幾つかの方法を提示する。樹木の年輪を介してその成長から調べる年輪年代学、次に葡萄の収穫日の研究、いかにもフランス人の研究らしい指標である。一七八九年から二〇〇〇年にかけてのブルゴーニュの葡萄の収穫日とパリの気温とは相関関係があり、高気温の時の葡萄は早期熟成で、冷涼期には収穫の遅延が起きているという。日本では桜の開花期がよく使われているが。
続いて干魃(かんばつ)や降雨の時に行われる祈願祭、これはキリスト教文化圏らしいところであり、そしてよく知られているのが氷河の研究や花粉の研究である。
一六五九年に温度計が利用できるようになってから、気候と歴史的事件との関係がよくわかるようになった。そこから歴史的事件に与えた気候の影響をよく知ることができるようになった。
そんなところから、気象条件がフランス革命の勃発に何らかの役割を果たしたのか、という質問に答える。「因果関係について語ることはよしましょう。それは単純化であり、滑稽でさえあります。」と前置きし、因果関係を性急に求めることを慎むとともに、かといって全く無関係だったのでもないとして、フランス革命にいたるまでの局面における気象の直接的、また間接的な影響を丹念に探っている。
最後の質問は、二〇〇七年夏の異常気象が歴史的にどう扱われるのかという現代と密接に関わる問題である。そこでは一三一四年から翌年の夏、一六九二年から翌年の夏、一七七四年の夏と比較し、それらの時期とは違って、現代では飢饉はもはや問題にはならなくとも、重大な変調の時として記憶されるであろうとしている。そういえばこの年を経て世界的に気候温暖化が極めて重視されるようになったのである。
では日本での気候と歴史的事件との関係はどうだろうか。たとえば戦国乱世に気候は関係していようか。それに相当する一五七〇年から一六三〇年は超小氷期と称される特別な寒冷期であった。ヨーロッパの魔女狩りもこの超小氷期のとばっちりを受けた。一六二六年の南ドイツ、春の霜によって葡萄の収穫がほとんど無かった。それがかつてこの地方で経験しなかった魔女狩りを引き起こしたという。
そもそも日本列島に定住社会が始まったのは気候の温暖化にともなうものであった。玉田芳英編『列島文化のはじまり』をみると、「約一万三〇〇〇年前、温暖化とともに最終氷期は終わりを告げ完新世(後氷期)がはじまった。縄文時代の幕開けである」と指摘している。
この気候の温暖化は列島各地に先駆けて南九州に最初に影響を与え、落葉広葉樹の豊かな森を育んだ。縄文時代はまさに気候の温暖化と連動して推移することになる。大規模集落と貝塚の出現がそれを端的に示している。
本書は、史跡を通じて日本の歴史を語ろうというシリーズの第一冊で、これまでの通史が史跡に僅(わず)かに触れ、例示するのとは違って、史跡の側から歴史を描くもので、史跡が生き生きとして語られているのが特徴である。我々の身近に存在する史跡の歴史的な位置づけがはっきり記されているだけでなく、史跡を通じたその時代の見取り図が描かれている。
そうした史跡の年代を探る方法として用いられているのが年輪年代測定法である。樹木の年輪の変化曲線を調べ、いつの時期のものかを探る方法であるが、これを通じて気候と史跡との関係もわかるという意味でも重要である。本書はこの方法や最新の炭素14年代測定法の紹介をしつつ、その有効性と問題点とを記している。
気候と歴史・人間との関係は密接であることは疑いないが、「しかし短絡的な理由づけは慎みましょう」というラデュリの指摘を重く受け止めつつ、今後とも丹念に探ってゆく必要がある。
今、温暖化という言葉に踊らされている面はなくはないのだが、着実に温暖化が進んでいるという現実を直視してゆく必要も痛感させられた。
ALL REVIEWSをフォローする