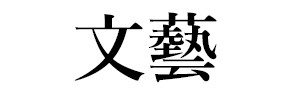書評
『転形期と思考』(講談社)
この評論集は批評といえるかどうかの瀬戸際にあると思うが、そのことよりも、文学を成り立たせ有効なものとするために必要な核を、他の多くの批評や小説と違って持っていることのほうが、私には重要である。その核とは「卑しさというエレメント」である。
山城は、中野重治の「斉藤茂吉ノオト」「ノオト九」と「広重」に、その「卑しさというエレメント」という核を読む。そしてその読みを論理的に説明していくため、中野のテクストの言葉の向いている方向をねじ曲げたり文脈を違えたりしないよう、中野の書いた言葉の引用を慎重に重ねていく。このような書き方の倫理にこそ批評が現れることは、著者のデビュー作である「小林秀雄のクリティカル・ポイント」に表明されているとおりであって、レトリックの問題などではない。
だがいくら厳密に言葉を引用し、様々な角度からアプローチしようとしても、山城が「広重」に読んでいるはずの核には届かない。その結果、第五章中ほどで、山城は追いつめられるようにして飛躍する。「広重」の語り手「私」には、広重の絵の雨や湖水が「全体としていかにも重たくものさびしい。そう思ってばらばら見ると、どれもこれも心に沁みるように思えてくる」。その理由を山城は「広重のこの水が重くものさびしいのは、死というのもによって翳っているからではないだろうか。卑しさの底で「死にたい」という無意識の衝動に思いがけず触れた「私」の心が広重の雨や湖にあの重さ・ものさびしさを見いだしたのではないか。[…]卑しさを余儀なくされる「どたん場」で、死を密かに待ち望んでいる自分を見いだしはしなかっただろうか」と説明する。そして、「私」は「死にたい」のに「死ねない」という「不可解な堅い底」に突き当たっており、それこそが生きるのに不可避かつ不可欠な「卑しさというエレメント」である、と説く。さらに、「いかにも重たくものさびしい」水の底には「何ともいえぬ暖かいもの」があり、そのような人々の「おとなしさ」が、「たたかうこと」、その主体となることに結びつくと読んでいく。
中野のテクストとこの認識の間には明らかに飛躍がある。このような認識が出てくる根拠は説明しきれず、恣意的にさえ見える。だがこれは恣意などではまったくなく、そのような恣意性の暴力で中野の書いた言葉を傷つけないよう、他の言葉を引き寄せることを厳しく制限し、モノとしての中野の言葉だけで核をかたどろうとしたぎりぎりの試みが潰えた果てに、この認識へ飛び降りているのである。そのことがそれまで忠実にかたどってきた中野のテクストを犯すかもしれないのに飛ばざるをえないという、いわば「どたん場」からの不可避・不可欠な卑しい飛躍である。その距離は、中野が「どたん場」の自分にある「卑しさというエレメント」を見なければならなかった落差と等しいとさえ感じさせる。
山城は、「卑しさというエレメントを呼吸して」、それを「社会秩序に向かって投げかえ」すことなしでは、文学が「たたかうこと」、世界を本当に変えることにつながりはしないと言おうとする。「清らかな」保田與重郎には致命的に「卑しさというエレメント」が欠けていたと批判するのも、文学史上の問題ではなく、いまの日本における言説を批判しているのだ。これは私にとって必要な本であり、今後何度でも読み直すことだろう。
山城は、中野重治の「斉藤茂吉ノオト」「ノオト九」と「広重」に、その「卑しさというエレメント」という核を読む。そしてその読みを論理的に説明していくため、中野のテクストの言葉の向いている方向をねじ曲げたり文脈を違えたりしないよう、中野の書いた言葉の引用を慎重に重ねていく。このような書き方の倫理にこそ批評が現れることは、著者のデビュー作である「小林秀雄のクリティカル・ポイント」に表明されているとおりであって、レトリックの問題などではない。
だがいくら厳密に言葉を引用し、様々な角度からアプローチしようとしても、山城が「広重」に読んでいるはずの核には届かない。その結果、第五章中ほどで、山城は追いつめられるようにして飛躍する。「広重」の語り手「私」には、広重の絵の雨や湖水が「全体としていかにも重たくものさびしい。そう思ってばらばら見ると、どれもこれも心に沁みるように思えてくる」。その理由を山城は「広重のこの水が重くものさびしいのは、死というのもによって翳っているからではないだろうか。卑しさの底で「死にたい」という無意識の衝動に思いがけず触れた「私」の心が広重の雨や湖にあの重さ・ものさびしさを見いだしたのではないか。[…]卑しさを余儀なくされる「どたん場」で、死を密かに待ち望んでいる自分を見いだしはしなかっただろうか」と説明する。そして、「私」は「死にたい」のに「死ねない」という「不可解な堅い底」に突き当たっており、それこそが生きるのに不可避かつ不可欠な「卑しさというエレメント」である、と説く。さらに、「いかにも重たくものさびしい」水の底には「何ともいえぬ暖かいもの」があり、そのような人々の「おとなしさ」が、「たたかうこと」、その主体となることに結びつくと読んでいく。
中野のテクストとこの認識の間には明らかに飛躍がある。このような認識が出てくる根拠は説明しきれず、恣意的にさえ見える。だがこれは恣意などではまったくなく、そのような恣意性の暴力で中野の書いた言葉を傷つけないよう、他の言葉を引き寄せることを厳しく制限し、モノとしての中野の言葉だけで核をかたどろうとしたぎりぎりの試みが潰えた果てに、この認識へ飛び降りているのである。そのことがそれまで忠実にかたどってきた中野のテクストを犯すかもしれないのに飛ばざるをえないという、いわば「どたん場」からの不可避・不可欠な卑しい飛躍である。その距離は、中野が「どたん場」の自分にある「卑しさというエレメント」を見なければならなかった落差と等しいとさえ感じさせる。
山城は、「卑しさというエレメントを呼吸して」、それを「社会秩序に向かって投げかえ」すことなしでは、文学が「たたかうこと」、世界を本当に変えることにつながりはしないと言おうとする。「清らかな」保田與重郎には致命的に「卑しさというエレメント」が欠けていたと批判するのも、文学史上の問題ではなく、いまの日本における言説を批判しているのだ。これは私にとって必要な本であり、今後何度でも読み直すことだろう。
ALL REVIEWSをフォローする