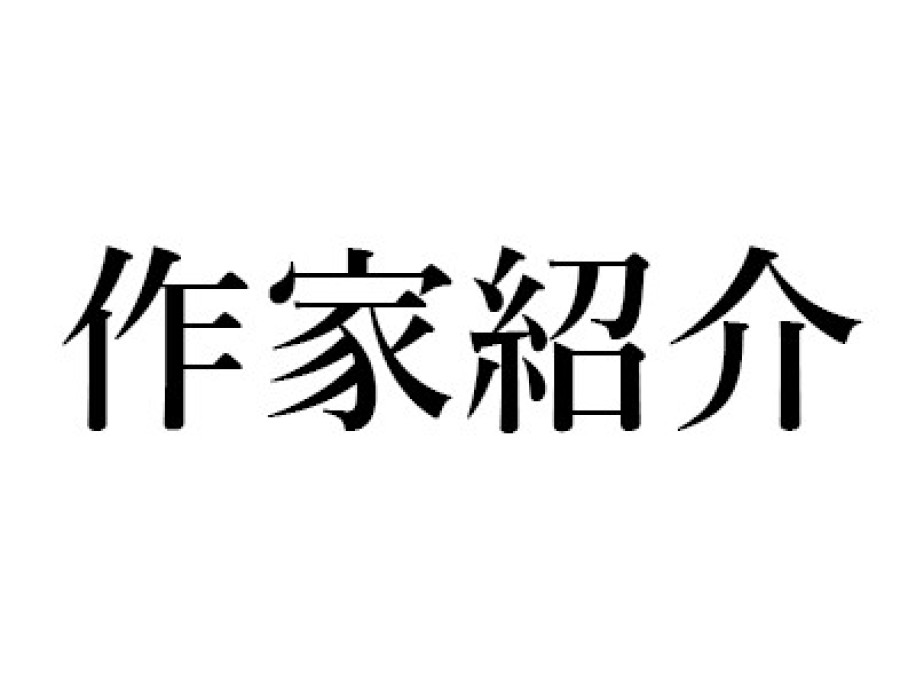書評
『金毘羅』(河出書房新社)
「純文学」と「エンターテイメント」の違いは何ですか、とは、いまだによく聞かれる質問だけれど、私は「そんなのは便宜的な分類で、境界はない」とは思っていない。ただ、私自身はその言葉を使わず、「文学」と「読み物」という分け方をしている。
その違いは、病気でたとえて言うと、根本的治療と対症療法のような関係にある。「文学」は、読んでいる人が自分では気づかない心の奥底に働きかけ、その人の無意識を変えたり、場合によっては壊したりする。ごく微妙にだけど、人格を変えうる。それに対して「読み物」は、当座の苦痛や絶望や気がかりを和らげて、人心地つけてくれるもの。
「文学」は必ずしも読みやすくない。でも、それでいいのだ。即効性のあるものではないから。「純文学の極道」(帯より)笙野頼子が放った極私小説『金毘羅』も、片手間に読めるような小説ではない。全身全霊で取り組むことが要求されるし、そのあげくには読んだほうも傷だらけになって精根尽き果てる。自分が「こんぴら」であることに覚醒した、作者に限りなく近い「私」がその半生を語る一代記は、要約を拒む。「金毘羅」である人生とはどういうことか、「金毘羅」に目覚めると何が変わるのか、それを必死で読み取ろうと努めていくと、最後にとてつもない解放感が一瞬だけ訪れる。この得も言われぬ救いの一瞬を、文学以外で感じることは難しい。
斎藤貴男の『国家に隷従せず』は、小説ではないから「読み物」とは違うけれど、対症療法を目指した本である。イラク派兵を始めとして、監視社会化、情念の支配など、日本社会がファシズムへ傾斜していると感じる著者は、本当は根本的治療が必要な事態なのに、そこから手をつけていては間に合わない、だから多少乱暴になろうとも対症療法として言葉を繰り出していくという決意でこの本を世に出したと言える。その決意に共感。
どちらも、替えのきかない「私」を拠り所にした本である。
その違いは、病気でたとえて言うと、根本的治療と対症療法のような関係にある。「文学」は、読んでいる人が自分では気づかない心の奥底に働きかけ、その人の無意識を変えたり、場合によっては壊したりする。ごく微妙にだけど、人格を変えうる。それに対して「読み物」は、当座の苦痛や絶望や気がかりを和らげて、人心地つけてくれるもの。
「文学」は必ずしも読みやすくない。でも、それでいいのだ。即効性のあるものではないから。「純文学の極道」(帯より)笙野頼子が放った極私小説『金毘羅』も、片手間に読めるような小説ではない。全身全霊で取り組むことが要求されるし、そのあげくには読んだほうも傷だらけになって精根尽き果てる。自分が「こんぴら」であることに覚醒した、作者に限りなく近い「私」がその半生を語る一代記は、要約を拒む。「金毘羅」である人生とはどういうことか、「金毘羅」に目覚めると何が変わるのか、それを必死で読み取ろうと努めていくと、最後にとてつもない解放感が一瞬だけ訪れる。この得も言われぬ救いの一瞬を、文学以外で感じることは難しい。
斎藤貴男の『国家に隷従せず』は、小説ではないから「読み物」とは違うけれど、対症療法を目指した本である。イラク派兵を始めとして、監視社会化、情念の支配など、日本社会がファシズムへ傾斜していると感じる著者は、本当は根本的治療が必要な事態なのに、そこから手をつけていては間に合わない、だから多少乱暴になろうとも対症療法として言葉を繰り出していくという決意でこの本を世に出したと言える。その決意に共感。
どちらも、替えのきかない「私」を拠り所にした本である。
ALL REVIEWSをフォローする