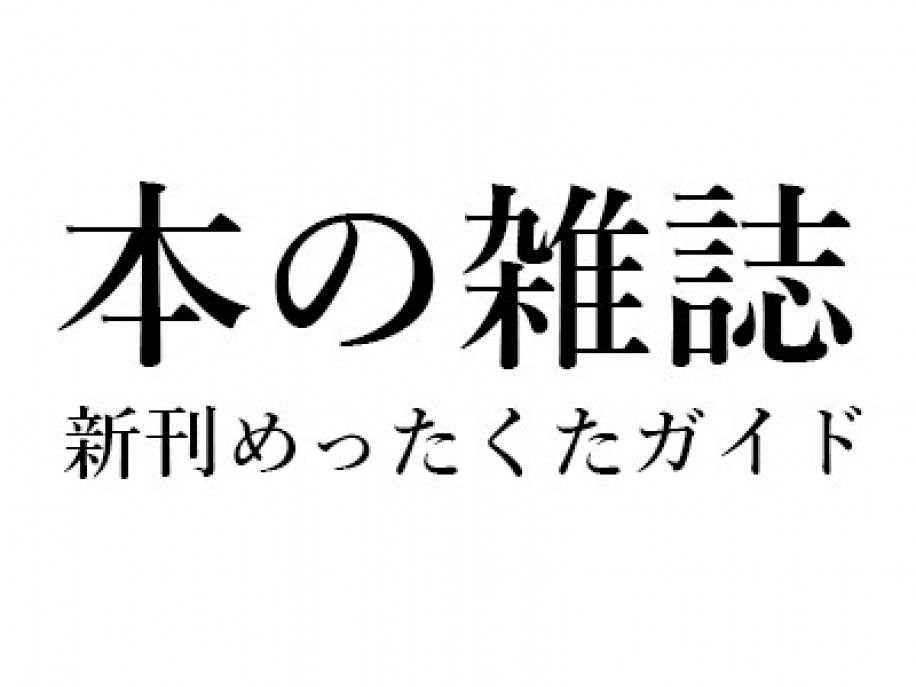書評
『日本小説批評の起源』(河出書房新社)
批評の起死回生
我々の“近代小説”の起源に、到来の『水滸伝』を置くという意表を衝く展開である。小説の起源はまた批評の起源である。無論そう簡単にすっきり納得の行くものではないが、270頁(ページ)余のこの本を読み終えた今、極上の探偵小説を味わった気分だ。ここで著者=探偵が採用した推理法は、系譜学的アプローチだ。ニーチェが、道徳上の用語(「良い」「悪い」)を歴史的・思想史的に、つまり「現在」という特権的な視点から裁くように記述するのではなく、「系譜学=Genealogy」(語源的意味は、ものごとの由来、出現譚)的に追究して、道徳観念の生々とした古層を掘り出したように。言わば、歴史の絨毯の中にひそめられた横糸を明らかにする(ベンヤミン)。
四書五経の往古より、作品の言葉の連なりの中で注目に値する箇所を批(ゆびさ)し、点を打ち(批点)、その下に小文字で注釈=意義を入れる(評点)。漢文伝統の「批」「評」を、中国における最初にして最高の白話(散文)長篇小説『水滸伝』に、明末清初の文芸批評家金聖嘆が施した。批点は全文の八割に打たれ、評点の総文字数は本文とほぼ匹敵する。つまり、「小説」の原理と「批評」の原義とが交叉して、読者は「物語」を読みながら同時に「批評」を読む。新しい小説、新しい読者の登場だ。原「水滸伝」は12世紀末から13世紀に成立したとされるが、明代に入って書の型に整えられ、120回本、100回本、70回本があり、70回本は金聖嘆による改作で、梁山泊に「好漢」全員が結集するまでを描き、その後の展開はつまらぬと腰斬(ようざん)された。しかし、この70回本こそ中国で最大の流布本であり、これが江戸期日本の散文フィクションの風土に入って、「読本(よみほん)」のジャンルが成立、我々の誰もが『水滸伝』70回本のように書きたいと願った。滝沢馬琴は、『水滸伝』の中で金聖嘆と出会うことで『八犬伝』の作者となり、自作中に施した注釈(批評)によって本朝最初の小説批評家となった。
その消息を説く探偵の筆致(批評)は非の打ちどころがない。
ここで、意外な世界が呼び出される。『古事記』である。『日本書紀』の影に隠れて、誰にも読まれず読めもしなかった『古事記』に、上代のものに近いと思しき日本語の訓読(ヨミガナ)を与えたのが本居宣長である。太安万侶の「文」(漢文、変体漢文)があり、その背後に稗田阿礼の「声」が想定され、更に阿礼が口誦(こうしょう)化した「古書」には古事(ふること)・古言(ふること)=まことが息づいている。初めに言葉(コトノハ)があった、と「旧約」の世界のように宣長は考え、そこに到るため、真の『水滸伝』のテクストを創出し、テクストそのものとなった金聖嘆と同様、彼は『古事記』本文に批点を打ち、評点を重ね、批評の限りを尽くして、神ながらの「声(ヨミガナ)」を実現する。
だが、この「声」が曲者だ。下って、この「声」なるモノが、馬琴らが切り拓いた近代批評の筋を抹消してゆく……。
起源は創出されると同時に隠蔽される。つまり犯人は隠れる。探偵が登場し、犯人を暴く。しかし探偵はまた、犯人が生み出した者、その息子でもあるのだ……。
批評の起源とは、常に「現在」である。そういうことに気付かせてくれる卓抜な書だ。
ALL REVIEWSをフォローする