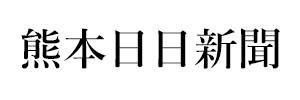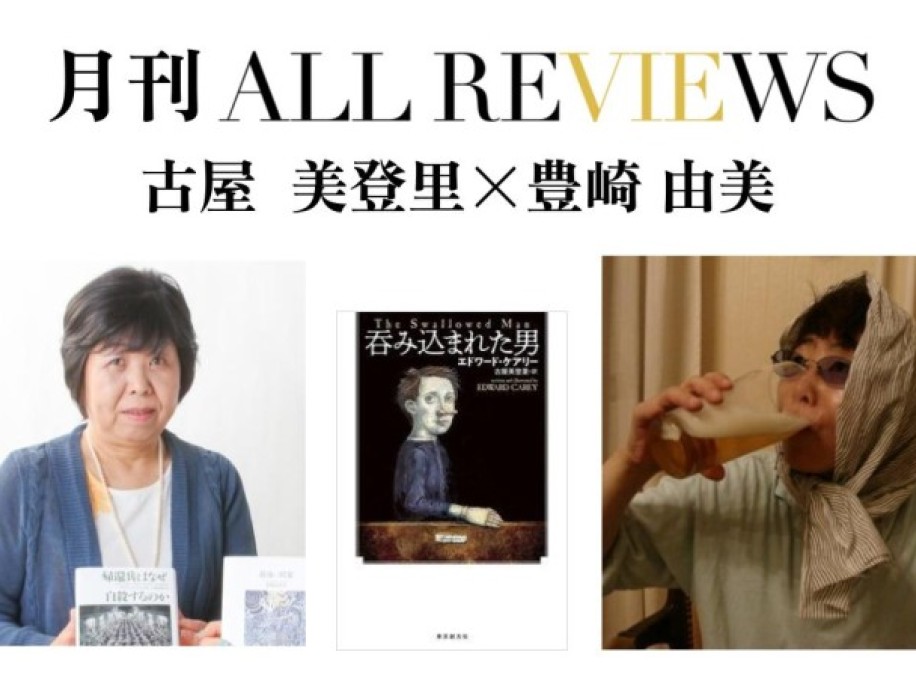書評
『アルヴァとイルヴァ』(文藝春秋)
就職がなかなか決まらない男子学生を追うドキュメンタリー番組を見た。悩んだ末に就職斡旋会社の面接を受け、「もっと笑顔で!」「はきはきしなきゃ」と日夜厳しい指導を受ける彼が、自宅で鏡を見ながら笑顔の練習をしている様子に胸が痛んだ。面接で笑顔が大事なのはわかる。はきはきとした素早い受け答えが求められるのもわかる。作り笑顔はできなくても心の温かい子や、よく考えた末に発言をする思慮深い子の良さを、ほんの一〇分ほどの面接で見極めることが不可能に近いこともわかる。だから『面接の達人』のようなマニュアル本が売れ、学生たちは自分とは少し違う明るく積極的な人格を演じ、面接官もまたその演技を評価するしかないのだろう(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2004年)。でも……。明るかったり、行動的だったり、てきぱきしてたりといった“陽”の要素ばかりが人間の良さだとは、やっぱり思いたくない。世界は時に、見過ごしてしまうような小さなものや、“陰”とされている何かによって癒されたり、修復されたり、光り輝いたりするのだから。
エドワード・ケアリーという作家の小説を読むと、その意を強くする。いささか反社会的な奇人変人ばかりが棲みついている館を舞台に、人生の痛苦と小さな歓び、傷ついた魂の癒しと再生の物語を、読む者の習慣に曇らされた目を浄化する「汚いはきれい、きれいは汚い」式のトリッキーな語り口で描いたデビュー作『望楼館追想』に続いて放つ、この『アルヴァとイルヴァ』もまた、読者にありていの価値観の放擲(ほうてき)を迫る小説なのだ。
主人公は、それなりの歴史を持つ小さな町エントラーラに生まれ育った双子の姉妹アルヴァとイルヴァ。ほんの一時でも離れたら死んでしまうと思い込むほど強い絆で結ばれた二人の楽しみは、プラスティック粘土による模型制作。アルヴァイルヴァーラという架空の町を作り、二人だけの夢想に耽っていた子供時代も、しかし、やがて終わりを告げる。思春期を迎え異性に関心を抱くようになった姉のアルヴァが“ネヴァーランド”を飛び出し、広い世界に憧れ自由奔放にふるまうにつれ、外界を恐れて部屋に引きこもるようになる妹のイルヴァ。しかし、ある出来事をきっかけにアルヴァは再びイルヴァとの合体を果たす。以来、常軌を逸した情熱を傾けてエントラーラの模型を作り続ける二人。やがて、町に大きな災厄がふりかかり――。
『望楼館追想』同様、この小説にも世界のありようにうまく適応できない、変わった人物が数多く登場する。アルヴァとイルヴァを外に出したがらない母親、切手を偏愛しその愛ゆえに早死にしてしまった双子の父親、マッチ棒細工を愛する郵便局長の祖父、口を利かない少年、町の問題児として悪名高きアルヴァのボーイフレンド、各国のTシャツを集めるトラック運転手、ゴシップ好きの仕立屋の老女、ピッグという名の刺青師などなど。もちろん、彼らの筆頭にして掉尾(ちょうび)を飾る変わり者がアルヴァとイルヴァであることは間違いない。
世界中を旅することを夢み、ついには自分の体に世界地図の刺青を入れてしまうアルヴァと、姉と二人だけの世界にいたいと願っている内向的なイルヴァ。この小説は、まず、彼女ら類(たぐ)いまれなキャラクターの成長をたどる奇妙な味のビルドゥングスロマンとして読まれるべきだろう。そして、二人の魂の遍歴を追うことが、すなわちエントラーラの歴史をたどる足跡となり、その小さな町で起こる大きな悲劇と小さな奇跡に立ち会うという特権的かつ特別な体験へとつながっていくのだ。
アルヴァとイルヴァが作った町の模型が、どんな形で大きな悲劇に傷ついた人々の心を癒すのか。〈小さなものは人を感動させる〉ことを描いて共感を生むこの小説を読むと、世界が美しかったり均整のとれたものだけで成り立っているのではないことがしみじみと了解される。とるに足らない小さなものや、一見役に立ちそうにない人や、明るさとは対極にあるような性質が、時にプラスの要素に転じることだってあるのだ。面接でうまく笑顔が作れなくたって大丈夫。世界はそんな小さなあなたやわたしが存在するという多様性によって豊かさを獲得するのだから。
【この書評が収録されている書籍】
エドワード・ケアリーという作家の小説を読むと、その意を強くする。いささか反社会的な奇人変人ばかりが棲みついている館を舞台に、人生の痛苦と小さな歓び、傷ついた魂の癒しと再生の物語を、読む者の習慣に曇らされた目を浄化する「汚いはきれい、きれいは汚い」式のトリッキーな語り口で描いたデビュー作『望楼館追想』に続いて放つ、この『アルヴァとイルヴァ』もまた、読者にありていの価値観の放擲(ほうてき)を迫る小説なのだ。
主人公は、それなりの歴史を持つ小さな町エントラーラに生まれ育った双子の姉妹アルヴァとイルヴァ。ほんの一時でも離れたら死んでしまうと思い込むほど強い絆で結ばれた二人の楽しみは、プラスティック粘土による模型制作。アルヴァイルヴァーラという架空の町を作り、二人だけの夢想に耽っていた子供時代も、しかし、やがて終わりを告げる。思春期を迎え異性に関心を抱くようになった姉のアルヴァが“ネヴァーランド”を飛び出し、広い世界に憧れ自由奔放にふるまうにつれ、外界を恐れて部屋に引きこもるようになる妹のイルヴァ。しかし、ある出来事をきっかけにアルヴァは再びイルヴァとの合体を果たす。以来、常軌を逸した情熱を傾けてエントラーラの模型を作り続ける二人。やがて、町に大きな災厄がふりかかり――。
『望楼館追想』同様、この小説にも世界のありようにうまく適応できない、変わった人物が数多く登場する。アルヴァとイルヴァを外に出したがらない母親、切手を偏愛しその愛ゆえに早死にしてしまった双子の父親、マッチ棒細工を愛する郵便局長の祖父、口を利かない少年、町の問題児として悪名高きアルヴァのボーイフレンド、各国のTシャツを集めるトラック運転手、ゴシップ好きの仕立屋の老女、ピッグという名の刺青師などなど。もちろん、彼らの筆頭にして掉尾(ちょうび)を飾る変わり者がアルヴァとイルヴァであることは間違いない。
世界中を旅することを夢み、ついには自分の体に世界地図の刺青を入れてしまうアルヴァと、姉と二人だけの世界にいたいと願っている内向的なイルヴァ。この小説は、まず、彼女ら類(たぐ)いまれなキャラクターの成長をたどる奇妙な味のビルドゥングスロマンとして読まれるべきだろう。そして、二人の魂の遍歴を追うことが、すなわちエントラーラの歴史をたどる足跡となり、その小さな町で起こる大きな悲劇と小さな奇跡に立ち会うという特権的かつ特別な体験へとつながっていくのだ。
アルヴァとイルヴァが作った町の模型が、どんな形で大きな悲劇に傷ついた人々の心を癒すのか。〈小さなものは人を感動させる〉ことを描いて共感を生むこの小説を読むと、世界が美しかったり均整のとれたものだけで成り立っているのではないことがしみじみと了解される。とるに足らない小さなものや、一見役に立ちそうにない人や、明るさとは対極にあるような性質が、時にプラスの要素に転じることだってあるのだ。面接でうまく笑顔が作れなくたって大丈夫。世界はそんな小さなあなたやわたしが存在するという多様性によって豊かさを獲得するのだから。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする