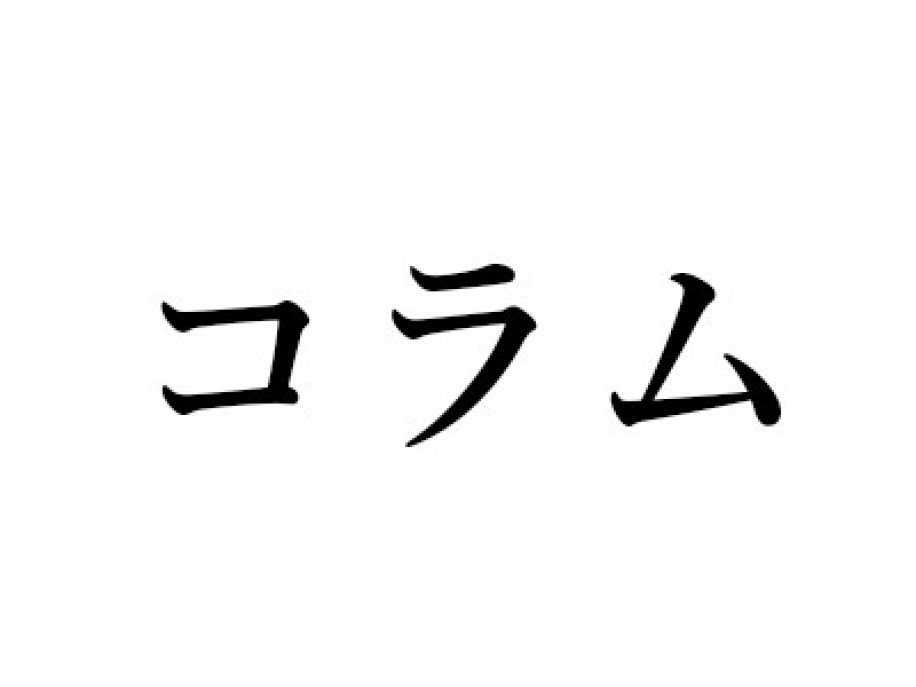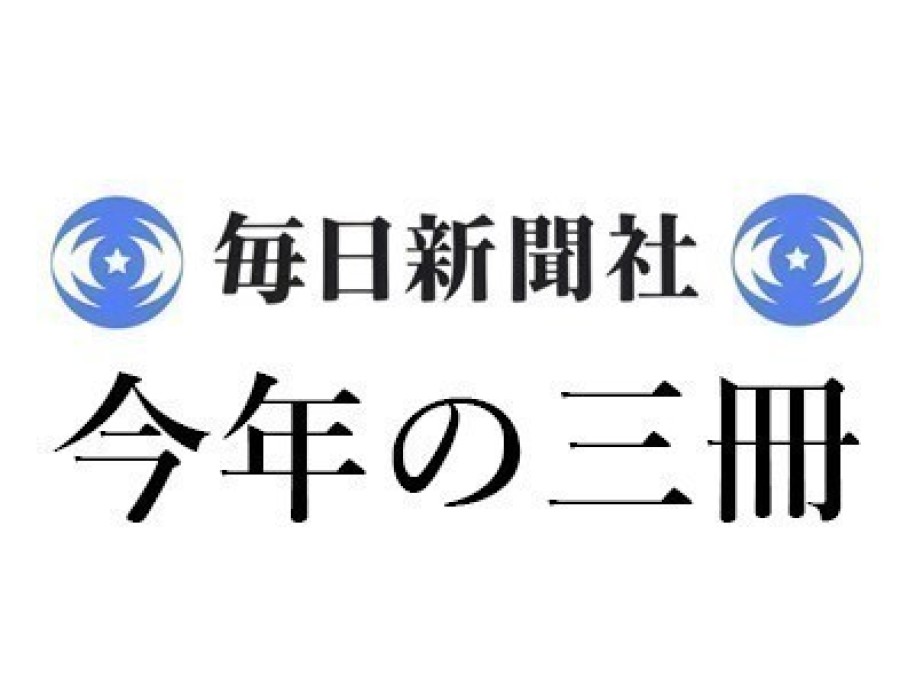書評
『光琳の櫛』(新潮社)
黒髪のゆくすえ
古美術品に魅入られた収集家を主人公にした小説は読みごたえがあるはずと思うのに、これという作品にめぐりあえない。運がないのか、それとも実際に秀作がないのか。たやすくは主人公に立てられないだろう。調べて間に合うならともかく、書く側にはそれこそ収集家自身をしのぐほどの蓄積が、付け焼き刃ではない知識、見識、眼力が要求される。
あなたにとっての日本の国宝を挙げよ、というアンケートに、「小林秀雄の脳髄と青山二郎の目」という回答があったのを読んだ覚えがある。主人公が普通の生活という場を動くのでなくては、小説は成り立たない。国宝級ほどではなくても、ある眼力を備えた目が生息する場をどう設けたらいいか。尋常ではない情熱、欲望、執心とまっこうから取り組んで、読者の共感を得るにはどんな工夫をしたらいいか。早い話、こうした肝心な点を解決しないでは小説はこそとも動きだすまい。
まともには歯が立たないから、収集家の生態を外側から攻めて、投機まがいの売買、掘りだしもの、真贋騒動を種にした奇談・珍談で間に合わせる。殺人事件の主役や脇役を務めさせたりもする。苦肉の策というよりも悪い冗談というべきだ。
あきらめかけてそんなことを思っていたのだが、芝木好子の『光琳の櫛』にめぐりあって年来の欲求不満は解消された。収集願望のおもむくままに過激に走って、やがてやつれはてる、そんな執念のすさまじさの一部始終をみごとに描ききっているのだ。収集家が女というところがまたいい。一九七九年の出版だから、二十年近くも前にとっくに秀作は書かれていた。
ここにはむろん、あざとい殺人事件も投機の一喜一憂もない。収集品の図録作りという何の奇もないプロットが置かれて、物語はその一線を動くだけ。
黒髪の美しい四十歳そこそこのヒロイン園(その)は赤坂で小ていな料亭雪国を営み、古い櫛や笄(こうがい)の収集に情熱を注いでいる。時代はオイル・ショック後の不況期。物語の時間枠は、園の収集品を見た大学の美術史の教師高垣が図録作りをすすめてから、出来上がった図録を園が高垣の伯母仲子に見せにゆくまで。その間に園と高垣は男と女の仲になり、出来上がると同時のように哀切な別れが来る。
一篇の眼目は古櫛と黒髪の対比につきるだろう。園の高揚や悲哀が常のものではなく、一(ひと)調子も二(ふた)調子も高くかつ沈痛なのも、物語がある平仄(ひょうそく)を整えてパセティックに進むのも、朽ちつつある櫛と、生々しい黒髪の絶妙な取り合わせがあるからだ。古伊万里や茶道具の収集でこれほど艶(えん)なおもむきが出せるものかどうか。
じつはこの作品を手にしたのは、あなたがご執心の黒髪の物語ですよ、と七十代の懇意なご婦人に教えられたからだ。小説の末尾で、七十四歳の仲子が、
「あなたには髪に挿すものがあってお幸せね。櫛やかんざしは一生添って語りかけてくれますもの。今更言うのもおかしいけど、黒髪は良いわね。やはり女のいのちですねえ」
と白いもののまじる髪をかきあげながら園にいう場面にいたって、僕は教えてくれたご婦人の真意を悟った。
園はただひと言、「ありがとうございます」と返す。万感こめたことごとしい言葉と違って、あたりまえの、さらりとした挨拶にすべてを含める小説家の至難のわざが成就されている。黒髪が黒髪でなくなったときの、園の後日譚まで、たぶん含められている。
芝木好子六十五歳の作。彼女は作品中の仲子の年齢で亡くなっている。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする