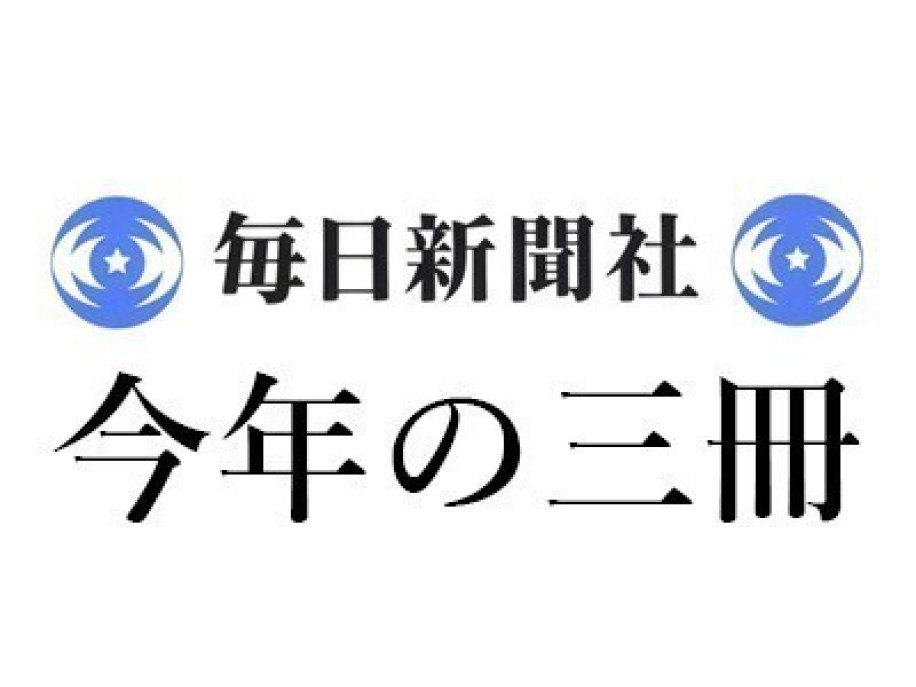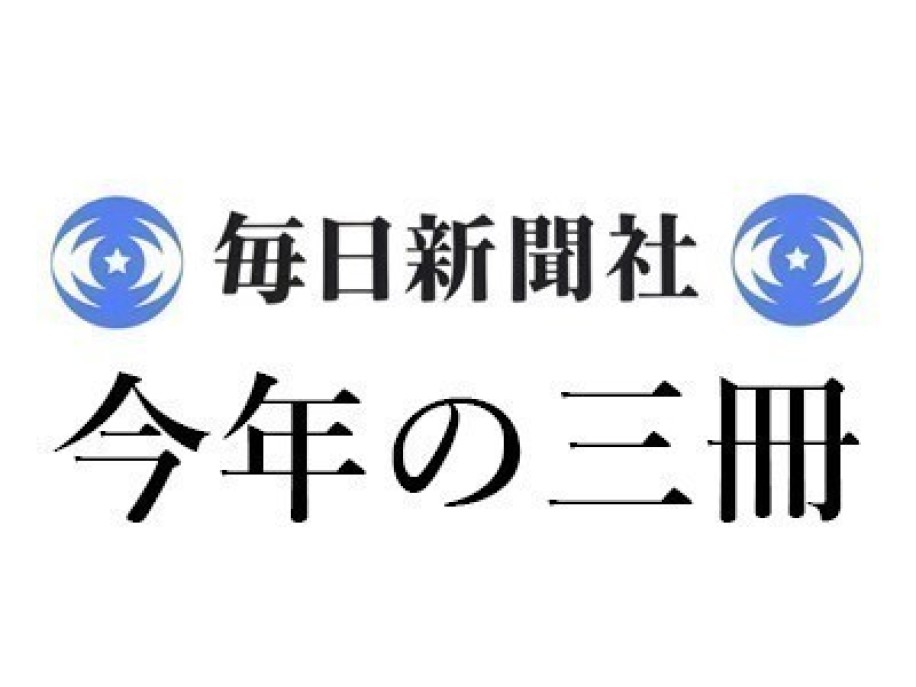書評
『修復的司法とは何か―応報から関係修復へ』(新泉社)
「失われたもの」の回復めざす「裁き」
考えてみれば奇妙なことだ。犯罪が発生する。犯人が検挙され、長い長い裁判にかけられる。が、もっともひどいダメージを受けた被害者そのひとには、その間ずっと、証人として以外の発言権がない。裁判中の経緯が逐一知らされるかというと、それもない。審理の全過程は、司法の専門家に委ねられたままだ。事件が起こるや、司法とメディアがそれを「犯罪」として、事件の当事者の手からもぎとってしまう。被害者の怖(おそ)れや怒りは孤立したまま増幅し、社会への不信どころか、ときに被害を受けた自己への強い非難さえ生まれ、やり場のない苦しみがそれとして肯定されることもなく、いよいよ深まってゆく。「被害には終わりがない」
現在の司法では、犯罪は<法>という国家秩序の侵害と位置づけられる。だから、罪の確定とそれに相応する合理的な刑罰の確定が中心に置かれ、問題のほんとうの解決、つまりは「失われたもの」の回復は、二次的にしか視野に入ってこない。被害者のニーズではなく、国家のニーズのなかで、審理は進められる。罰金も、だから国家に納められるのだ。
著者たちが一九七八年に開始した「加害者と被害者の和解プログラム」(VORP)は、犯罪もしくは紛争を見るときに、どの法律を侵したのか、どのような刑罰を受けるべきかという「応報的司法」の視点から、だれが傷つけられたのか、そのひとはいま何を必要としているのかという「修復的司法」の視点へと、「レンズを変える」(原題)ことを求めている。
著者たちの憂慮は、専門家にすべての審理過程を委ねることで、わたしたちはみずから問題を解決する能力を失ってしまったのではないかというところにある。被害者が不在であるだけでなく、加害者にも矯正の機会はあっても赦(ゆる)しの機会はないのだから。現在わが国でも試みられつつある裁判外紛争解決(ADR)の手法の源流にある、この修復的司法の古典は、「裁き」が何の解決であるべきかという、いちばん基本的な問いへとわたしたちを呼び戻す。
朝日新聞 2003年9月7日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする