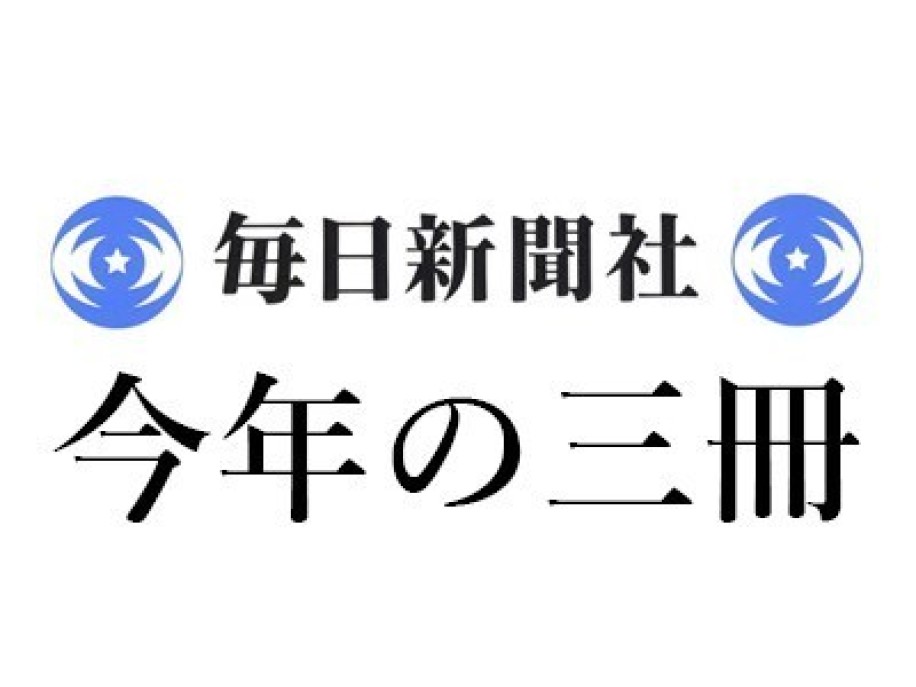書評
『エッセイとは何か』(法政大学出版局)
複雑な現実とらえる「思考の試み」
エッセイといえば、書店ではいつも「文学」の欄外に置かれ、小説や詩、評論以外の、作家による「軽い」書き物のごった煮といった扱いを受けている。そう、「随想」なのである。他方、ジョン・ロックの『人間知性論』やヒュームの『人間知性に関する哲学的探究』といった近世哲学の大著、その「論」や「探究」も「エッセイ」で、どうしてこんなに緻密(ちみつ)な推論の書がエッセイなのか、つねづね不思議に思ってきた。が、「エッセイ」という観念の歴史をひもといて、その謎を教えてくれる本は意外にない。そしてようやっとわたしたちのもとに届けられたのがこの本だ。エッセイは、なんとも多義的で、定義しようのないジャンルだというため息がまず漏れる。が、そこからは学者らしい検証が開始される。エッセイの原点であるモンテーニュの『エセー』にさかのぼって、「秤(はかり)」や「腕試し」といった原意から「思考を試しにかける」という精神を取りだす。そしてそれが英国でなぜ大きな展開をみせ、その後西欧社会にエッセイストという「個」群を作ったのかを探る。大衆読者層の登場にみられるような「専門性と公共性とを分離するような空間」の出現が、公理的な知と臆見(おっけん)(ドクサ)のすきまで思考する精神を必要としたというのだ。
揺れや逸脱やひっくり返し、思いつきや道草、そして不意の立ち止まり……。エッセイはそんな飄々(ひょうひょう)としたスタイルをとる。が、それは、現実を複雑なままに捉(とら)えること、つまりは「学校」的ともいえるきれいな論理、安易な断定や単純化に抵抗するからだ。
エッセイは、なによりも体系への欲望、全体性の誘惑に抵抗する。だから、複数の論理のせめぎあい、断片的な思考、執拗(しつよう)な吟味や懐疑、狩猟を思わす実験を、そして最後に、知ることの官能を愛(め)でる。「機敏で、日常的で、公的で、つねに現場にいて……」(サント=ブーヴ)という精神、それはほとんど<知>のエチカ(倫理)とも言うべきものだ。
クールな分析を貫いているのに、とても熱い本だった。
朝日新聞 2003年6月1日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする