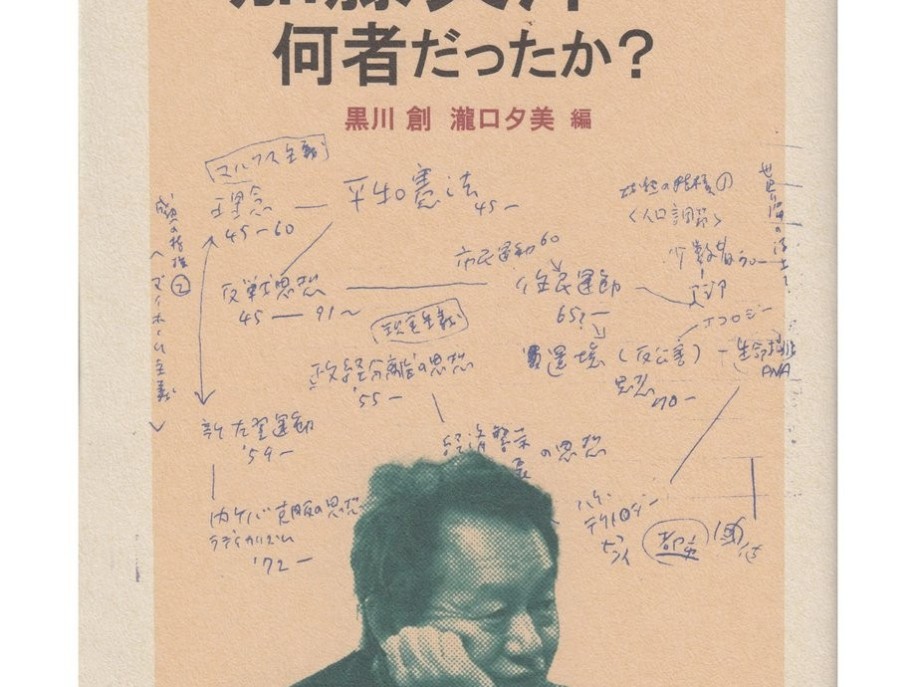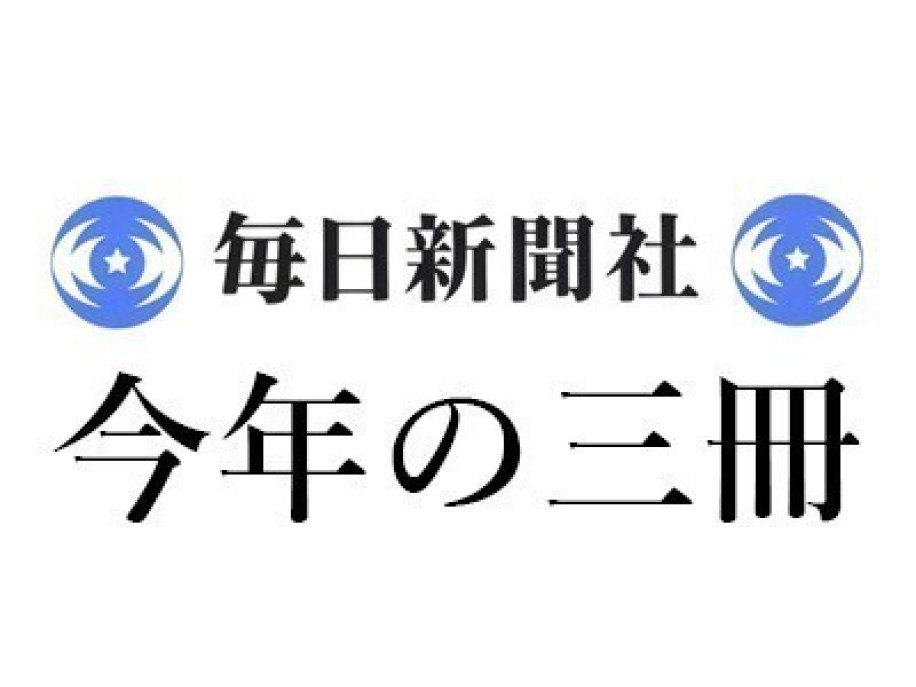書評
『日本人よ!』(新潮社)
オシムは、言葉のファンタジスタ
先日行われたサッカーのキリンカップ、日本代表対コロンビア代表の試合を、私は埼玉スタジアムで観戦した。久しぶりに日本のサッカーで心地よく酔えたのは、試合内容がよかったせいもあるが、オシム監督の『日本人よ!』を読んでいったおかげで、彼があの試合で何をしようとしたのか、大変明快にわかったからだ(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆年は2007年)。一例を挙げよう。スタメンの布陣を見て、多くのサッカーファンは驚いただろう。高原のワントップに、稲本をトップ下、その右に中村俊輔、左に遠藤。私も驚きつつ、ああ、これが『日本人よ!』でオシムが言っていたあのことかな、とあれこれ考えた。オシム監督は本書の中で、中村俊輔に何が足りないのか、どうすべきなのか、かなりはっきりと語っている。私はあの布陣を見て、オシムは俊輔の足りない部分を育てにかかっているのではないか、と思った。たぶん、俊輔だけでなく、遠藤や稲本についても。
それは何か? ここでは明かさない。知りたい人はぜひ、『日本人よ!』第二章を読んでください。私は「なるほどねえ」といたく感心した。
この本を読んでいる間、ひたすら興奮しっぱなしだった。私は小説家であり、小説を読むことが何よりも好きなわけだが、オシム監督の言葉を読んでいる間の興奮は、好きな小説を読んでいるときの興奮と似ているのだ。
どういうことか?
例えばJリーグについて。オシム監督が世界に通用するサッカーを実践しようとしているチームとして挙げるのは、ガンバ、フロンターレ、ジェフ。ほんとそうだよなと思ってから、あれ、浦和レッズは? と気づく。むろん、言い忘れた、なんてことはありえない。
ではなぜ浦和を外したのだろう、と考えながら読み進める。やがて、Jリーグも世界の傾向と無縁ではなく、お金のために優勝にこだわるあまり、負けないことを最優先するチームも出てきている、というくだりが現れる。これがひょっとして浦和のこと? と考え、浦和の今のサッカーを思い返すと、否定できなくなってくる。
つまり、読み手、聞き手に考えさせるのだ。考えさせ、何が問題か、気づかせる。気づかせ、ではどうしたらいいか、とさらに考えさせる。
オシム監督の語りは、一事が万事、このような形で成り立っている。何を語っていないのか、なぜ矛盾したことを言うのか、どうして韜晦な言い回しを選ぶのか、それらを考えているうちに次第にオシム監督の頭の中が読めてくる。そう、「読むこと」が求められているのだ。だから、小説好きにはたまらない。
でもこれってサッカーそのものではないか、とも思うのだ。オシム監督は言葉でもサッカーをしている。スペースを空けるためにおとりの言葉を吐き、相手がつられたらそのスペースを突く。突かれた相手は危機に陥り、必死で対処しようと頭を働かせる。
オシム監督はこの本で、「代表メンバー選出の基準の一つは、頭のよさということだ」と何度も明言している。その頭のよさとは、ゲームの文脈を読み取る能力、ということだろう。それは、文章の行間や語られていないことを考えて読み取る能力と同じだ。
オシム監督は、サッカーという競技を知り尽くしている。だが、希有なのは、サッカーを言葉に変換する能力があることなのだ。サッカーを知り尽くしているという点では、ジーコだってオシムに負けないだろう。それは現役時代のプレーが証明している。けれど、ジーコにはそれを語る言葉がなかった。だから監督として選手を方向づけられなかった。
もうすぐ日本代表はアジアカップ本番に臨む。本書を読んでから観戦すると、そのサッカーが何倍にも豊かになって見えてくることを、私は請け合う。
ALL REVIEWSをフォローする