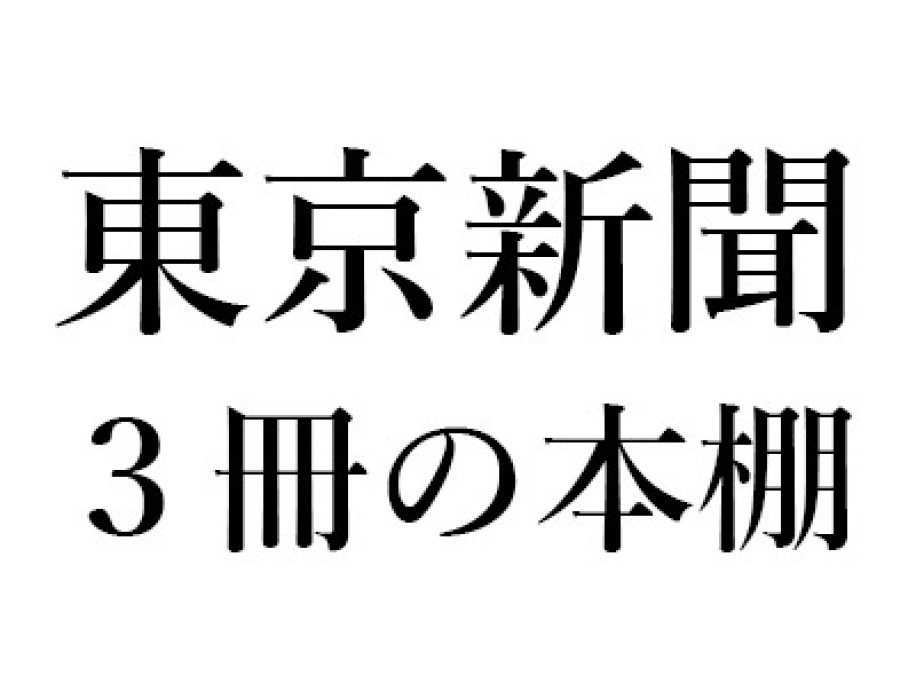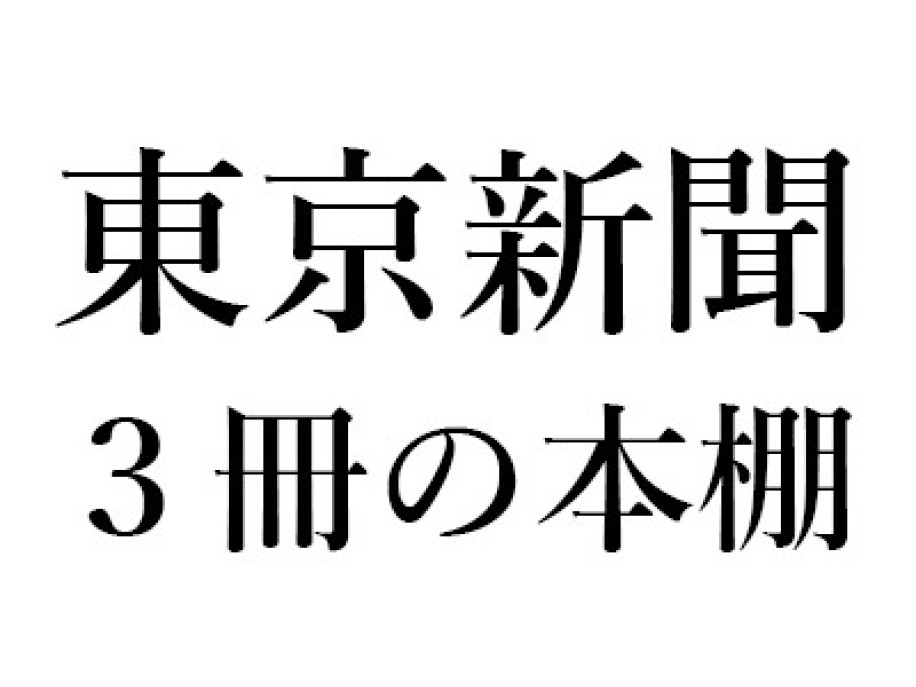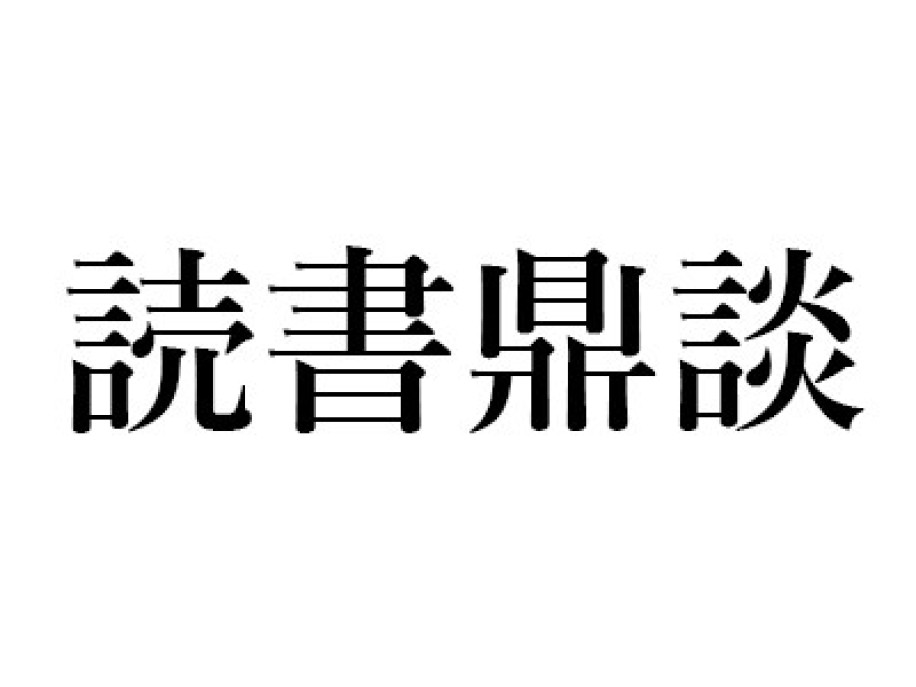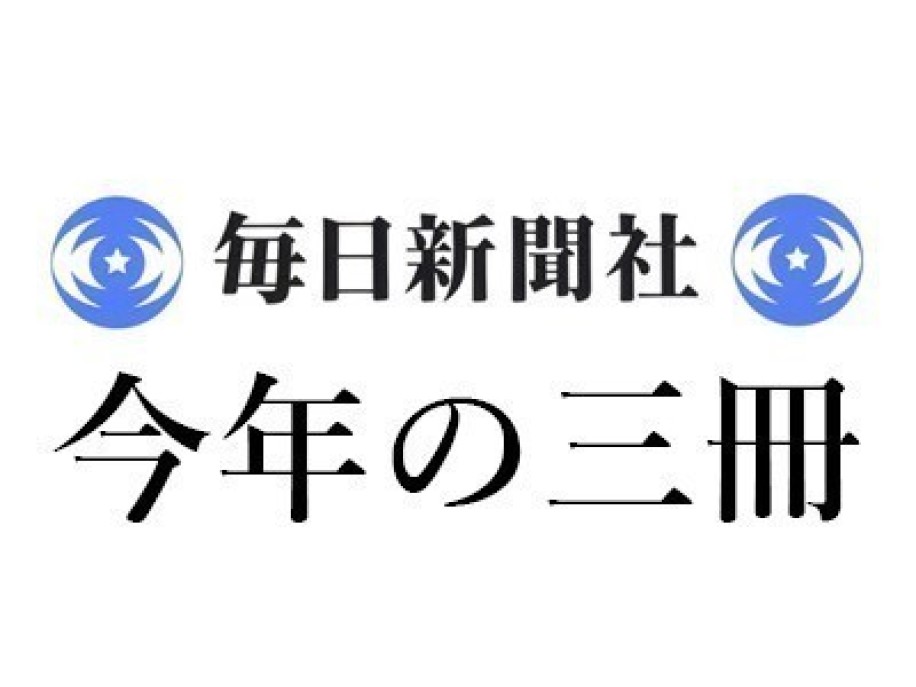書評
『砂の城』(新潮社)
美しいものは消えない
二〇〇八年の一年間、月に一本、テレビドラマの脚本を書いていました。テレビドラマには大抵いくつかの制約(条件)がありますが、今回は「主人公は中高生の女子であること」。それ以外の内容はお任せとのお達しに、友情、恋愛、家族間のすれ違いなど、書いているときだけ気持ち十代女子になりきって一喜一憂していました。そして一本書き終わるたびに、
「こんな青春、送りたかったな」と、ふと我が青春を振り返りました。
わたしは高校一年の夏に故郷大阪から単身上京しました。
とりあえず夜間高校に編入したものの、夜間通学というシステムや人間関係も含めた環境にどうしても馴染めない。そのうち日を追うごとに忙しくなったため、通学日数が少ない高校へ転校することに。結局三つの学校を渡り歩いた末、通信制高校に落ち着きました。東京で通った学校はすべて決まった制服がなかったので、わたしにとって制服とは、学生役を演じるための「衣装」でした。
こんな風に書きだしてみると、なんだかむなしい学生時代ですね。
でも当時はそんな風に思いませんでした。「あなたは仕事をするために来たんでしょ」と周囲の大人から言われていたし、わたし自身ももちろんそのつもり。恋愛も遊びも、むろん学生の本分である勉強など面倒くさいことはなるべく回避し、余計なことは考えず目的である仕事に遭進しなくちゃならない。
それがわたしの青春でした。
でもどこかでその「面倒くさい」ものを求めていたのかもしれません。そんな時、当時通いつめた本屋で出合ったのが遠藤周作著『砂の城』でした。
本作の舞台は一九七〇年代の長崎県島原。高校一年の主人公早良泰子と友人水谷トシは将来の希望と不安を感じ始めている。当時の女性は高校を卒業したら結婚するか、花嫁修業の一環で進学するというのが主流。色々と考えた末、地元短大にそろって進んだ二人の運命は、ある分岐点でバラバラになっていきます。
泰子は大学生の西宗弘と出会い、淡い恋をします。トシは大学をやめて星野という男と神戸へ向かいますが、男に流されるままに犯罪に手を染め、刑務所へと送られるのです、その後、西は過激派グループに加入し、ハイジャック事件を起こします。その飛行機に偶然乗り合わせたのが、スチュワーデス(現在の客室乗務員)となった泰子でした。
読んだ当時、トシの生き方は理解に苦しんだし、「過激派」という言葉すら知りませんでした。ただ、あるセリフがこれまで感じたこともない衝撃をわたしの心に与えたのです。
物語冒頭で戦争に行く前に母の初恋相手の残した言葉が、泰子に託した母の手紙に綴られています。
負けちゃだめだよ、うつくしいものは必ず消えないんだから。
この言葉がズシンと胸を打ち、涙がこぼれました。
「戦争」という個人には何の責務もないことに巻き込まれて、明日をも知れぬ男が、初恋の人を亡くす恐怖に怯える少女にかけた言葉です。が、わたしには自分にかける言葉のように聞こえました。
親と離れて暮らす寂しさ、学校や仕事場でうまく立ち回れない自分へのいら立ち、どうにもならない激しい感情に駆られ、何もかもが自分の敵のように思えて仕方なかった時、わたしはそういう感情に対し鈍感になろうとしていました。感情を無視すれば、たとえ傷つけられても平気だと考えたから。それはたぶんわたしがもっと子どもだったころからの、辛い時をやり過ごす方法でもありました。
しかし演技や歌のレッスンでは感情を出すことを求められます。いつもどうしていいかわからず、失敗ばかりしていました。
一時ブレる、ブレないという言葉が政界で頻繁に使われていましたが、それに例えるなら、当時のわたしはとにかくブレずにいようとしていたのです。
しかしブレない状態というのは、十分にブレた後に定まることをいうのでしょう。
十代の子どもは、自力だけで自分の位置は定まりません。あれこれと翻弄されることによって考えや精神が研磨され、そして時代や場所など、自分以外の何かの力によって、ブレないでいられる地点までいつのまにか持っていかれる、そんなものだろうと思います。「うつくしいものは必ず消えない」という言葉には、表面的な美しさを示すものではなく、研磨されたのちに残るものを指している、と解釈しました。
思春期、青春期のブレまくりの時期に、いきなりひとつのことに打ち込もうとするわたしに疑問を投げかけ、「突っ張らずとも自然に位置は定まる」というような答えを一篇の小説がくれました。
人生を変えた本という取材などで、『砂の城』を答えに挙げることがありますが、その理由は少しずつ変化しています。読み返すその度に本書は一字一句変わっていないのに、読み手の自分が青春時代からどんどん離れた分、急にわかることがある。そして自分の子どもの青春を眺めるような立場でいることに気付きます。
当時の自分を心の中で抱きしめて「負けないで。うつくしいものは消えないんだから」と声をかけているのかもしれません。
ところで、私がこの本を手に取ったきっかけは、そのタイトルにあります。
砂という脆く、すぐに壊れてしまうものと、堅牢なイメージの城を組み合わせた「砂の城」。実はある女性歌手の歌のタイトルと同じ。この歌が大好きでした。きっとこの小説がその源だったのですね。そんな共通点にも惹かれてやまない一作です。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
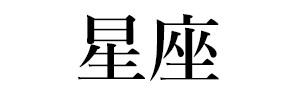
星座 2010年4月1日
ALL REVIEWSをフォローする