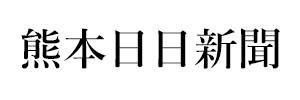書評
『告白』(中央公論新社)
うわあぁぁっ、町田康がやってもうた! 昨年『パンク侍、斬られて候』っちゅうネオ時代小説の傑作をいてこましたばかりやのに(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2005年4月)、次に出した『告白』がまた大傑作になってんねんで。えーらいこっちゃ、えらいこっちゃ。……すみません。ここ数週間の狂ったような『告白』熱のあまり、間違いだらけの河内弁で興奮してしまったわたくしなんでございます。いや、でも、ホントに、読売文学賞、谷崎潤一郎賞、泉鏡花賞、野間文芸賞といった有名どころの文学賞を独り占めしたっておかしくない。そのくらいの作品だと思し召せ。
明治二六年五月二五日の深夜、河内国赤阪村字水分で農家の長男として生まれ育った城戸熊太郎が、博打仲間の谷弥五郎と、同地で幅を利かせていた松永傳次郎宅などに乗り込み、傳次郎一家や親族らを次々と斬殺、射殺。その数は一〇名にも及んだが、被害者の中には自分の妻や乳幼児も含まれていた――。「河内十人斬り」として河内音頭のスタンダードナンバーにも残っている事件を題材に、町田康がこの小説で描こうとしているのは、人が人として生きていられなくなるほどの深い絶望なのではないでしょうか。人はなぜわかりあえないのか。言葉はなぜ本当のことを正確に伝える術になり得ないのか。そのわかりあえなさ、伝えられなさが強いる孤独と絶望。熊太郎を惨劇へと導き、引いては同時多発テロ以降の”無・理解”ではなく”非・理解”の世界を作り上げているのも、そんなコミュニケーションの断絶なのではないか。読後、明治時代と現代の光景が重なりあう、そんな重層的な物語になっているのです。
作者は熊太郎を思弁の人として描いています。世の中には、家族や村人が持っているそれとは違う水準や基準があるということを、子供の頃早々に悟ってしまった熊太郎は、狭い世界で自分たちだけの価値観に拠って話し行動する周囲の人間と、いつしか自然な会話ができなくなってしまうのです。思いと言葉と行動が一致している村人たちは「もうじき秋祭りやな」「そやな」という必要最小限の会話でわかりあえてしまうのに、熊太郎にはそんな簡単なこともできない。思考はとりとめもなく広がり、それらは〈河内の百姓の言葉で表すことができない〉から、熊太郎の思いはまるで伝わりません。
知性ゆえに〈村人から見れば熊太郎はごく簡単な、あほでもできることができぬ大たわけ〉になってしまう不条理。自分は他の者とは違うという自意識、それと同じくらい強いコンプレックスから孤絶感を深める熊太郎は、農作業にも真面目に取り組めず、無頼の徒と化していきます。作者はそんな主人公に「あかんではないか」とツッコミを入れながら、五ページに一回は爆笑できるユーモラスな文体とエピソードをもって、熊太郎の思考の流れを心理小説さながらにつぶさに記述していくのです。
ここに描かれた熊太郎は、怠け者で欠点が多い人間です。でも、悪人じゃない。むしろ、正直者の善人の側に近いといえましょう。たまには改心して田を耕してみたりもします。けど、いっかなうまくいかない。ためしに、一八三ぺージから数ページにわたる熊太郎の苦心惨惰ぶりを読んでみて下さい。爆笑と共に、頭の中であれこれ考えることが喋るとか動くといった行動にまるで結びついていかない熊太郎という人物を、好きにならずにはいられなくなるはず。その共感ゆえに後半、彼がどんどん窮地に追い込まれ、それまでの笑いが一転凍りつき、あの悲劇の夜へと刻一刻近づいていく時、胸苦しさを覚えずにはいられないのです。熊太郎を追いつめたものは何なのかと、深く考えずにはいられなくなるんです。
熊太郎は明治期に入ってきた西洋式の近代的自我に翻弄された日本人の投影、という読み方も可能でしょう。凶行に走るその姿を、アメリカという大国に伝える言葉を持たないまま自爆テロに走るアラブ人と重ねることも可能でしょう。熊太郎はいかようにも読み替え可能なイコン、もしくは神話的な人物なのです。全編を彩る河内弁の調子まで翻訳するのは至難の業かもしれないけれど、他の国の人たちにも読んでほしい。もちろんすべての日本人が読むべきなのは言うまでもありません。
【この書評が収録されている書籍】
明治二六年五月二五日の深夜、河内国赤阪村字水分で農家の長男として生まれ育った城戸熊太郎が、博打仲間の谷弥五郎と、同地で幅を利かせていた松永傳次郎宅などに乗り込み、傳次郎一家や親族らを次々と斬殺、射殺。その数は一〇名にも及んだが、被害者の中には自分の妻や乳幼児も含まれていた――。「河内十人斬り」として河内音頭のスタンダードナンバーにも残っている事件を題材に、町田康がこの小説で描こうとしているのは、人が人として生きていられなくなるほどの深い絶望なのではないでしょうか。人はなぜわかりあえないのか。言葉はなぜ本当のことを正確に伝える術になり得ないのか。そのわかりあえなさ、伝えられなさが強いる孤独と絶望。熊太郎を惨劇へと導き、引いては同時多発テロ以降の”無・理解”ではなく”非・理解”の世界を作り上げているのも、そんなコミュニケーションの断絶なのではないか。読後、明治時代と現代の光景が重なりあう、そんな重層的な物語になっているのです。
作者は熊太郎を思弁の人として描いています。世の中には、家族や村人が持っているそれとは違う水準や基準があるということを、子供の頃早々に悟ってしまった熊太郎は、狭い世界で自分たちだけの価値観に拠って話し行動する周囲の人間と、いつしか自然な会話ができなくなってしまうのです。思いと言葉と行動が一致している村人たちは「もうじき秋祭りやな」「そやな」という必要最小限の会話でわかりあえてしまうのに、熊太郎にはそんな簡単なこともできない。思考はとりとめもなく広がり、それらは〈河内の百姓の言葉で表すことができない〉から、熊太郎の思いはまるで伝わりません。
知性ゆえに〈村人から見れば熊太郎はごく簡単な、あほでもできることができぬ大たわけ〉になってしまう不条理。自分は他の者とは違うという自意識、それと同じくらい強いコンプレックスから孤絶感を深める熊太郎は、農作業にも真面目に取り組めず、無頼の徒と化していきます。作者はそんな主人公に「あかんではないか」とツッコミを入れながら、五ページに一回は爆笑できるユーモラスな文体とエピソードをもって、熊太郎の思考の流れを心理小説さながらにつぶさに記述していくのです。
ここに描かれた熊太郎は、怠け者で欠点が多い人間です。でも、悪人じゃない。むしろ、正直者の善人の側に近いといえましょう。たまには改心して田を耕してみたりもします。けど、いっかなうまくいかない。ためしに、一八三ぺージから数ページにわたる熊太郎の苦心惨惰ぶりを読んでみて下さい。爆笑と共に、頭の中であれこれ考えることが喋るとか動くといった行動にまるで結びついていかない熊太郎という人物を、好きにならずにはいられなくなるはず。その共感ゆえに後半、彼がどんどん窮地に追い込まれ、それまでの笑いが一転凍りつき、あの悲劇の夜へと刻一刻近づいていく時、胸苦しさを覚えずにはいられないのです。熊太郎を追いつめたものは何なのかと、深く考えずにはいられなくなるんです。
熊太郎は明治期に入ってきた西洋式の近代的自我に翻弄された日本人の投影、という読み方も可能でしょう。凶行に走るその姿を、アメリカという大国に伝える言葉を持たないまま自爆テロに走るアラブ人と重ねることも可能でしょう。熊太郎はいかようにも読み替え可能なイコン、もしくは神話的な人物なのです。全編を彩る河内弁の調子まで翻訳するのは至難の業かもしれないけれど、他の国の人たちにも読んでほしい。もちろんすべての日本人が読むべきなのは言うまでもありません。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする