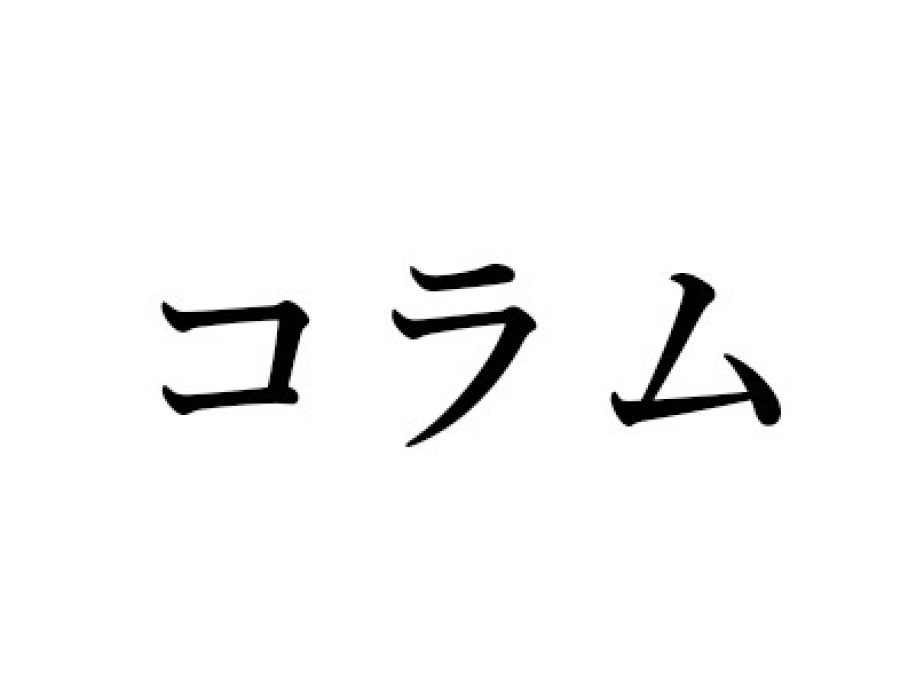書評
『大友二階崩れ』(日本経済新聞出版社)
「義」に忠実な家臣の家督をめぐる攻防戦
親が長男に財産を譲る。ところが何らかの理由があって、「やっぱりなかったことに」といって、その財産をたとえば末っ子に譲り直す。現代ではとても認められない行為だが、家父長権がたいへんに強大だった中世にあっては、この「悔い返し」行為はなんの文句もなく認められた。鎌倉幕府は「問題なし」という判断だったし、幕府の法律である「御成敗式目」の20条にも「OK」と明示されている。財産のもっとも大きなものは「家督」である。平安時代の後期などでは、男子はそれぞれに所領を分け与えられていたが、鎌倉時代も中期になると、「家督」に定められた男子が親の財産の主要部分を受け継ぐようになり、この趨勢(すうせい)は時代の流れとともに、定着していく。
以上まとめると、戦国時代では「家督」を定める権利は父親にあり、「家督」かそうでないかは、その子の将来に、良くも悪くも甚大な影響を与えた。
同時代の豊後。大友家の発展を現出した当主の義鑑(よしあき)は、五郎義鎮(よししげ)(のち宗麟(そうりん))を家督に据えたがこれを廃嫡し、聡明な塩市丸を後継者にしようと目論(もくろ)んでいた。本来はその行為は武家社会では正しい。だが、有能をもって知られる大友家臣団の面々は、それぞれの思惑に従って虚々実々の駆け引きを展開し、それが「二階崩れの変」という陰惨な事件に発展していく。
この本の興味深いところは、タイトルとされた「二階崩れ」があくまでも流れの一コマであって、本当は家臣たち相互の、手に汗握るギリギリの交渉を描いていることにある。主人公に据えられた吉弘鑑理(あきまさ)は「義の人」として造形される。義に即した彼の行動は多くの人を不幸にしながら、最後には受け入れられていく。それはまさに、一服の清涼剤たる武人の姿なのだ。
ALL REVIEWSをフォローする