書評
『河岸忘日抄』(新潮社)
ふと気づけば、忙しがっていることで必要とされているふりをしている。何でもかんでもわかった気になろうとしている。そういうハイテンションな日々に、時々、心底疲れてしまう。そんな時、堀江敏幸の小説が効く。セーヌ河岸に繋留(けいりゅう)されている船で暮らすことになった〈彼〉。その日々の出来事と思考の航跡をたどった最新刊『河岸忘日抄』もまた、落ち着きのない心の中心にすーっと鉛錘(えんすい)を垂らしてくれる、そんな鎮静効果のある小説なのです(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2005年)。
この小説の中では、強さや速さといった世間で称揚されている価値に疑議が呈されます。たとえば、小学生の時に理科の実験でやった二本の電池を直列と並列につないで光量の違いを見る実験を引きながら堀江さんは、1+1が2の光量を生む直列つなぎを礼賛し、並列つなぎの〈足したつもりなのに、じつは横並びになっただけで力は変わらず温存される前向きの弥縫策(びほうさく)を認めようとしない〉世間の窮屈さを明らかにするのです。稀有の強さは、〈ひたむきな弱さの持続によって維持され、最後の最後に実をむすぶ〉ものなのではないかと、そっと示すのです。何もかもがくっきり鮮明に見えることをよしとする風潮にあって、〈ぼんやりと形にならないものを、不明瞭なまま見つづける力〉が欲しいと念じるのです。
携帯電話を持たず、メールではなく手紙とファクシミリで日本にいる友人と近況や心境をやり取りするこの小説の担い手は、一見マイナスに見えるような言葉や考えにこそ心を寄せていきます。すぐに結論に飛びつき、くるくるとよく回転する頭を働かせ、有利な側へと動き続けることで、多数派の中心へ踏み込んでいく――いわゆる世間で言うところの成功者とは正反対の人間なのです。流行に棹さすことなく、時の河岸に佇(たたず)み、自分の内側と世界で起きていることについて静かに多面的に考えを深めていくのです。
でも、これは隠遁者による随想小説の類ではありません。そうした思索の跡を、読者のページを繰る指を止まらせないだけの興味深い物語の中に織り込む。それが堀江作品の素晴らしさなのです。Kという化け物みたいな鮫(さめ)の影に脅かされる男の生涯を描いたブッツァーティの短篇といった、〈彼〉が船上生活で読む数々の小説とその粗筋、かつて観た映画の記憶、船を所有する大家と交わす会話とこの老人の孫娘にまつわる謎、郵便配達夫との交流、探偵をしていたこともある年長の友人とやり取りするファクシミリや手紙の内容。それらがすべて、その後にあらわれるエピソードのさりげない伏線になっており、あたかも上質なミステリーのような読み心地が味わえる構成になっているのです。
この小説の中にはたくさんの心に響く言葉があります。たとえば、書評という本について云々する職業に就いているわたしは、次の言葉を胸に深く棲みつかせたいと願う者です。
〈趣味に合う合わないを口にするのは、あまりにもやさしい。好き嫌いでものごとを判断するのは、あまりにもたやすい。そんな単純な二分法で世界を割り切ることができたら、生はどれほど安楽だろう。趣味に合わないと断じるとき、なぜ趣味に合わないかを説明するのは容易ではないけれど、むずかしいことでもない。こいつはだめだとあきらめようとする内側の声を消して均衡をとりながら、その均衡が紋切り型に陥らず、自分ひとりに可能な心の溝を確実にトレースするレコード針の針圧は、千人いれば千通りある。公約数を求めるのではなく、もう約分できなくなったその最小値がすなわち個になる方向でひとに接することこそが、きびしい試練なのだ〉
無人島に持っていける本を一冊選べと言われたら、今のわたしなら間違いなくこの小説を選びます。物語と思惟(しい)と語りがこれほど清冽な流れをなしている作品は、それほど多くはないのですから。
【この書評が収録されている書籍】
この小説の中では、強さや速さといった世間で称揚されている価値に疑議が呈されます。たとえば、小学生の時に理科の実験でやった二本の電池を直列と並列につないで光量の違いを見る実験を引きながら堀江さんは、1+1が2の光量を生む直列つなぎを礼賛し、並列つなぎの〈足したつもりなのに、じつは横並びになっただけで力は変わらず温存される前向きの弥縫策(びほうさく)を認めようとしない〉世間の窮屈さを明らかにするのです。稀有の強さは、〈ひたむきな弱さの持続によって維持され、最後の最後に実をむすぶ〉ものなのではないかと、そっと示すのです。何もかもがくっきり鮮明に見えることをよしとする風潮にあって、〈ぼんやりと形にならないものを、不明瞭なまま見つづける力〉が欲しいと念じるのです。
携帯電話を持たず、メールではなく手紙とファクシミリで日本にいる友人と近況や心境をやり取りするこの小説の担い手は、一見マイナスに見えるような言葉や考えにこそ心を寄せていきます。すぐに結論に飛びつき、くるくるとよく回転する頭を働かせ、有利な側へと動き続けることで、多数派の中心へ踏み込んでいく――いわゆる世間で言うところの成功者とは正反対の人間なのです。流行に棹さすことなく、時の河岸に佇(たたず)み、自分の内側と世界で起きていることについて静かに多面的に考えを深めていくのです。
でも、これは隠遁者による随想小説の類ではありません。そうした思索の跡を、読者のページを繰る指を止まらせないだけの興味深い物語の中に織り込む。それが堀江作品の素晴らしさなのです。Kという化け物みたいな鮫(さめ)の影に脅かされる男の生涯を描いたブッツァーティの短篇といった、〈彼〉が船上生活で読む数々の小説とその粗筋、かつて観た映画の記憶、船を所有する大家と交わす会話とこの老人の孫娘にまつわる謎、郵便配達夫との交流、探偵をしていたこともある年長の友人とやり取りするファクシミリや手紙の内容。それらがすべて、その後にあらわれるエピソードのさりげない伏線になっており、あたかも上質なミステリーのような読み心地が味わえる構成になっているのです。
この小説の中にはたくさんの心に響く言葉があります。たとえば、書評という本について云々する職業に就いているわたしは、次の言葉を胸に深く棲みつかせたいと願う者です。
〈趣味に合う合わないを口にするのは、あまりにもやさしい。好き嫌いでものごとを判断するのは、あまりにもたやすい。そんな単純な二分法で世界を割り切ることができたら、生はどれほど安楽だろう。趣味に合わないと断じるとき、なぜ趣味に合わないかを説明するのは容易ではないけれど、むずかしいことでもない。こいつはだめだとあきらめようとする内側の声を消して均衡をとりながら、その均衡が紋切り型に陥らず、自分ひとりに可能な心の溝を確実にトレースするレコード針の針圧は、千人いれば千通りある。公約数を求めるのではなく、もう約分できなくなったその最小値がすなわち個になる方向でひとに接することこそが、きびしい試練なのだ〉
無人島に持っていける本を一冊選べと言われたら、今のわたしなら間違いなくこの小説を選びます。物語と思惟(しい)と語りがこれほど清冽な流れをなしている作品は、それほど多くはないのですから。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
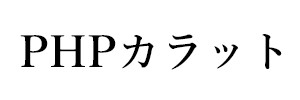
PHPカラット(終刊) 2005年7月
ALL REVIEWSをフォローする








































