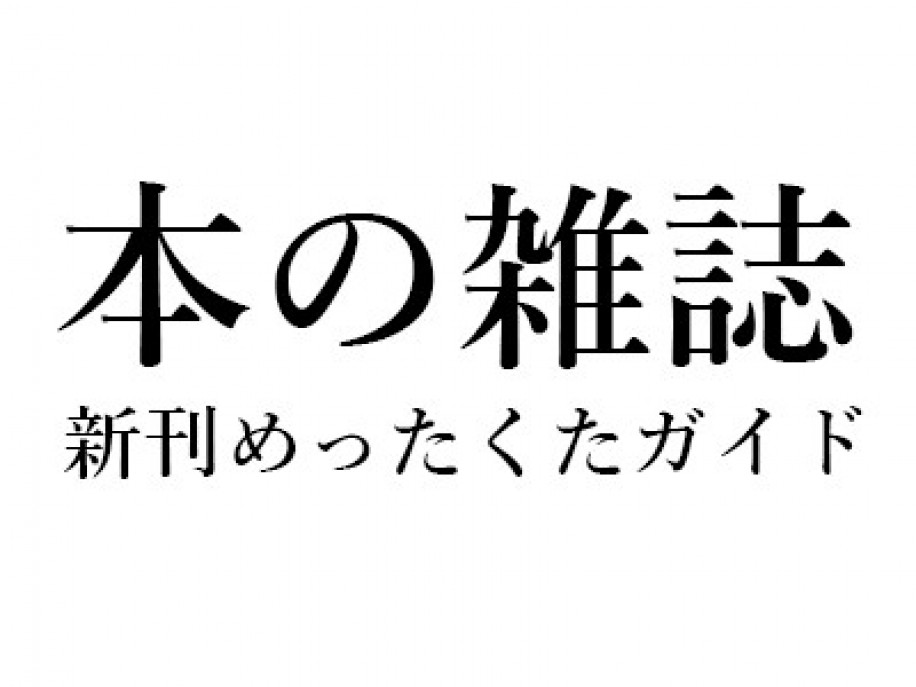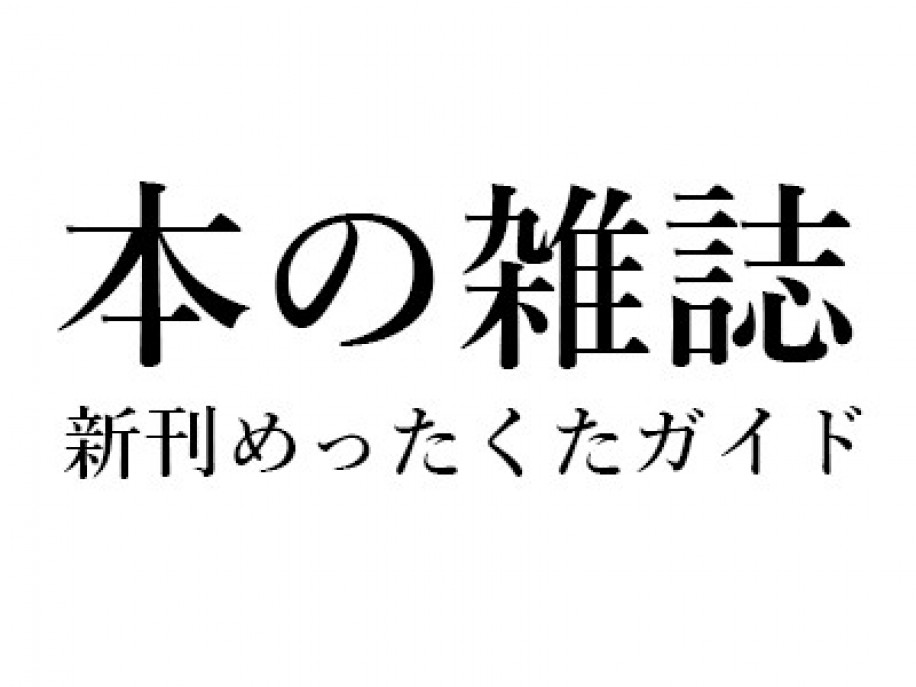書評
『映画辛口案内―私の批評に手加減はない』(晶文社)
批評の三つ星もしくは五つ星
このコーナーは要するに書評である。理想的な書評とは何かというなら、ほめてあれば即読みたくなり、逆にけなしてあったとしてそんなにひどいのなら一度経験してみたいと思わせるようなものである。一言でいうなら、食欲がわくもの。これぞ書評の三つ星もしくは五つ星。そして料理も、そんな彼女たちと同様だ、と言ってしまいたい誘惑にかられる。何しろ、ほとんどの前菜にキャビアがのっかっているのだから。それはさながら手首で光るロレックスといったところ。その違いといったら、ロレックスは時を告げてくれるけれど、ここのキャビアは金属くさい味がして穏やかではないし(勘定に対しては特に)、実のところそれほど洗練されているということもない。……。主菜の「スズキのバジリコ風味」は、料理長がいかにソースをうまく作れるか、ということを言うための一品。魚の言い分もあったろうに(いや、なかったのかもしれない)。結局は、パンの切れ端でもその役を果たしえたはず、というわけだ。そうすれば値段も安くなる。デザートもまたしかり。アメをかけたリンゴとパイ生地を別々に調理することによって、タルト・タタンを自分風にアレンジしたかったのかもしれないけれど、私に言わせればそれはほんとうじゃない。なぜなら、タルト・タタンの本質そのものが、一緒に調理することで果物とパイ生地のマリアージュ(結婚)を生み出す、その特別な調理法にあるのだから。
これは「ブルータス」六月一日号に載ったフランスの「覆面レストラン批評家」フランソワ・シモンが日本のフランス料理店を(覆面)訪問して書いた批評の一節。明快で、鋭く、面白い。その結果として、少々不躾で意地悪に見えるのは致し方あるまい。シモン氏はあの偉大なレストランガイド「ミシュラン」を生んだ国の人なのである。いや、その「ミシュラン」の背後には、エスプリに富んだものすごい文芸批評の歴史があるというべきか。ぼくならずとも、このフランソワ・シモンの書き方で書評や文芸時評をやったら面白いだろうなあと思いたくなるだろう。では、こんなのは如何。
ランディスは、三〇年代風の堅苦しいスタイルを再現できたと思っているのかもしれない。最初の一時間ほど、ランディスはあらゆるディテールをとくと頭におさめてくれというように、それぞれの場面を強調し、固定していく。まるで「本当のわたしはもっと利口だ」といっているようだ。ついに、あなたは座席から立ち上がって、こうさけびたくなる。「そうか? じゃ、早く証明してみろ」この映画はもったいぶっている――どの構図もじっと静止したきりなので、もたもたするな、とカメラの尻をけっとばしたくなる(『映画辛口案内』ポーリン・ケイル著、浅倉久志訳、晶文社)。
ここにもシモンと同じエスプリ(?)がある。いや三つ星(五つ星)精神が。いいなあと思う。思うけれど、実行できないのは白黒をつけるのを嫌う(そのことによって他人に嫌われるのを嫌う)この国の精神風土のせいなのか。試しにちょっとやってみようかな。
久々の新作。ぼくは読みながら頭が痛くなった。いや、ぼくだけではなく、この作品を読む読者は誰だってそうなるかもしれない。ここに出てくる恋愛感情はテレビドラマのそれのように現実味がない。この作品はまるで、女子高生の恰好をしているCMの西田ひかるのようだ。ファン以外にとっては、ブリッ子と呼ぶのもおそろしい。
やっぱり、ぼくには無理だ……。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする