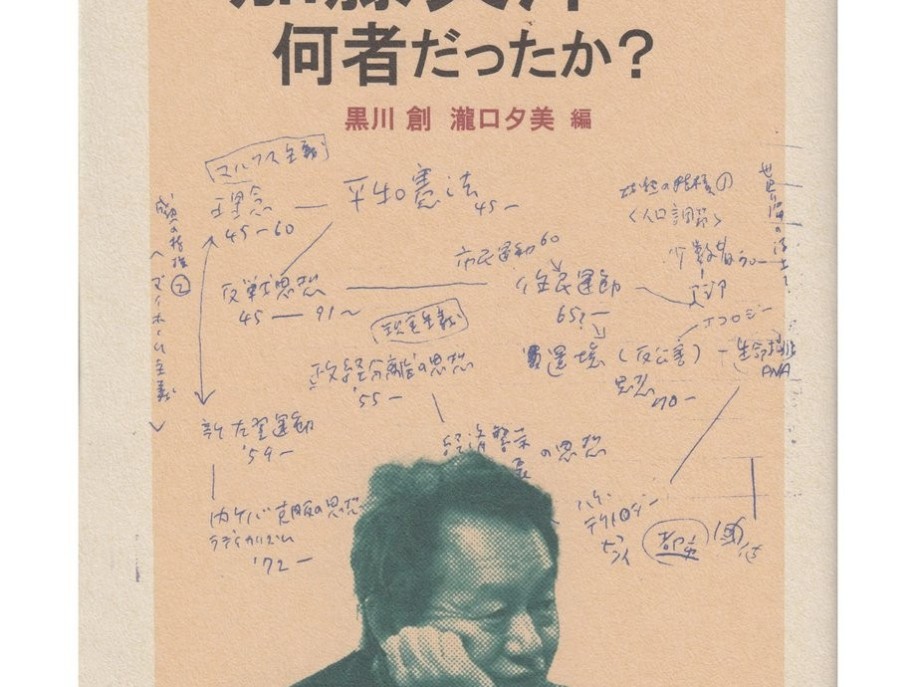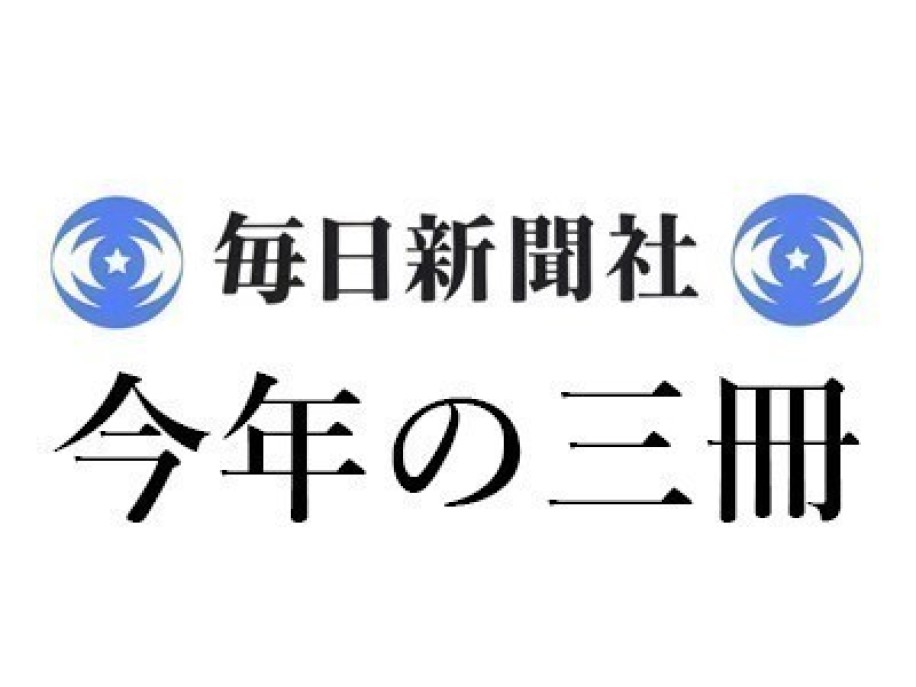書評
『メディア・ショック―「第四の権力」を解剖する』(新評論)
開発競争で遅れをとった仏
テレビとはなにか、どんな悪弊があり、どのような未来を期待してよいのか。こうした設問は日本でもつねに繰り返されており、また多チャンネル化が進むアメリカでは情報ハイウェイというマルチメディア志向をもたらした(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1994年)。僕たちは、ついアメリカを基準に考えがちだが、本書によって、ヨーロッパの中心にいるフランスがこの問いにどう立ち向かっているのか知る機会が得られた。本書で強く感じられるのは、BBC(イギリス)のドキュメンタリーやハリウッド製の映画や日本のアニメーションなどの映像ソフト、そして新しい技術(高品位テレビ)で、フランスが遅れをとっているという危機意識である。国家の未来を左右するかもしれないこれらの産業が現状のままであれば、フランスは国際競争で生き残れなくなる。イタリア、スペインなどのラテン系の第二グループに転落しつつあるのだ。この事実はフランスの気位をいたく傷つけている。シャネル、ディオール、サンローラン、カルティエ、エルメス、ヴィトンなどの贅沢(ぜいたく)品産業を持ちながら、「現在でもなお文化と知的影響の灯台だと自負している国にとって、メディアの分野で二流視されることは何という屈辱だろうか!」と。
たしかにフランスはメディアの入れ物においては遅れをとった。だが、つねに時代を切り拓(ひら)く思想家を輩出するこの国で書かれた警句はやはり傾聴に値する。いわく「人々はこれからは現場中継で戦争し、カメラの前で暴動を鎮圧し、同時中継でクーデターを進めることになる」、いわく「政治家は虚偽を述べれば追放され、経済人は損失を出せば破産する、だがジャーナリズムはばかなことを言ってもいつまでもそこにいる」。日本については、「この権力乱用に無頓着な国では――権力はいたるところに存在し、どこにも存在しない――マルチメディア集中は極度にまで進行しており、最大級の新聞と大型民放は同一グループに属している」と羨望と皮肉が込められている。
ALL REVIEWSをフォローする