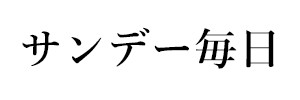書評
『死にいたる芳香』(早川書房)
天使の取り分
ワインを樽で熟成できるのは最大限二年、あとはビンに移してねかせる。ワインから蒸溜したコニャックは樽のなかでしか熟成しない。樽材を通して呼吸し、木材の成分を長年月にわたってとりこんで美質を磨いてゆく。木材を通して呼吸するのだから蒸発をさけられない。年に二~四パーセントずつ減っていくこの熟成中の蒸発がコニャック作りの大きなネックらしい。目減りも大変な量だが、気化には当然アルコール分も含まれるわけで、常に火災の危険もある。それに備えてもちろん保険が二重三重にかけられている。
コニャック作りにはピュアモルト・ウイスキー作りの六倍も費用がかかる。原料には質のよくないワインが使われている。上等のワインを使ったらさぞかし極上のものができるにちがいないと当然思う。だが、ワインとして高値で売れるのに、さらに手間と費用をかけるなんて愚の骨頂。どのメーカーも資金繰りで大わらわなのだ。
観光客としてコニャックの醸造元に立ち寄るだけでは知ることのできないそうした内情、コニャック作りの詳細を、ユベール・モンテイエのミステリー『死にいたる芳香』は、保険会社の慧眼な調査員を案内役にして、あまさず教えてくれる。
スイスの保険会社の調査員、ペーターは、休暇中のパリで知りあった美食評論家のサルティーヌと食事中に異様な死を目の前にする。コニャックのグラスを傾けていたサルティーヌが、性器を勃起させたまま色情狂そのままに狂い死にするのだ。コニャックからはヨヒンビンおよびダチェラという催淫・幻覚効果のあるアルカロイド毒物が検出され、ペーターは分析結果をたずさえて醸造元のドリュモン社に乗りこむ。
ドリュモン社では、そのコニャックを「フランス革命二百年記念ブレンド」と銘打って大々的に売りだす予定で、すでに二百八十本は世界中の要人、懇意に配るために出荷ずみ。サッチャー夫人がサルティーヌみたいなていたらくになったら、いったいどうなるか。
配送差し止めの手配だけは早速なされてひと安心だが、件(くだん)のブレンドのサンプルを念のために口にした酒倉の責任者はきっぱりと言う。
「非の打ちどころがありません。見事にして豪華。生き生きとした多彩なビロードのような味です」
毒物は酒倉でビン詰めにする段階でしか入れようがないとわかるだけで、ペーターの探索は頓挫する。犯人と目星をつけた何人かも美食に目がないだけで、犯罪には走りそうにない。
作者は、フランスでは名うての美食家で通っているらしい。この小説も、美食・美酒談義がすぎて、その間に犯人が高飛びしそうで、犯人捜しをあてこんで読んでゆくと、もどかしい思いにつかまることになりかねない。しかし、冒頭でれっきとした殺人事件を起こしているわけだから、とにかく犯人捜しはまがりなりにも続けられる。やがて、ドリュモン社社長夫妻の愛憎劇が表舞台にせりだして、毒物混入の真犯人の名もあきらかになる。あきらかになるが、その直後、酒倉が、証拠になる品々もろとも炎上し、コニャック全部が蒸散してしまう。
小説の原題は、『天使の取り分』というのだそうだ。もともとはコニャックが醸成中に蒸発する分のことで、普通には、何かをかすめとるときに、「これは天使の分」というふうに使う。誰が何をどこからかすめとるのか、最後にならないとわからない。わかってニヤリとする楽しみもある。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする