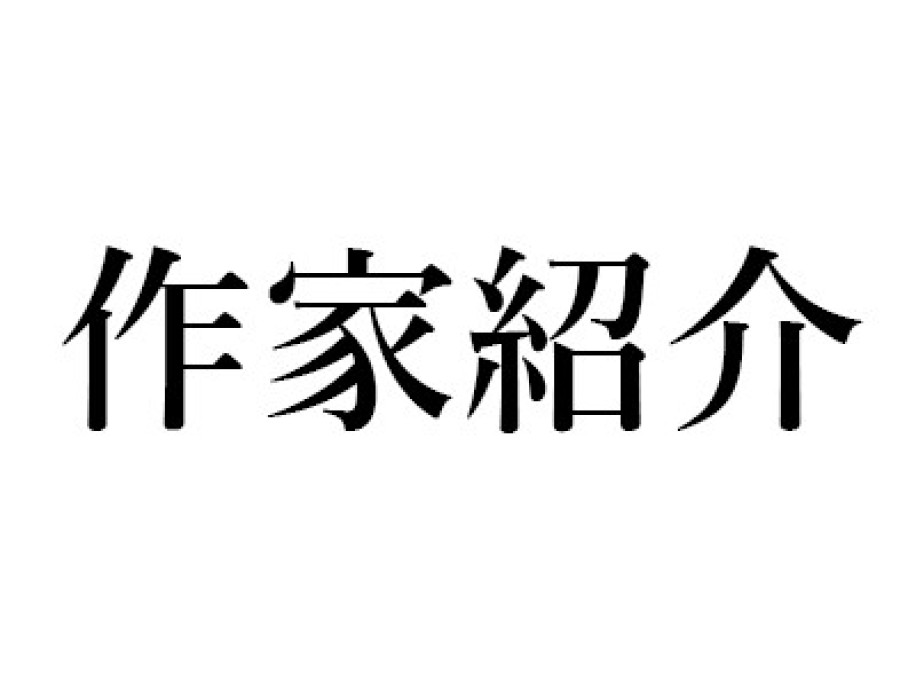書評
『木』(新潮社)
〈なみ外れた眼〉といわざるを得ない。
えぞ松は一列一直線一文字に先祖の倒木のうえに育つ。どんなに知識のない人にも一目で、ああ倒木更新だ、とわかると聞いた。
なんという手ごたえの強い話か、と思うと、耳にきいただけでは済まされない。ぜひ目にも見ておかないことには、と幸田文は、はるばる北海道富良野の東大演習林まで見に行く。
年を考えると七十すぎである。思い込んだら一念でぎゃあぎゃあわめいた、とすまながっているが、本書に一貫する、自分の目で見なければ承知しない精神、というものにまず圧倒される。 倒木の上の若木はどうだったか。
若木をのせた死んだ親木はどうか。
多少怯じながら苔をおしのけ、樹皮を掻き分ける。雨に濡れた指先が芯に触れる。「古木の芯とおぼしい部分は、新しい木の根の下で、乾いて温味をもっていた」。ああ、このぬくもりをうっかり見落とさなくてよかった、とおもう。
ここはまるで読む者が親木になって触られたようにさえ感じる。このぬくもりを自分の行先き一生のぬくみとして信じよう、ときめる気になったら、感傷的にされて目がぬれた、とある。
無知無学だから、などといいつつ、文さんは五感でせいいっぱい木を見る。匂いをかぐ。ひめしゃらの樹皮を流れる美しい水に感動すると、その水量を手ではかってみたくなる。その水を舌で味わいたくなる。「ものを覚える」とは、ここから始まるのだろう。
自在に焦点を変えられる目でもある。ひのきの木の美点を並べたてられると、「あまりよすぎると、こちらが淋しくなる」と、関心が反転してしまう。
たとえば二本、兄弟木が生えている。片方がまっすぐそびえれば、片方は必ず傾斜する。かしいだ方からは上材はとれない。それをアテという。と聞くと、「アテの悲しさで心がいっぱいになる」。
かしげばどこかに無理がくる。バランスを崩すまいとしながら、木はものをいわずに生きている。立派だ。だが、せつない。「木の生きていく苦しみと、人の生きていく苦しみとが、あまりにもよく似ているので、しきりに親身な感情が動いて」しまう。
アテが悪い、といわれればどうよくないのか、やはり自分の目で確かめなくてはいられない。文さんはアテが挽かれるところを見るために出直す。アテは暴れた。裁たれてて、反りかえった。「な、わかったろ。アテはこうなんだ。だからワルなんだ」といい捨てられ、たまらなくて裂けたもののそばに膝をつく。「抱けば、その頑くなな重量。このアテをどうしたらいいかとだけ、あとは何も考えられなかった」
「見る」という言葉が多用されるが、それは漫然と眺めるのではない。五感で「貧欲に承知」してはじめて、「わかった」というものなのだ。
木の感情をわがものとする――〈自然との共生〉とはまさにこのことである。それは「枯れていく木を眺めていられるほど自分の神経はむごくはないのだ」といった父露伴に教わったことだ。文さんがバカ値だからと子どもに藤の木を買ってやらなかったとき、露伴は怒った。町に育つおさないものには、縁日の植木を見せるのも草木への関心をもたせるかぼそいながらの一手段、心の養いであるといったのである。
「木」を見に行くうちに、崩落に出会う。木にあらわれた自然の「恵み」になれて「目がウジャジャケていた」と、はっとする。結果、木を成り立たせる山河、その自然のこわさの方に目がいく。こうして連関して『崩れ』(講談社)が書かれ、これ以降の『木』の各章はあきらかにトーンが変わる。
文格が高く、リズムがあり、まさしくという言葉が選ばれている。でも単なる名文ではない。もしかすると、いっていることはやさしく、当り前のことかもしれない。
が、「木」への迫りかた、心の添わせかたは、やはり凄まじい。生活のテンポや内容を変えなければ、読みきれないのではないかと思った。まして小手先の書評などできはしない。ただただ圧倒された。
【この書評が収録されている書籍】
えぞ松は一列一直線一文字に先祖の倒木のうえに育つ。どんなに知識のない人にも一目で、ああ倒木更新だ、とわかると聞いた。
なんという手ごたえの強い話か、と思うと、耳にきいただけでは済まされない。ぜひ目にも見ておかないことには、と幸田文は、はるばる北海道富良野の東大演習林まで見に行く。
年を考えると七十すぎである。思い込んだら一念でぎゃあぎゃあわめいた、とすまながっているが、本書に一貫する、自分の目で見なければ承知しない精神、というものにまず圧倒される。 倒木の上の若木はどうだったか。
威圧はおぼえないが、みだりがましさを拒絶している格があった。清澄にして平安、といったそんな風格である。むざとは近よらせぬものがある。
若木をのせた死んだ親木はどうか。
あわれもなにも持たない、生の姿だった。……これはまあなんと生々しい輪廻の形か。
多少怯じながら苔をおしのけ、樹皮を掻き分ける。雨に濡れた指先が芯に触れる。「古木の芯とおぼしい部分は、新しい木の根の下で、乾いて温味をもっていた」。ああ、このぬくもりをうっかり見落とさなくてよかった、とおもう。
ここはまるで読む者が親木になって触られたようにさえ感じる。このぬくもりを自分の行先き一生のぬくみとして信じよう、ときめる気になったら、感傷的にされて目がぬれた、とある。
無知無学だから、などといいつつ、文さんは五感でせいいっぱい木を見る。匂いをかぐ。ひめしゃらの樹皮を流れる美しい水に感動すると、その水量を手ではかってみたくなる。その水を舌で味わいたくなる。「ものを覚える」とは、ここから始まるのだろう。
自在に焦点を変えられる目でもある。ひのきの木の美点を並べたてられると、「あまりよすぎると、こちらが淋しくなる」と、関心が反転してしまう。
たとえば二本、兄弟木が生えている。片方がまっすぐそびえれば、片方は必ず傾斜する。かしいだ方からは上材はとれない。それをアテという。と聞くと、「アテの悲しさで心がいっぱいになる」。
かしげばどこかに無理がくる。バランスを崩すまいとしながら、木はものをいわずに生きている。立派だ。だが、せつない。「木の生きていく苦しみと、人の生きていく苦しみとが、あまりにもよく似ているので、しきりに親身な感情が動いて」しまう。
アテが悪い、といわれればどうよくないのか、やはり自分の目で確かめなくてはいられない。文さんはアテが挽かれるところを見るために出直す。アテは暴れた。裁たれてて、反りかえった。「な、わかったろ。アテはこうなんだ。だからワルなんだ」といい捨てられ、たまらなくて裂けたもののそばに膝をつく。「抱けば、その頑くなな重量。このアテをどうしたらいいかとだけ、あとは何も考えられなかった」
「見る」という言葉が多用されるが、それは漫然と眺めるのではない。五感で「貧欲に承知」してはじめて、「わかった」というものなのだ。
木の感情をわがものとする――〈自然との共生〉とはまさにこのことである。それは「枯れていく木を眺めていられるほど自分の神経はむごくはないのだ」といった父露伴に教わったことだ。文さんがバカ値だからと子どもに藤の木を買ってやらなかったとき、露伴は怒った。町に育つおさないものには、縁日の植木を見せるのも草木への関心をもたせるかぼそいながらの一手段、心の養いであるといったのである。
「木」を見に行くうちに、崩落に出会う。木にあらわれた自然の「恵み」になれて「目がウジャジャケていた」と、はっとする。結果、木を成り立たせる山河、その自然のこわさの方に目がいく。こうして連関して『崩れ』(講談社)が書かれ、これ以降の『木』の各章はあきらかにトーンが変わる。
文格が高く、リズムがあり、まさしくという言葉が選ばれている。でも単なる名文ではない。もしかすると、いっていることはやさしく、当り前のことかもしれない。
が、「木」への迫りかた、心の添わせかたは、やはり凄まじい。生活のテンポや内容を変えなければ、読みきれないのではないかと思った。まして小手先の書評などできはしない。ただただ圧倒された。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア

DIY(終刊)
ALL REVIEWSをフォローする