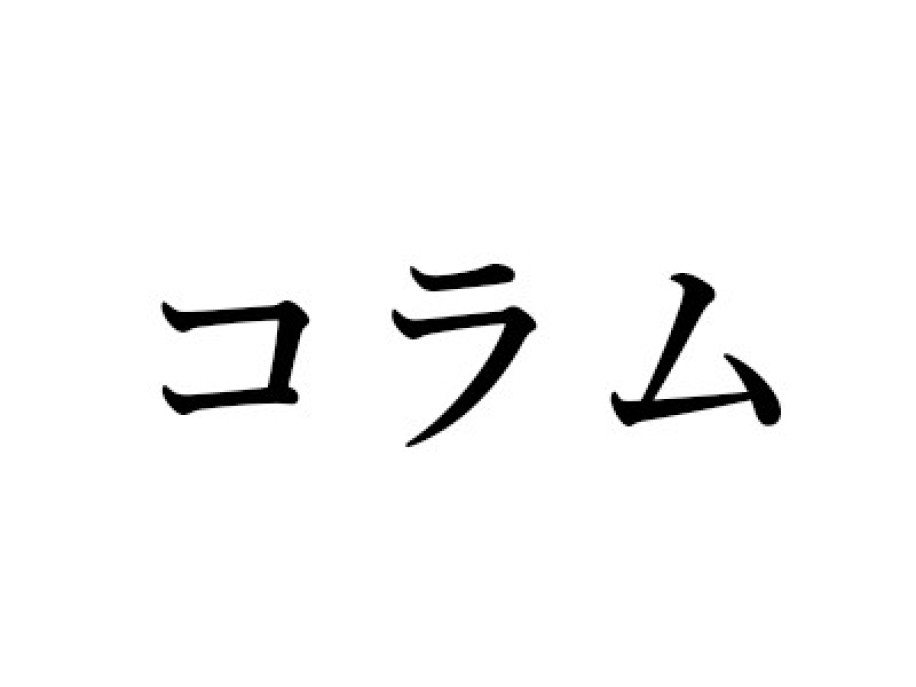書評
『文明の子』(幻冬舎)
ある作品を酷評した場合、できるだけその後も追いかける。そして、もし当方比的に「酷評した作品よりも良い」と思えた時には、そのことをちゃんと書く。それが、わたしの書評家としての落とし前のつけ方です。というわけで、太田光の『文明の子』。わたしは太田さん初の小説集『マボロシの鳥』について、雑誌(文章)ではなくラジオ(話し言葉)でこんな風に批判しました。
「伝わってほしい思いや考えを、一から十まで説明し、その窮屈な語りによって、小説世界を平板にしてしまっている。また、作者が芸人だからかもしれないが、オチをつけなきゃという意識が強すぎるあまり、収録作品のどれもこれもが、読者をわかりやすい感情に誘導する陳腐な終わり方になっている」
ここまで酷評したのですから、わたしには『文明の子』を読む責任があります。で、最初に置かれた、鳥が文明を築いた星の話「光と風」を読みながら「またか」とがっかりしたわけです。また、寓話風のショートSFを読まされるのか、と。でも、それは早とちりでした。ジョン・レノンを殺した犯人の強い思いに引き寄せられたサンタクロースの話や、遺伝子操作によって高い知能を獲得したネズミの話、ピーター・パンになぞらえられる赤ちゃんポストに捨てられた子供の話、滅亡した地球でロボットを友として生きる博士の話など、『文明の子』には、それぞれ一見関係のなさそうな短い話が並んでいます。うっかりした読者なら短篇集と思うかもしれません。しかし、これは長篇小説です。けいれん的時間旅行者を主人公にしているため、時空があちこちへ飛ぶという構成になっているカート・ヴォネガットの『スローターハウス5』。その語りのスタイルに、次元の移動も加えるという野心から生まれた小説なのではないか。勝手な想像なので間違っているかもしれませんが、少なくともそういう“読み”を誘発する結構にはなっているんです。
人間の強い思いを示す電磁波の粒子を、光速に近いスピードで衝突させ核合成することで、人間が望む何かを出現させるマシーンを作った天馬博士。その試運転で、空飛ぶクジラを出現させてしまう孫のワタル。幼いワタルが、動物と会話ができる孤独な少年マナブと出会い、空飛ぶクジラにのって次元を超える冒険に繰り出す物語に、優秀なDNAを持つ人類を人工的に生み出す研究所で誕生した天才・悟による、行き詰まった進化を飛躍させるための実験の暴走という物語が合流する。それがメインストーリーです。
その本筋の合間に、少子化、対アメリカ外交、リーダーシップの不在、戦争、想像力の欠如、グローバリゼーションといった、今此処にある危機を象徴させるエピソードを飛び石のように置く。そのことによって、『マボロシの鳥』でも奏でられていた、前に進み続けようとする人類が生み出してきた文明に対する絶対的な信頼というテーマを、批判的な検討を加えながらより多角的に、より重層的に謳い上げたのが『文明の子』という小説なのです。しかし、その試みが全面的に成功を収めているかといえば、そうではありません。優秀な文芸編集者がついていたなら簡単に手直しできたであろう傷はあります。子供の会話は巧みでも、成人男女のそれは作りものめいているという弱点も目立ちます。でも、少なくとも、冒頭で挙げたデビュー作における欠点は見事に修正されています。このまま書き続ければ、いつか“量子飛躍”を遂げるかもしれない。その可能性の芽はたしかに読み取ることができました。次回作の完成を、今度は“楽しみに”待ちたいと思います。
【この書評が収録されている書籍】
「伝わってほしい思いや考えを、一から十まで説明し、その窮屈な語りによって、小説世界を平板にしてしまっている。また、作者が芸人だからかもしれないが、オチをつけなきゃという意識が強すぎるあまり、収録作品のどれもこれもが、読者をわかりやすい感情に誘導する陳腐な終わり方になっている」
ここまで酷評したのですから、わたしには『文明の子』を読む責任があります。で、最初に置かれた、鳥が文明を築いた星の話「光と風」を読みながら「またか」とがっかりしたわけです。また、寓話風のショートSFを読まされるのか、と。でも、それは早とちりでした。ジョン・レノンを殺した犯人の強い思いに引き寄せられたサンタクロースの話や、遺伝子操作によって高い知能を獲得したネズミの話、ピーター・パンになぞらえられる赤ちゃんポストに捨てられた子供の話、滅亡した地球でロボットを友として生きる博士の話など、『文明の子』には、それぞれ一見関係のなさそうな短い話が並んでいます。うっかりした読者なら短篇集と思うかもしれません。しかし、これは長篇小説です。けいれん的時間旅行者を主人公にしているため、時空があちこちへ飛ぶという構成になっているカート・ヴォネガットの『スローターハウス5』。その語りのスタイルに、次元の移動も加えるという野心から生まれた小説なのではないか。勝手な想像なので間違っているかもしれませんが、少なくともそういう“読み”を誘発する結構にはなっているんです。
人間の強い思いを示す電磁波の粒子を、光速に近いスピードで衝突させ核合成することで、人間が望む何かを出現させるマシーンを作った天馬博士。その試運転で、空飛ぶクジラを出現させてしまう孫のワタル。幼いワタルが、動物と会話ができる孤独な少年マナブと出会い、空飛ぶクジラにのって次元を超える冒険に繰り出す物語に、優秀なDNAを持つ人類を人工的に生み出す研究所で誕生した天才・悟による、行き詰まった進化を飛躍させるための実験の暴走という物語が合流する。それがメインストーリーです。
その本筋の合間に、少子化、対アメリカ外交、リーダーシップの不在、戦争、想像力の欠如、グローバリゼーションといった、今此処にある危機を象徴させるエピソードを飛び石のように置く。そのことによって、『マボロシの鳥』でも奏でられていた、前に進み続けようとする人類が生み出してきた文明に対する絶対的な信頼というテーマを、批判的な検討を加えながらより多角的に、より重層的に謳い上げたのが『文明の子』という小説なのです。しかし、その試みが全面的に成功を収めているかといえば、そうではありません。優秀な文芸編集者がついていたなら簡単に手直しできたであろう傷はあります。子供の会話は巧みでも、成人男女のそれは作りものめいているという弱点も目立ちます。でも、少なくとも、冒頭で挙げたデビュー作における欠点は見事に修正されています。このまま書き続ければ、いつか“量子飛躍”を遂げるかもしれない。その可能性の芽はたしかに読み取ることができました。次回作の完成を、今度は“楽しみに”待ちたいと思います。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする