書評
『奇術師』(早川書房)
やっと……。クリストファー・プリーストの『奇術師』が書店に並んでいるのを見て、安堵の溜め息をついた意味は、『魔法』を読んだ方ならご理解いただけましょう。かつて早川書房から出ていた、夢の文学館シリーズの一冊として刊行。この世に存在する三角関係をモチーフにした小説中もっとも奇妙な物語で、最終行に至っても「?」が駆けめぐり、最初から読み返さずにはいられない、まさにマジックのごとき逸品が『魔法』だったのです。一九九五年に出た、かの本の訳者あとがきに記されていた〈今年待望の新作長篇 The Prestige が発表された〉、その作品が二〇〇四年の今、ようやく訳出あいなったのだから、深い溜め息ももれようというもので。さて、では、それだけ待たされた作品の出来映えはというと――。
物語は、ジャーナリストのアンドルーが、ある宗教団体で起こった眉唾ものの奇跡に関する記事をフォローするために、列車に乗りこむシーンから幕をあけます。が、ニュースソースを提供するからと、彼を呼び寄せた女性ケイトから聞かされたのは宗教団体の話などではなく、自分と彼女の出自にまつわる話。二人の祖先は、それぞれ〈瞬間移動〉を持ちネタにしていた十九世紀末の天才奇術師で、終生激しいライバル関係にあったのです。そして、その確執は子孫である自分たちにも深い影を落としているのだ、と。
実はアンドルーは養子として今の両親にもらわれているので、実の親の顔を知りません。ごく幼い頃から、分身のような存在からサインを送られているという強烈な感覚を覚えることがあり、自分には双子の兄弟がいたのではないかと思うに至ったアンドルーは、長じて戸籍などを調べてみたのですが、そんな形跡はまるで残っていないのでした。しかし、ケイトの話を聞いているうちに、かつての疑念を再燃させたアンドルーは――。
アルフレッド・ボーデン、ルパート・エンジャという二人の奇術師が残した手記と日記。物語の大半はその記述に費やされています。憎悪という強い感情を共有しあった二人だけに、そこで触れられている出来事は度々重複しており、しかし、書き手が変わればこれほど見える光景が違うものかというほど、その内容は異なっているのです。それが、全編を彩る“語り=騙(かた)り”のほんの手始め。この騙りがもたらすズレは物語が進むほどに大きくなっていくのですが、そのズレは最後に用意された“双子=分身=ドッペルゲンガー”にまつわる大きな騙りによって一本に収斂していき、やがて哀しくも不気味な光景を出現させるのです。この奇術のトリックを彷彿させる記述のテクニックは、さすが騙り名人プリーストの面目躍如というべきで、思わず唸らないではいられません。
が、若干の不満もあります。訳す際に二人の文体に変化をもたせていないためか、同じ出来事について二つの視点で語(騙)りあうというパートがどうしても冗長に感じられてしまうのです。そんなイライラは最終章に用意されている驚愕で帳消しになるわけですし、そうした懇切丁寧な筆致が大半の読者にとってはわかりやすさにつながっていくことも了解できます。けれど、『魔法』におけるタイトな語り口、それがもたらすクールな現実崩壊感、説明抜きの不親切ぎりぎりの騙り性に魅了された身には、そのくどさ(親切)が物足りなく感じられるのも正直な感想なのです。
とはいえ、そんな無いものねだりをしたくなるのも、相手がプリーストだからこそ。奇術という娯楽芸術のバックステージものとして、アクロバティックな分身譚として、驚天動地のSF小説として、存分に楽しめる内容であるのは間違いありません。先述したとおり、親切な語り(騙り)になっていますから、プリースト初心者にこそおすすめしたい一冊なんであります。
【この書評が収録されている書籍】
物語は、ジャーナリストのアンドルーが、ある宗教団体で起こった眉唾ものの奇跡に関する記事をフォローするために、列車に乗りこむシーンから幕をあけます。が、ニュースソースを提供するからと、彼を呼び寄せた女性ケイトから聞かされたのは宗教団体の話などではなく、自分と彼女の出自にまつわる話。二人の祖先は、それぞれ〈瞬間移動〉を持ちネタにしていた十九世紀末の天才奇術師で、終生激しいライバル関係にあったのです。そして、その確執は子孫である自分たちにも深い影を落としているのだ、と。
実はアンドルーは養子として今の両親にもらわれているので、実の親の顔を知りません。ごく幼い頃から、分身のような存在からサインを送られているという強烈な感覚を覚えることがあり、自分には双子の兄弟がいたのではないかと思うに至ったアンドルーは、長じて戸籍などを調べてみたのですが、そんな形跡はまるで残っていないのでした。しかし、ケイトの話を聞いているうちに、かつての疑念を再燃させたアンドルーは――。
アルフレッド・ボーデン、ルパート・エンジャという二人の奇術師が残した手記と日記。物語の大半はその記述に費やされています。憎悪という強い感情を共有しあった二人だけに、そこで触れられている出来事は度々重複しており、しかし、書き手が変わればこれほど見える光景が違うものかというほど、その内容は異なっているのです。それが、全編を彩る“語り=騙(かた)り”のほんの手始め。この騙りがもたらすズレは物語が進むほどに大きくなっていくのですが、そのズレは最後に用意された“双子=分身=ドッペルゲンガー”にまつわる大きな騙りによって一本に収斂していき、やがて哀しくも不気味な光景を出現させるのです。この奇術のトリックを彷彿させる記述のテクニックは、さすが騙り名人プリーストの面目躍如というべきで、思わず唸らないではいられません。
が、若干の不満もあります。訳す際に二人の文体に変化をもたせていないためか、同じ出来事について二つの視点で語(騙)りあうというパートがどうしても冗長に感じられてしまうのです。そんなイライラは最終章に用意されている驚愕で帳消しになるわけですし、そうした懇切丁寧な筆致が大半の読者にとってはわかりやすさにつながっていくことも了解できます。けれど、『魔法』におけるタイトな語り口、それがもたらすクールな現実崩壊感、説明抜きの不親切ぎりぎりの騙り性に魅了された身には、そのくどさ(親切)が物足りなく感じられるのも正直な感想なのです。
とはいえ、そんな無いものねだりをしたくなるのも、相手がプリーストだからこそ。奇術という娯楽芸術のバックステージものとして、アクロバティックな分身譚として、驚天動地のSF小説として、存分に楽しめる内容であるのは間違いありません。先述したとおり、親切な語り(騙り)になっていますから、プリースト初心者にこそおすすめしたい一冊なんであります。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
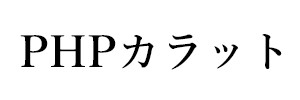
PHPカラット(終刊) 2004年9月号
ALL REVIEWSをフォローする








































