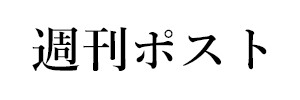書評
『異都憧憬 日本人のパリ』(平凡社)
人は芸術の都としてパリに憧れる。とりわけ、明治の末から大正期にかけて、日本の芸術家や文学者がパリに対して抱いていた憧憬(しょうけい)は強かった。だが、その憧憬がどこからきたのかということになると、いまひとつ納得いく説明を見いだすことができなかった。
本書は、高村光太郎、島崎藤村、金子光晴といった芸術家、文学者などが、パリ体験という形を通して突き詰めざるを得なかった異文化理解の問題を詳細に論じたものだが、なによりもユニークなのは、彼らがパリに対して抱いていたこうした憧憬が、どのような過程を経てできあがっていったかという問題を、ボヘミアン神話の解明を手掛かりにして考察した点にある。
著者によれば、社会の道徳や価値にとらわれず自由な生活を送る芸術家、すなわちボヘミアンという神話は、黒田清輝や久米桂一郎に続いてパリに留学した画家岩村透が書いた『巴里の美術学生』によってもたらされたという。
岩村透は、自らが留学したパリの画塾、アカデミー・ジュリアンの美術学生たちの自由で底抜けに明るい生活を活写するというかたちで、日本に初めてボヘミアニズムを紹介したが、そこで、彼が目的としたのは「求道と放恣(ほうし)が不即不離であるパリの美術学生の姿を通じて、実は《近代日本洋画家と社会》について論じる」ことだった。つまり岩村はブルジョワ的な価値観と対立しながら自らの芸術を生み出していく芸術家という新しいライフ・スタイルを日本に創り出すことで、同時に彼らの存在を許す芸術家の都パリのイメージを定着させたのである。
ところで、こうしたボヘミアニズムの元をただせば、十九世紀の中頃に、アンリ・ミュルジェールが書いた小説『ボヘミアン生活の情景』に行き着くが、著者はミュルジェールがボヘミアンというものを、芸術を信仰とみなして貧乏に殉教する「無名のボヘミアン」と、安定した生活に入る前の通過儀礼として、貧乏な芸術家の生活に耐える「公式のボヘミアン」の二つに分けていることに注目する。
とりわけ後者のライフ・スタイルに注意を促す。というのも、日本人を初めとする外国人の芸術家や文学者にとって、パリとは、まさに、そうした安定した価値観の社会へ入るためのひとつの通過儀礼としての役割を担っていたからである。
すなわちパリは「自国の文化との葛藤から一時的にせよ放免され得る唯一の場所」として、いいかえれば、外国人の「公式のボヘミアン」を育てる教育装置として機能していたのである。
ボヘミアン神話から生まれたパリへの憧憬、それは、じつは、「今」「ここ」にない自分自身への憧憬にほかならなかったのである。
【この書評が収録されている書籍】
本書は、高村光太郎、島崎藤村、金子光晴といった芸術家、文学者などが、パリ体験という形を通して突き詰めざるを得なかった異文化理解の問題を詳細に論じたものだが、なによりもユニークなのは、彼らがパリに対して抱いていたこうした憧憬が、どのような過程を経てできあがっていったかという問題を、ボヘミアン神話の解明を手掛かりにして考察した点にある。
著者によれば、社会の道徳や価値にとらわれず自由な生活を送る芸術家、すなわちボヘミアンという神話は、黒田清輝や久米桂一郎に続いてパリに留学した画家岩村透が書いた『巴里の美術学生』によってもたらされたという。
岩村透は、自らが留学したパリの画塾、アカデミー・ジュリアンの美術学生たちの自由で底抜けに明るい生活を活写するというかたちで、日本に初めてボヘミアニズムを紹介したが、そこで、彼が目的としたのは「求道と放恣(ほうし)が不即不離であるパリの美術学生の姿を通じて、実は《近代日本洋画家と社会》について論じる」ことだった。つまり岩村はブルジョワ的な価値観と対立しながら自らの芸術を生み出していく芸術家という新しいライフ・スタイルを日本に創り出すことで、同時に彼らの存在を許す芸術家の都パリのイメージを定着させたのである。
ところで、こうしたボヘミアニズムの元をただせば、十九世紀の中頃に、アンリ・ミュルジェールが書いた小説『ボヘミアン生活の情景』に行き着くが、著者はミュルジェールがボヘミアンというものを、芸術を信仰とみなして貧乏に殉教する「無名のボヘミアン」と、安定した生活に入る前の通過儀礼として、貧乏な芸術家の生活に耐える「公式のボヘミアン」の二つに分けていることに注目する。
とりわけ後者のライフ・スタイルに注意を促す。というのも、日本人を初めとする外国人の芸術家や文学者にとって、パリとは、まさに、そうした安定した価値観の社会へ入るためのひとつの通過儀礼としての役割を担っていたからである。
すなわちパリは「自国の文化との葛藤から一時的にせよ放免され得る唯一の場所」として、いいかえれば、外国人の「公式のボヘミアン」を育てる教育装置として機能していたのである。
ボヘミアン神話から生まれたパリへの憧憬、それは、じつは、「今」「ここ」にない自分自身への憧憬にほかならなかったのである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする