書評
『イッツ・オンリー・トーク』(文藝春秋)
語り手は新聞社で働いていたものの精神に失調をきたし、今は売れない絵を描いて貯金を切り崩す生活を送っている三〇代の〈私〉。物語は早朝の蒲田駅前で、〈私〉が演説中の都議会議員から拡声器で名前を呼ばれる場面から始まる。それは大学時代の友だち・本間だったのだけれど、やがて読者には彼がED(勃起障害)だということが告げられる。今も病院に通い、薬を服用し、男とみれば〈誰とでもしてしまう〉〈私〉が、この小説世界の中で心通わせるのは、本間をはじめ、皆どこか少し壊れた人物ばかりだ。
〈私〉は退屈した主婦や少し頭の弱い巨乳ちゃんになりすます出会い系サイトのバイトで知り合った痴漢のkさんと時々会う。痴漢をしてもらうのだ。kさんは〈垂れ目で頭が少しさびしい四十代だが、私が好きなタイプの禿(は)げ方〉をしており、彼の触り方は〈愛がないのに心がこもって〉いる。二歳年下の鬱病のヤクザ・安田もまたネット上で知り合った人物。〈私の、メンタル系の病気のサイト、つまり躁鬱や神経症の人間が集まるホームページにリンクをたどってやって来〉たのだ。
この作品で一番キャラが立っている〈私〉のいとこの祥一も、自殺予告メールを送ってくるような男。〈長いことパチプロをやっていたが昨年末に大損して種銭がなくなってからは女の家に転がり込んでヒモになった〉が、彼女に新しい男が出来て捨てられ、〈こいつは何かを見つけないと繰り返し狂言自殺するに違いない〉と心配した〈私〉に誘われるまま福岡からジャージ姿で転がり込んできた祥一が、本間の選挙活動のボランティアを始めるあたりから、語りのトーンに愛嬌とユーモアが加わり、それが物語を豊かにふくらませていく。〈誰かにおやすみって言われたのはひさしぶりばい〉なんて言ったり、選対事務所の〈思想屋のおばさん〉に叱られてへこんだり、一緒に銭湯に行けば男湯のほうから「おーい姫やー」なんて呼びかけたり、可愛いったらありゃしない。作者はこのヘンテコないとこに関して、読者にひとつの罠を仕掛けているのだけれど、そのタイミングが絶妙なのである。罠にはまった瞬間、頭の中で「!」と「?」がせめぎあい、あわてて祥一の登場シーンを全部読み返さずにはいられない。そして、この仕掛けによって読者の祥一への愛は一層深まるのである。
この小説はそうした少しずつ壊れた人物たちが、不安定な姿勢ながらも自分の足で立ち、時によりかかりあいながらも、ベタついた交歓とは無縁にすれ違っていく様を描いて清潔だ。
でも、そうした病んでいるがゆえに存在感を示すキャラクターたちの陰に隠れて見逃されがちな一人の人物の存在を抜きにしては、この小説は始まりもしないし、終わりもしないと思う。それは、新聞記者の特権意識を丸出しにしていた頃の〈私〉に唯一説教をしてくれた友人・理香。彼女が二六歳の時に事故で他界したのをきっかけに、〈私〉の心はバランスを失いはじめたのだ。
おそらくは、〈私〉が躁の時は暴走を押さえ、鬱の時は気持ちを引き立ててくれたであろう理香について、この小説は多くのことを語らない。でも、彼女の存在が〈私〉の要(かなめ)であるように、作品に対してもまた、その役割を果たしているのだ。もうここにはいない者によって支えられる、今ここにいる者の物語。このひっそりと静かな気配の仕掛けもまた、絶妙というべきであろう。理香の命日で終わるこの物語を、語り手は〈イッツ・オンリー・トーク、全てはムダ話〉とアイロニカルに突き放す。が、もちろんそうではない。第一三〇回芥川賞は受賞できなかったけれど、これは新人のデビュー作品としては、瞠目すべき秀作なのだから。
【この書評が収録されている書籍】
〈私〉は退屈した主婦や少し頭の弱い巨乳ちゃんになりすます出会い系サイトのバイトで知り合った痴漢のkさんと時々会う。痴漢をしてもらうのだ。kさんは〈垂れ目で頭が少しさびしい四十代だが、私が好きなタイプの禿(は)げ方〉をしており、彼の触り方は〈愛がないのに心がこもって〉いる。二歳年下の鬱病のヤクザ・安田もまたネット上で知り合った人物。〈私の、メンタル系の病気のサイト、つまり躁鬱や神経症の人間が集まるホームページにリンクをたどってやって来〉たのだ。
この作品で一番キャラが立っている〈私〉のいとこの祥一も、自殺予告メールを送ってくるような男。〈長いことパチプロをやっていたが昨年末に大損して種銭がなくなってからは女の家に転がり込んでヒモになった〉が、彼女に新しい男が出来て捨てられ、〈こいつは何かを見つけないと繰り返し狂言自殺するに違いない〉と心配した〈私〉に誘われるまま福岡からジャージ姿で転がり込んできた祥一が、本間の選挙活動のボランティアを始めるあたりから、語りのトーンに愛嬌とユーモアが加わり、それが物語を豊かにふくらませていく。〈誰かにおやすみって言われたのはひさしぶりばい〉なんて言ったり、選対事務所の〈思想屋のおばさん〉に叱られてへこんだり、一緒に銭湯に行けば男湯のほうから「おーい姫やー」なんて呼びかけたり、可愛いったらありゃしない。作者はこのヘンテコないとこに関して、読者にひとつの罠を仕掛けているのだけれど、そのタイミングが絶妙なのである。罠にはまった瞬間、頭の中で「!」と「?」がせめぎあい、あわてて祥一の登場シーンを全部読み返さずにはいられない。そして、この仕掛けによって読者の祥一への愛は一層深まるのである。
この小説はそうした少しずつ壊れた人物たちが、不安定な姿勢ながらも自分の足で立ち、時によりかかりあいながらも、ベタついた交歓とは無縁にすれ違っていく様を描いて清潔だ。
でも、そうした病んでいるがゆえに存在感を示すキャラクターたちの陰に隠れて見逃されがちな一人の人物の存在を抜きにしては、この小説は始まりもしないし、終わりもしないと思う。それは、新聞記者の特権意識を丸出しにしていた頃の〈私〉に唯一説教をしてくれた友人・理香。彼女が二六歳の時に事故で他界したのをきっかけに、〈私〉の心はバランスを失いはじめたのだ。
おそらくは、〈私〉が躁の時は暴走を押さえ、鬱の時は気持ちを引き立ててくれたであろう理香について、この小説は多くのことを語らない。でも、彼女の存在が〈私〉の要(かなめ)であるように、作品に対してもまた、その役割を果たしているのだ。もうここにはいない者によって支えられる、今ここにいる者の物語。このひっそりと静かな気配の仕掛けもまた、絶妙というべきであろう。理香の命日で終わるこの物語を、語り手は〈イッツ・オンリー・トーク、全てはムダ話〉とアイロニカルに突き放す。が、もちろんそうではない。第一三〇回芥川賞は受賞できなかったけれど、これは新人のデビュー作品としては、瞠目すべき秀作なのだから。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
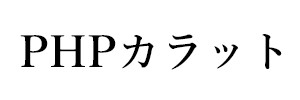
PHPカラット(終刊) 2004年6月号
ALL REVIEWSをフォローする




































