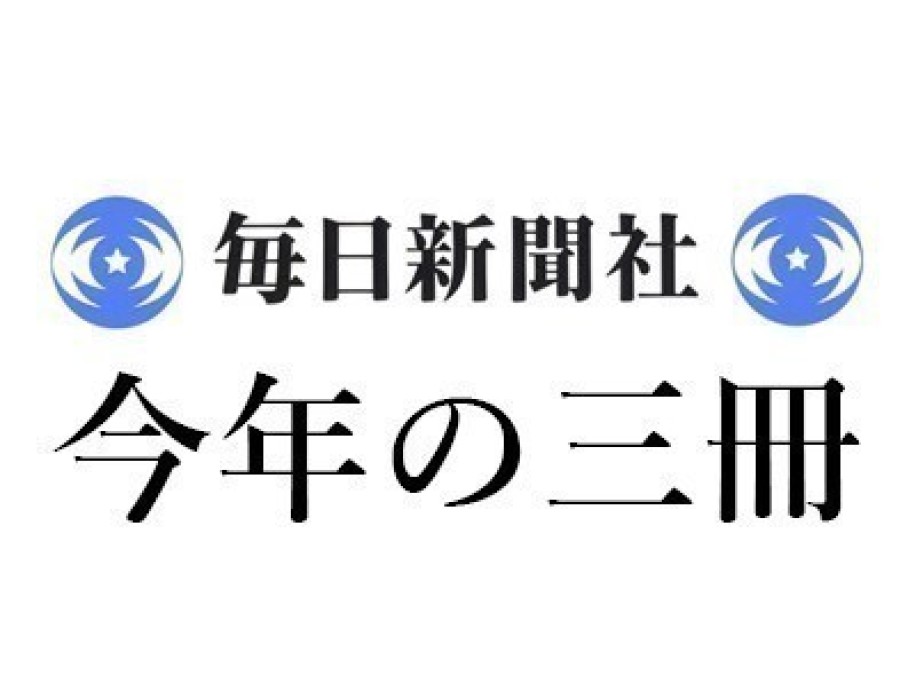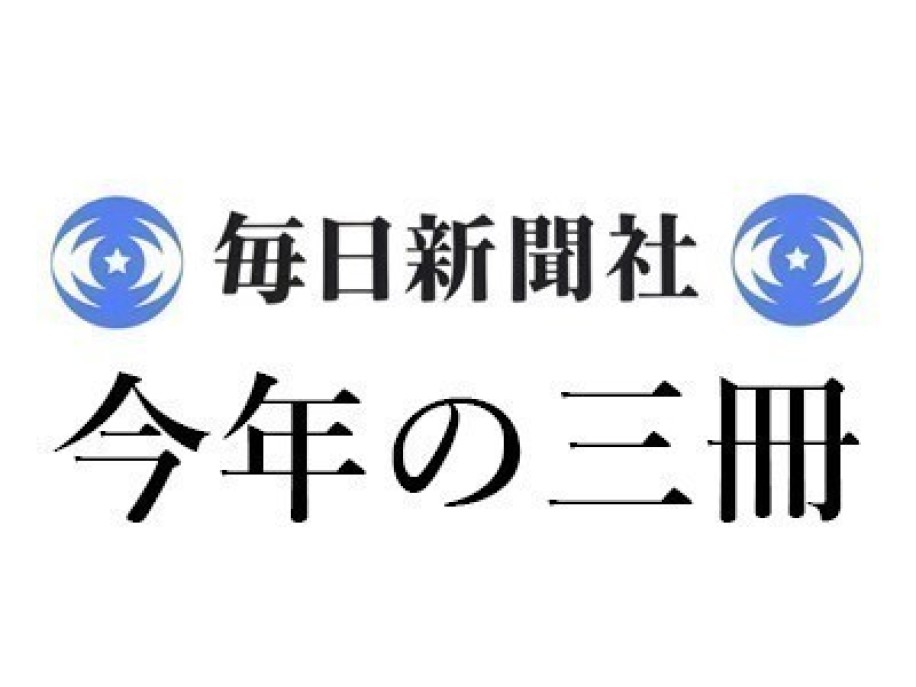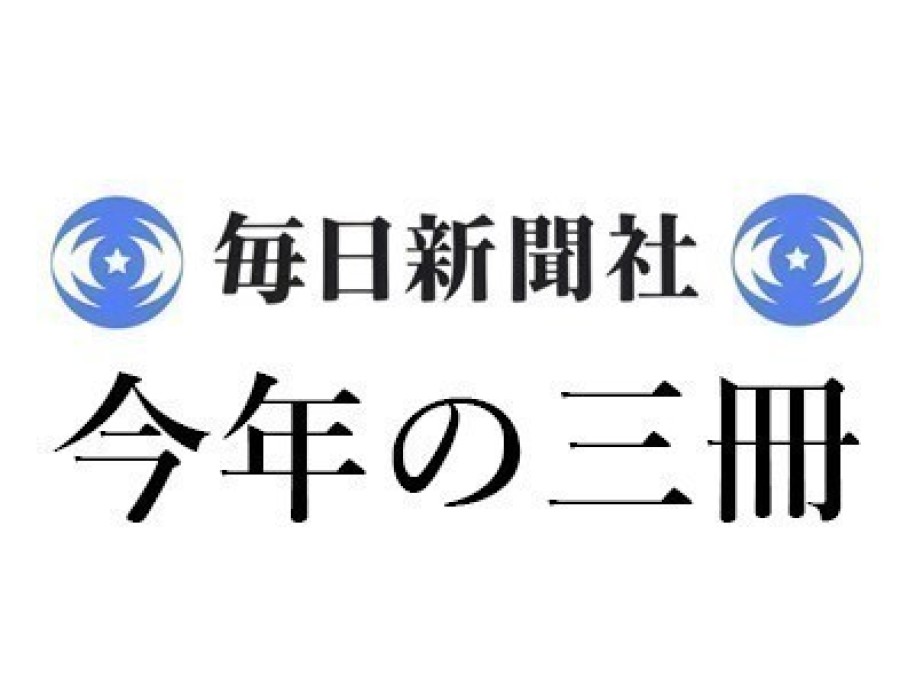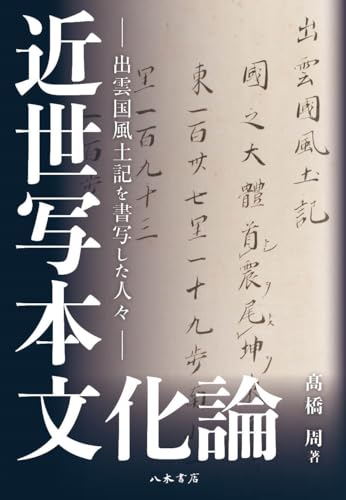書評
『番茶菓子』(講談社)
知恵あるおばさんの眼
二月は梅の匂う月、三月はものの芽の萌(きざ)す月、と幸田文は書いている。でもまだ寒い。こたつの中で、みかんの筋をとりながら、『番茶菓子』(講談社文芸文庫)を読む。あちこちに発表されたエッセイ。しかし雑文のよせ集めという感じがまったくないところがすごい。一つ一つが粒立って、掌編小説のよう。もったいない。ゆっくり読もう。
たとえば「午後」。春のとろっとした午後に客を待つ。客は二人だが別々に来た。四十を超した男と女。もつれるくせに繋(つな)がらない、長い間柄。「男はその数年間を、あるときはひとり燃え、あるときはひとり冷え、女の結婚を機にして気もちを新しくした」。ところが女は終戦後、離婚して引き揚げてくる。「だんだん苦しく、だんだん暇のない日々になって行って、だがそのわりに若さ美しさを保っていた」。一度話し合おうということになり、著者が家を提供する。
台処は夕がたになると花やいで明るくなる。西に窓があるせいだ。時計がなくても時間はわかる。私はそろそろ豌豆(えんどう)の蔓を取ったりしはじめていると、女が泣いた顔で帰る挨拶をした。
そっと二人に任せながら、待つ文さんの手の動き、見えない時計のコチコチいう音まで聞こえるようではないか。
あとに残った男は「あのひとの時間は二十年前に停止しちまったんじゃないかな」という。女の進歩のなさ、それを自分に言われているような痛さで聞く。庭を見て、おやっと思う。花が荒れ、枝がへし折れている。まさかあのひとが……。
煙草を吸い男は、「猫ですよ。……花は台なしになったけど、そのおかげで僕、あのひとに憎まれ口利きたいのをこらえきった」
たった三頁ほどの男と女というもののドラマ。それをみつめる智恵のある「おばさん」の深くきびしく、温かなまなざし……。
本の背後に、里の父こと幸田露伴の声がかすかに遠い海鳴りのようにひびく。
「好色ものは用心しないと思わぬときに記憶がよみがえるものだ」
これは「梅暦」をよんだ娘にいったことば。
「なにも雪の中のたけのこをたべたいと云うんじゃない。菜っぱの煮びたしとさんまの焼いたので沢山なのだ。だからさんまをうまく焼いて食わしてくれ」。
それに応えるべく七輪の上で、しゅぷしゅぷいってるさんまの皿を運びつけると、その格好があわてて不様(ぶざま)だと父なる人はわらう。「敵討じゃないよ。昼飯だよ」
著(き)るものについての話も多い。なかのいい友だち三人、集まれば、相手の新しい半襟を「いい色だこと」と誉めながら、大抵はむこうの健康も精神状態も見当がつくという。
「ありあわせで結構、よりよく著ることであるだけだ。たとえ浴衣に狭帯(せまおび)すがたでも、せめてその日だけはノー・エクスキューズ、弁解なしの誇りをもとう」という文さんのきっぱりした言葉。着替える暇なく会合にかけつけ、しどろもどろに服の弁解ばかりしている私は背中をどん、と励まされる。
三人の子を一人で養おうと思えば、何かとゆきとどかぬ私の暮らし。習い事もさせてやれないし、勉強も見てやれないし、とときに後ろめたい。だけど文さんは「木の実・こども」という小文で、こういってくれる。
親木も元気で丈夫で快活できどっていない。鈴なりの子供はさくさくと甘く、まっかでいきいきと沢(つや)がある。こう来なくてはほんとうじゃない。
幸田文という人は、何から何まで私にとってビタミン剤のような作家である。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
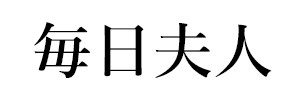
毎日夫人(終刊) 1993年~1996年
ALL REVIEWSをフォローする